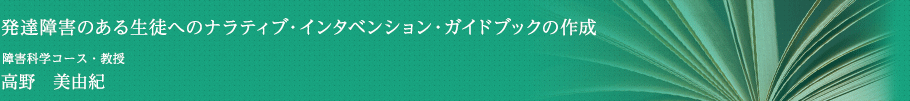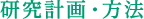
【平成28年度】
本研究では、語りに関して学校で先駆的に行われた活動を集積し、効果を支持する背景理論を整理し、教師にとって使い易いプログラムを開発する。
1)発達障害のある生徒のためのナラティブ・インタベンションの素案を作成する。
時期:平成28年6月~9月
方法:➀ narrative intervention programme (Joffe, 2011)のプログラムのポイントや、StorySharing™での支援者の態度を抽出(担当:高野、有働が専門家に助言を受けて行う)
(経費:謝金2H×1人分、交通費1人分)。
②日本の中学生・高校生の興味関心に沿った教材の選定(担当:高野、上田、武田)。
④ 評価方法の検討(担当:主に高野)。
2)ナラティブやお話語り(ストーリーテリング)を導入した教育実践を分析する。
時期:平成28年9月から平成29年1月
- ①中学校等で実践した資料の分析(担当:研究組織の全員)
- Groveによる日本の中学校特別支援学級や小学校、特別支援学校高等部で行ったマルチセンソリー・ストーリーテリングや先行研究を児童生徒の効果、語り手の工夫の観点から分析する。分析にはELANや会話分析、現象学的分析等を採用する予定である。
- ②大学院修士課程の授業(障害児保健研究)での実践を分析(担当:高野)
- マルチセンソリー・ストーリーテリングの具体的な方法(音楽療法や言語訓練からのヒントを含む)を授業の中で紹介する。履修生の感想を分析する。
(経費:外部講師への謝金2H×3人分、交通費3人分)
3)ナラティブ・インタベンション・ガイドブックを作成する。
時期:平成28年12月から平成29年2月
担当者:高野を中心に研究組織の全員
平成28年12月に会議を持ち、ガイドブックの構成を全員で検討し、役割を分担する。現時点では、背景知識(理論)、プログラム(15回)、教材の参考資料、評価方法を含める予定であるが、1)2)の途中経過を踏まえて修正する。平成29年2月中旬を原稿締め切りとし、3月中旬に印刷を仕上げる。
Ⅱ.生命倫理・安全対策等に関する留意事項
本研究は、文部科学省・厚生労働省の「疫学研究に関する倫理指針」、個人情報保護法及び兵庫教育大学規定のガイドラインに従って行う。
- ・研究の対象者に対しては、研究に対する十分な説明および同意(同意書)を得る。特に学校での授業において研究協力いただく場合も可能性があるが、その際には研究代表者および担当教員の両方から学生あるいは生徒本人に依頼をわかりやすく説明し、中学校等の場合には保護者への説明も行う。紙面での説明と同意を得る。
- ・個人情報は、必要最小限の情報のみを扱い、得られた情報は、研究以外の目的には使用しないことを徹底する。観察記録を含めて、個人情報の保護・管理の徹底を図る。
- ・特に、本研究は障害のある子どもに関連する人々を研究対象としており、児童の安全や人権に不安要素の多い社会情勢にあっては、より慎重な処理が必須であるという認識に立っている。
これらの旨は研究分担者と共有する。