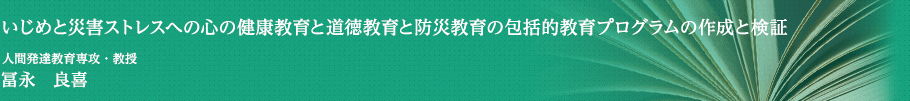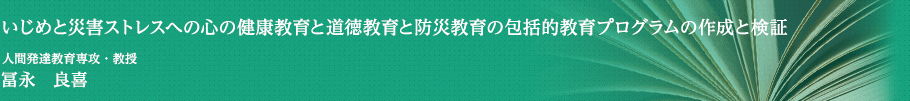
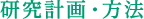
【平成26年度】
- 1)いじめと災害-子どもの命と子どもが命を守る教育研究企画シンポジウム開催と研究打ち合わせ(全研究者):大学院生・大学生・教育関係者を対象に、企画趣旨講演(冨永)・大災害後の子どもの心のケア(山本・大谷)・大災害後の防災教育(森本・定池)・いじめ防止の道徳授業(淀澤)・いじめとストレス授業(井上)を話題提供者としキックオフ・シンポジウムを公開で行う。その後2年間の研究打ち合わせを行う(会場:神戸HLC)。
- 2)証拠に基づいた教育を進めるためのいじめ意識アンケートやストレス尺度開発と検証(山本、本間、大谷):いじめ被害・いじめ加害の行動レベルといじめ加害抑止や助長意識についてのアンケートを開発する。また、いじめや災害というトラウマストレスを測る尺度は医学や心理学に基づいた尺度は開発されているが学校教育で活用しやすい尺度は充分ではない。そのため学校教育で活用できるいじめ意識アンケートとストレスアンケートを開発検証する。
①岩手13 万人の児童生徒に2011 年度から3年間「心とからだの健康観察」(小学生19 項目版、中高校生31 項目版)を実施してきた、そのストレス尺度の信頼性と妥当性と検討するとともに、被災経験・被支援経験の経年変化を分析する。そのため、心とからだの健康観察統計分析会議を行う(山本、大谷、小塩真司(統計専門家)、冨永:東京にて会議を行う)。
②いじめ意識尺度を開発し、小学校3校・中学校4 校で実施し、その信頼性と妥当性を検討する(淀澤、井上真一(研究協力者・稲美中学教諭・大学院2年生)、冨永)。③防災教育に関する苦痛度尺度の信頼性と妥当性の検討をする。「津波という言葉を見たり聞いたりする」や「津波の映像をみる」など9項目からなる。被災地の沿岸部の小学校2校中学校3校で実施してきたデータの分析と結果を検討する(森本、定池、冨永)。
- 3)いじめ予防のための道徳授業と心の健康教育としてのストレスマネジメント授業の作成と効果検討いじめ防止対策推進法にはいじめの防止として道徳教育の充実が記載された。いじめ予防には、いじめは許されないという規範意識の育成といじめ被害による心身の打撃と回復及びいじめ加害者のストレスと加担者の同調性指摘される。道徳の時間には読み物教材を活用して道徳的価値を深め、特別活動や総合的学習の時間に体験活動を行うことを奨めている(淀澤,印刷中)。そのため規範意識や社会的ルールを育成する道徳授業案とストレスマネジメント授業案を作成しその効果を検証する。
授業案はパワーポイントで作成し、授業者による授業の均一化をはかる。中学校2校各4クラスにて、読み物教材を中心としたいじめの道徳授業と「いじめとストレス」の授業の実施順序をカウンターバランスする。事前事後にいじめ意識アンケートを実施して効果を検討する。
- 4)災害後の心のケアと防災教育の融合的取り組みの検討(定池・冨永)。
①災害後の防災教育と心理支援のあり方に関する面接調査(冨永・山橋直子(研究協力者・医療SSW・大学院2年生))
②語り継ぐ防災教育:奥尻津波を中学時代に体験した定池による防災学習会を岩手沿岸部の中学校で実施する。その前後に災害とストレスを学ぶ授業と防災教育の苦痛度尺度を実施し、効果を検討する。
【平成27年度(予定)】
- 1)心の健康教育・道徳教育・防災教育の融合的なカリキュラム試案の作成と提言(全研究者):津波被災地の中学校1校と関西の中学校1校をモデル校として、年間計画に、心の健康教育・道徳教育・防災教育を位置づけ、校務分掌・研修体制・生徒の感想などを分析する。
- 2)いじめと災害-子どもの命と子どもが命を守る教育成果報告シンポジウム(全員)。
- 3)日本心理臨床学会第34回大会にて成果発表