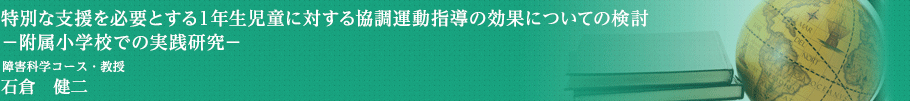
特別な支援を要する通常学級の低学年児童に対して協調運動の指導を行うことで、「感覚特性」「多動性・衝動性」「対人関係」「情緒」「書字」「読字」等が改善・向上することを実践的に明らかにする。
特別な支援を要する児童生徒への運動指導の実践については多くの報告がある。しかし、「対人関係」「情緒」との関連性や「書字」「読字」との関連性について標準化された方法で検討されたものは少ない。また、殆どの研究は対象児についての指導前後の比較研究であり、対照群と比較した研究は行われていない。
本研究では、「対人関係」「情緒」「書字」「読字」との関連性について標準化された方法で検討する。それにより、協調運動の指導によって改善・向上する事項を客観的に示すことができる。また、指導を行わない児童との比較を行うことで、指導効果についてエビデンスの高い検討が可能である点が大きな特色である。
特別な支援を要する児童生徒への運動指導は一般的によく行われているが、そのエビデンスを明確にしたものは少ない。本研究は標準化された方法で測定し、対照群との比較検討を行う点で、これまでにない研究デザインとなっている。
石倉研究室では協調運動について研究を多く行ってきているが、特別支援学級での指導実践、小学校での調査研究、レビュー研究にとどまってきた。一方で附属小学校は、特別な支援を要する児童への指導について模索をしている状況であった。
2021年度から附属小学校1年生の協調運動に関する調査を開始し、2022年1月に実施された入学試験からは協調運動についての課題を取り入れることで、入学前の協調運動と入学後の情緒・行動面や学習面との関係について調査を行ってきた。その一部は、2022年度「理論と実践の往還・融合」に関する共同研究活動として実施された。その成果の一部は、兵庫教育大学学校教育学研究36号に掲載している(近田・石倉・阿賀・冨田,2023)。
その共同研究の成果は継続し、附属小学校の入試問題と入学後の情緒・行動面や学習面との関係について、継続的に調査が行われ、現在も調査方法についての工夫が行われている。
附属小学校では個別の教育支援計画等が作成されている児童に対して「ちゃれんじ教室」という指導の場が設けられていたが、低学年向けの実践が未整備なままであった。2024年夏に石倉研究室にその実践についての打診があり、それに応えるために2024年10月から「からだ・ちゃれんじ」と称した指導の場を設けている。しかしそれは急遽始まった実践であり、調査・研究や実践のための準備が十分ではない。そのため、令和7年度の本申請を行うことで、実践研究としての体制を整えるものである。