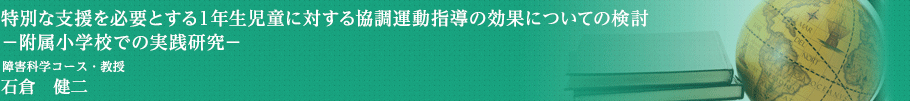
1)対象は、1年生の全児童とその保護者
2)調査内容は、それぞれの項目について以下の標準化されたテストを用いる。
・感覚特性:SSP(感覚プロファイル短縮版) ← 全保護者に調査
・多動性・衝動性、対人関係、情緒:SDQ(子どもの強さと困難さアンケート) ← 全保護者に調査
・書字、読字:URAWSS-Ⅱ(読み書き理解)又はPWT描線テスト(前書字技能テスト) ← 全児童に実施
3)研究の役割分担は、南屋・中尾の校内調整に基づき、石倉研究室(石倉及び大学院生)で調査を行う。
1)対象は、以下の2つの条件(a.b.)に合致する1年生児童5名程度。
a.個別の支援計画等が作成されている児童、又は担任や特別支援教育コーディネーターによって特別な支援が必要と判断された児童。
b.運動指導プログラムへの参加希望のある児童。第1クールと第2クールは別々に募集する。
2)指導の内容と方法
・石倉研究室の大学院生(修士課程/博士課程)複数名で、協調運動についての指導を行う。
・指導の具体的な内容や方法は、専門家(中根)の助言を得て実施する。
・水曜日の6時間目に6回程度実施する。
3)研究の役割分担は、冨田・南屋・中尾の校内調整に基づき、石倉研究室(石倉及び大学院生)で実施する。
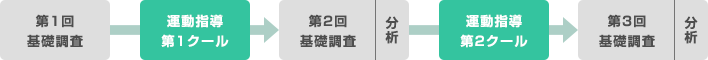
運動指導の前後に全児童(1年生)を対象に標準化されたテストを実施し、なおかつ希望者を対象に運動指導を実施することで、対象となる条件a.ではありながら指導の対象とはならなかった児童、又は対象となる条件a.以外で協調運動や書字・読字に特異性のある児童を対象群として、比較して分析することができる。
・特別な支援が必要と判断されても、運動指導の対象とならない児童がいることになるが、自由意思による参加希望に基づいて参加者が決定される。
・詳細は兵庫教育大学「人を対象とする研究に関する倫理審査委員会」に申請を行う中で検討する。
2026年3月頃に、大学構内(神戸キャンパス含む)又は附属小学校で研究報告会を行う。コメンテーターとして、研究組織外の専門家を招聘する。学内外に広報し、参加者は広く募るものとする。