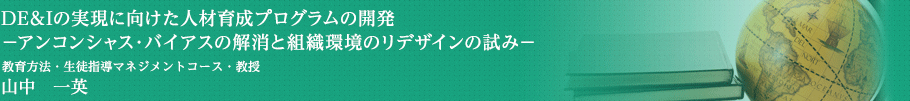
Diversity(多様性),Equity(公正性),Inclusion(包摂性)の頭文字をとったDE&Iは,現代のあらゆる組織にとって,そして社会全体にとっても,最も重大で大切な概念の一つになりつつある。VUCAと呼称される変化の激しい時代の中にあってDE&Iは,多様な人々が誰もがいきいきと活躍を続けながら生きがいをもって暮らしていくために,組織が推進すべき考え方であり,実現すべきビジョンなのである。ところがそうであるにもかかわらず,組織においてDE&Iを推進し実現していくのは,けっして容易なことではない。なぜならそこに,いくつもの障壁が存在しているからである。まずは,「アンコンシャス・バイアス(unconscious bias)」である。生活経験を通して無意識のうちに刷り込まれた,性別,職業,年齢等に対する価値観の偏り,認知の歪み,偏見や思い込み等を意味する概念である。人間に備わった心の仕組みがDE&Iの推進・実現を妨げてしまうのである。また,「組織環境」にも課題がある。たとえば「障害」について,それを個人の問題に還元することなく,組織内の成員や道具等との関係によって社会的に構成されるものと措定するなら,DE&Iの推進と実現は,組織環境のリデザインの問題として再構成されることになる。以上のように本研究では,アンコンシャス・バイアスと組織環境を,DE&Iの推進・実現を阻む主たる要因とみなし,研究を展開していくことにする。
本研究では,DE&Iの実現に向けて,アンコンシャス・バイアスの解消と組織環境のリデザインを企図した2つのフェーズからなる人材育成プログラムの開発を試みる。第1フェーズは,テーマに関連した学術的知見(社会心理学や特別支援教育等)のレクチャである。第2フェーズは,関連事例に基づいたエクササイズである。本研究の目的は,これら2つのフェーズの内容と方法の開発である。なお本研究が対象とする組織は,企業と学校である。DE&Iに関する実践は,企業が先駆する。その一方で遅滞しているかもしれないのが,学校である。したがって,企業と学校の両方を視野に入れることで,相補的で相乗的な展開が期待されるのである。
令和6年度は,上記プログラムの内容と方法の開発に注力する。そして令和7年度以降において,開発したプログラムの試行実践を重ねる予定である。
現在,多くの企業が,DE&Iの実現に向けた取り組みを加速させている。ところがそこでは,アンコンシャス・バイアスの解消という個人の心理過程に焦点をあてた取り組みが主であるように思われる。
本研究の独創性は,アンコンシャス・バイアスはもちろんのこと,それに加えて,組織環境をDE&Iの推進・実現の障壁として措定している点にある。「障害」の概念を例にとって説明したい。障害を個人のインペアメント(impairment)として定位すれば,障害は個人の問題に還元されてしまう。他方で障害を社会的な相互作用によって可視化されるディスアビリティ(disability)として捉えれば,障害は組織内の成員や道具等との関係の所産として社会的に構成されるものになる。このように障害を組織内の人的,物的リソースの布置連関の問題として定義したなら,DE&Iの推進と実現は,組織環境のリデザインの問題として再構成されることになるのである。
第2フェーズでは,事例(ケース)を用いたエクササイズが想定されている。教職大学院でもビジネススクール等の実践でも事例を用いた学習はめずらしいことではないが,アンコンシャス・バイアスの解消と組織環境のリデザインを同時に視野に入れたケース教材はそれほど多くないように思われる。また事例は,実際の出来事が言語化されたものである。「アンコンシャス(無自覚)」であるという特徴を考慮すれば,そうした事例のほうが,抽象度の高い理論よりも,現実感や当事者意識をもたらしやすいにちがいない。そして,多くの事例を収集すると,その中に相反するものが含まれていたり,感情を揺さぶるものがあったりする。読み手は事例の中に見出した矛盾や齟齬,喚起された感情等を手がかりに思考を重ねていくことができるだろう。その過程で,暗黙に保持する自らのバイアスを認識することができると想定されているのである。こうした点も,本研究の独創性といってよいであろう。
第1フェースで実施するレクチャの内容は,将来的に,DE&Iのテキスト等の出版物として刊行することができるであろう。また,試行実践を経た人材育成プログラムは,企業や学校へ「研修パッケージ」として提供することも可能であろう。
差別や偏見に関しては,長い学術研究の歴史があり,これまでに膨大な数の先行研究が蓄積されてきた。一方でアンコンシャス・バイアスやDE&Iは,「マイノリティ」と呼称される方々を取り囲む問題として,学術というよりは社会問題として,しかも近年になって,拡がってきた概念といってよいのかもしれない。「男女共同参画社会基本法」が制定されたのは平成11年だが,制定当時,ジェンダー平等について,現在ほど活発な議論は展開されていなかったように思われる。アンコンシャス・バイアスの解消やDE&Iの推進・実現は,当然のことながら大学を含めたすべての学校種で求められることであるが,企業での実践のほうが遥かに進んでいるように見受けられる。本研究は,差別や偏見に関する数多の学術研究の知見を,アンコンシャス・バイアスやDE&Iといった概念のもとで集約・整理するとともに,企業での社会的な実践と結び付ける役割を担っているといえよう。
DE&Iの推進・実現は,あらゆる組織のひいては社会全体の課題であろう。そうだとすれば,組織に籍を置く誰もが,この課題に誠実に向き合っていかなければならない。もとより兵庫教育大学には,DE&Iに繋がりの深い専門分野の研究者も多数在籍している。したがって,そうした学内の教員が協働することで,この課題の解決に大きな貢献ができるのではないかと考えられた。
産学協調のコンセプトの一つに,「産学共創教育(sharing education)」がある。本学と企業が共有課題であるDE&Iの推進・実現に向けて,人材育成プログラムを協働して開発するプロジェクトを立ち上げることがあるとすれば,それは「産学共創教育」の一つのかたちであり,本研究の取り組みがその一助になることが期待された。