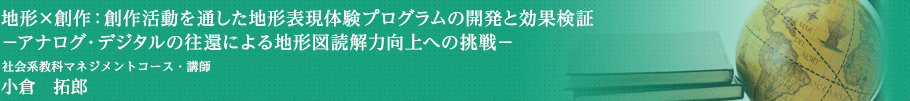
本研究の計画を図2に示す.紙粘土を用いて地形の3次元形状を表現する創作活動を通した地形表現体験プログラムを開発する.河川のはたらきによって形成される典型地形(扇状地,三角州,自然堤防など)に加えて,従来の地形図では表現が難しい地形(滝,ポットホールなど)をテーマとして,児童生徒らに紙粘土で3次元の地形模型を作ってもらう.ドローン測量由来の地形データを3Dプリントした模型をまねて紙粘土で地形を作ったり,模型表面にペンで景観を描いたりする授業も展開し,創作活動が苦手な児童生徒への配慮ができる教材も作成する.作成した地形模型と地図帳を組み合わせて,地形の凹凸や等高線の読み取り,地形と土地利用の関係等を考察させる授業を展開する.プログラム終了後には地形図読解に関する小テストを実施し,創作活動が地形図読解に与える影響や学習のモチベーションに関する検証を実施する.
研究期間前半には,創作活動が地形図読解に寄与できたかを,アナログ教材(地形図,地形模型)やデジタル教材(GISで作成した地図)を用いた事例と比較する.この結果を踏まえて教材やプログラムを改良し,研究期間後半には,創作活動とアナログ・デジタル教材を併用・往還するプログラムを作成し,複数の教材を組み合わせた地形図読解に関する効果検証を実施する.
研究代表者・研究分担者の相互関係 小倉が総括を行う.教材開発は2グループに分かれて実施する.中村・井上・田村・佐藤凌・古家・大西・桑名・亀井・佐藤学・笈田は,学習指導案および地形表現体験プログラムの計画立案を実施する.小倉・早川・山内・小林は,典型地形のドローン空撮と3Dデータ作成を実施する.随時Vincentと国際的な観点から学習モチベーションや教師のファシリテーションについて議論する.授業実践は,勤務先の校種(小:古家・桑名・亀井・佐藤学・笈田,中:佐藤凌・大西・井上,高:中村,大:小倉・早川・山内・小林・田村)にて展開し,校種(発達段階)に応じて地形理解がどう変化するかを検証する.9月に全員で中間検証を実施し,教材を改良して1月に効果検証の総括を行い,論文執筆を実施する.
主要設備との関連 ドローン空撮データの処理および野外調査で3Dデータを処理・閲覧できるノートPCを1台計上する.本研究で実施したアンケートやインタビュー調査の統計解析にも使用する.
経費と研究計画の関係性 メンバーの勤務先である兵庫県・神奈川県を中心に旅費を計上する.授業実践では,各校種の授業を2名以上のメンバー共同で実施する.校種(発達段階)による学習効果の差に着目しながら実践経験を共有し,研究グループ全体にフィードバックできる体制を構築する.

本研究では,個人情報を伴う質問紙調査・インタビュー調査を必要とする研究が含まれている.これらを実施する際には,事前に学内の倫理審査委員会にて承認を得た上で遂行する.
本研究の成果を現職教員と共有すべく,本学教育・言語・社会棟7Fの地域教材開発室でワークショップを実施する予定である.対象は学内外の教職員程度であり,紙粘土を用いた簡易的な地形模型作成のワークショップを実施する.参加者から教材やプログラムに対するフィードバックも受けて,次年度以降の教材改善や論文化に向けた議論を実施する.オンラインでも聴講可能な環境を整えることも検討している.