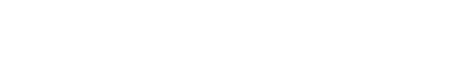現院生たちの日々の実際

Aさん
- 校種
- 義務教育学校(前期課程) 教諭
- 教育実践リフレクションでの取り組み
- 研究テーマ:「自尊感情を高める学級経営-アサーショントレーニング,勇気付け(アドラー心理学),ストローク理論(交流分析)を柱として-」。日々の教育カウンセリングや道徳教育を柱とした学級経営や生徒指導を通して、子供の自尊感情を高めていく、承認欲求や自尊感情尺度で、その変容を分析する。
- 1年次の時間割
- 自分自身の専門の教科(社会科)や、基本的な教育理論、そして普段の学校現場で生かせられるもの、生徒理解に関するものを学びたくて、授業を選択しました。また、2・3 年次での「研究プログラム」の履修を考えています。
| 前 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 6時限 (18:30~20:00) |
第二言語習得と外国語学習 | 授業における評価の基準作成理論と学力評価 | 道徳教育及び道徳授業の理論と実際 | 学校における道徳教育の実践研究 | |
| 7時限 (20:10~21:40) |
包括的児童生徒支援に関する事例研究 | ||||
| 集中講義 | 教育実践リフレクション | 包括的児童生徒支援に関する事例研究 | |||
| 後 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 6時限 (18:30~20:00) |
教育課程の制度的特質と課題 | ||||
| 7時限 (20:10~21:40) |
教員のための人権教育の理論と方法(夜間クラス)(前半) | 教育実践リフレクション | |||
| 集中講義 | 教職員職能開発と研修プログラムの開発 | 授業におけるICT活用 | |||
*後期は前期の反省を受けて、3 年長期履修なので、最低必要限の授業のみにしました。
- 1年間講義を受講してみて感じる学びやよろこび
- 目の前の仕事をこなすだけの日々ではなく、目の前の仕事(教育実践の課題)を研究ベースですすめられ、常にスーパーバイズ(指導助言)してくださる大学院の先生の存在自体が、有り難く、心強い。日々の生活が充実したものになった。

Bさん
- 校種
- 中学校教諭
- 教育実践リフレクションでの取り組み
- 研究テーマ:「これまでの教育理論」と「ICTを活用した授業実践」とのベストミックスを目指した授業づくり。専門教科である「社会科教育」を中心に、先行研究に学びながら授業実践及びその改善に取り組んでいます。
- 1年次の時間割
- 自分自身の専門の教科(社会科)や、基本的な教育理論、そして普段の学校現場で生かせられるもの、生徒理解に関するものを学びたくて、授業を選択しました。また、2・3年次での「研究プログラム」の履修を考えています。
| 前 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 6時限 (18:30~20:00) |
授業における評価の基準作成理論と学力評価 | 社会系教科の授業デザインの理論と方法 | 職員のための学校組織マネジメントの実践演習 | ||
| 7時限 (20:10~21:40) |
教育実践リフレクション | 児童生徒を活かす学級経営の実践演習 | 包括的児童生徒支援に関する事例研究 | 総合的な学習と特別活動のデザイン | |
| 集中講義 | 教えと学びの社会学 | ||||
| 後 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 6時限 (18:30~20:00) |
子ども理解と学級経営の心理学 | 初等社会科教材研究・授業づくり | 教職員職能開発と研修プログラムの開発 | ||
| 7時限 (20:10~21:40) |
実践的な指導方法に関する理論と実際 | 教員のための人権教育の理論と方法 | 教育実践リフレクション | ||
| 集中講義 | 授業におけるICT活用 | ||||
- 1年間講義を受講してみて感じる学びやよろこび
- これまで行ってきた授業実践などを振り返り、より専門的な教育理論に基づき検証したり、直接、大学院の先生方から専門的な理論を学びたいという思いで大学院に入学しました。この1年間の学びの中で、今まで知らなかった理論に触れたり、先行研究の調べ方、論文を読みこむ姿勢など、多くのことを経験しました。いずれも大学院で学ばなければ、そして1人では容易にそのような領域や意識にたどり着けなかったような気がします。
大学院というところは、学部と違って、自分自身で研究テーマを設定し、学んでいくところだと聞いていました。正にその通りだと思います。そして学びへの意欲があれば、積極的に自分で動いて、研究室の門を叩くことが求められるとも聞いていました。実際に、1つの授業から様々な取り組み・実践が生まれてきました。受け身の姿勢では、おそらくそこまで発展することもなかったと思います。
様々な理論・考えに触れることによって、学ぶことへの意欲が高まっていくことも実感しています。この1年で読んだ本の冊数は、それまでの何倍も多く、もっと学びたい、知りたいという意欲はより高まっています。それは学んだことを発表する場があり、それを聞いてくれたり、批判的検討を加えてくれる先生方や仲間がいるからだと思います。そのような場や機会は、普段の学校現場ではなかなか得ることが出来ません。
間もなく入学して1年が経とうとしています。大学院での学びはあと1年しかありません。ある程度、学びの成果を出していくことが2年目には求められてきますが、一生涯、学び続けると捉えるならば、学ぶことへの基礎をより固め、深めていくことも重要かと認識しています。より意欲的に、そして自主的に学びの継続を意識して、自身の教育実践の検証や研究をリフレクション(省察)していきたいと考えています。

Cさん
- 校種
- 中学校教諭
- 教育実践リフレクションでの取り組み
- 研究テーマ:「「協同学習を通して理解を深める数学科の授業つくり~小中の連携~ ~算数と数学のつながりについて~」。「個別最適な学び」と、子供たちの多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」の一体的な充実が図られることが求められています。では、効果的な協同的な学びとは、協働学習を通して生徒はどのような力を育むことができるのか、小学校と中学校では協働学習の違いがあるのか、その中に算数と数学の違いはあるのか、などを研究し授業に還元していくことを進めています。
- 1年次の時間割
- 必修科目を中心に時間割を考え、自分の関心のある心理学の授業も受講しました。私が進路担当をしているので、後期は授業を取ることが難しいのが分かっていたので、前期にまとめて受講しました。後期は集中講義を中心に時間割を考えました。そのかわり、平日は教育実践リフレクション(ゼミ)の準備に時間をかけ、研究の内容を深めるようにしました。
| 前 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 6時限 (18:30~20:00) |
教員の社会的役割と自己啓発 | かかわりの発達心理学 | |||
| 7時限 (20:10~21:40) |
特色あるカリキュラムづくりの理論と実際 | 児童生徒を活かす学級経営の実践演習 | 包括的児童生徒支援に関する事例研究 | 教員のための学校組織マネジメントの実践演習 | |
| 集中講義 | 包括的児童生徒支援に関する事例研究 教育実践リフレクション 特別研究 | ||||
| 後 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 6時限 (18:30~20:00) |
円滑な学級経営のための力量形成 | ||||
| 7時限 (20:10~21:40) |
|||||
| 集中講義 | 授業におけるICT活用 障害のある児童への指導と支援方法 学校におけるデータの取り方と分析 特別研究 教育実践リフレクション | ||||
- 1年間講義を受講してみて感じる学びやよろこび
- 大学院で講義を通して、日々の教育実践を学んだ理論と結びつけ、多角的に考え、分析する授業をしていて、「ほんとうにこの教え⽅で⽣徒はうまく理解してくれているのか?」「もっとうまい教え⽅はないのか?」「そもそも⽣徒が理解するとはどういうことなのか?」など多くの疑問を持っていました。⼤学院に⼊学し授業や特別研究を通し多くの理論を知ったことで、今まで持っていた疑問の解決の⽷⼝をつかみ、それを授業で実践し⽣徒の笑顔が増えたり、⽣徒が主体的に学んでいる姿を⾒られることが増えてきました。その時に学ぶことの意義をあらためて感じることができました。また、授業では校種の違う現職教員の⽅々、管理職、教育委員会の⽅々などと意⾒を交流することができたのも、私にとってはとても⼤きかったです。多くの⽅が悩みながら頑張っていることを知り、正直ホッとし活⼒を得られました。
教育実践リフレクション(ゼミ)では、とても丁寧に指導していただき、理論を深めることができました。そのことで、今までと違った側⾯から考えることができるようになり、1 年間の学びで⾃分が変わったことを実感することができました。また、合同ゼミもあり、同期の頑張りが刺激になり、研究への⼒が⼊りました。
この 1 年間で多くのことに触れることができ、すべてが貴重な経験になりました。「⾃分の成⻑が⽣徒へ還元される」ことを意識し、これからの⼤学院⽣活をさらに充実したものにしたいと思います。