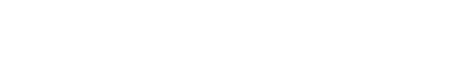Q&A
働きながら学ぶことの、悩み・苦労・そして、よろこび。

| Q1. | どうして大学院で学ぼうと思ったのですか? |
|---|---|
| A1. |
Aさん 生涯にわたって学習したいと思っており、また、60歳まで学校現場で務め、その後は大学で教員志望の人を育てたいという希望を持っているからです。これに加え、心を育てる道徳教育の実践研究を進めたいからです。 Bさん 「目の前にいる子ども達のために、授業が上手くできるようになりたい」という思いで、積極的に授業づくりの改善に取り組んできました。さらにステップアップを図るために、一度立ち止って、これまでの授業実践を振り返り、課題や改善点を洗い直し、専門の先生方の下で、より専門的な見地から検証と構築をしたいと思ったからです。 Cさん GIGAスクール構想などを含む授業改善や自校の課題に対して、解決策を模索していた際に、兵教の大学院のことを知ったからです。 |
| Q2. | 大学院での学びで自分の中で何か変わり始めたことがありますか? |
| A2. |
Aさん 今までは仕事中心の生活からライフワークバランス変わってきており、これまでの自分の人生をふりかえる機会が持て、人生が充実しつつある。 Bさん これまでは実践を中心に取り組んできましたが、理論的な裏づけや先行研究にあたるなどの視点が加わり、より多面的・多角的に考えるようになってきました。また、授業の中で大学の先生方や、同じコースの仲間の方と議論する中で、一人では考えつかなかったようなことにも気付かされました。そして、それを実践に生かすことができ、より中身の濃いものが取り組めるようになりました。 Cさん 学び直しにより、自身が現場で培った様々な経験を振り返ることができ、新しい時代に対応した授業や学び、公教育はどうあるべきかなどを深く考えるようになったと思います。 |
| Q3. | なぜ、本コースで学ぼうと思ったのですか? |
| A3. |
Aさん 実践に基づいた自分のしたい研究ができ、現場の苦労や課題を共有できる唯一のコースと思ったからです。つまり、大学教員の研究に合わせる必要はなく、主体性を発揮し、現場の問題解決につながると考えたからです。 Bさん 学校現場で勤めながら大学院で学ぶためには、夜間コースである本コースが最適であることと、コースの仲間が全員、現職の教員であることから、様々な教育現場での考えや悩みを共有できるのではないかと考えたからです。 Cさん 夜間で学べるコースが本コースであったからです。 |

| Q4. | 講義に出席するために、職場に迷惑をかけないですか? 職場の理解をどのようにして得ましたか? |
|---|---|
| A4. |
Aさん 基本的に勤務時間外のことなので、職場に迷惑をかけるとは思っていません。もっと言えば、働き方改革、生涯学習を率先垂範しようと考えています。今までは遅くまで残って仕事をすることが美徳と信じてやってきましたが、今は時代錯誤であると自覚しています。幸い職場の理解は十分に得られていますので、ことあるごとに本コースで学んでいることを話しPRし、他の職員にも学ぶことの楽しさを感じてほしいと思っています。 Bさん 年度初めに、管理職や学年の先生には説明をし、理解を得るようにしました。職場には出来るだけ迷惑をかけないようにするために、仕事の進め方を工夫するように心掛けました。また、大学院での学びを、職場で生かす取り組みをして、還元できるようにしました。ただ、どうしても職場を離れられない時は、オンラインで参加することもありましたし、大学院の先生に連絡をして欠席し、レポート作成など代替させていただくこともありました。 Cさん コロナ禍で部活動の時間も短縮になっているため、生徒指導がなければ、同僚に迷惑をかけることはないのではないかと思っています。 |
| Q5. | 平日の講義(特に6時限)は出席できますか? |
| A5. |
Aさん 勤務地が自宅に近く、また、神戸サテライトにも比較的に近いこともあり出席できました。それに、オンラインなのでPCを接続する環境さえあれば出席できると思います(同じコースの仲間は、通勤路の途中にあるカラオケボックスを利用して受講していました。)。 Bさん 今年度はオンラインの授業が多かったため、遅れて途中から参加することはありましたが、比較的、出席できたと思います。全て神戸キャンパスでの対面授業であれば、少し事情は違ったと思います。 Cさん コロナ禍で、Zoomなどのオンライン授業がほとんどであったため、出席はしやすかったです。 |
| Q6. | 土・日や夏休み、冬休みの講義の集中講義と職場の仕事(行事、クラブの大会など)が重なった場合、どうしましたか? |
| A6. |
Aさん やはり仕事を優先しました。その場合は講義の先生に代替の課題をいただき、学び、提出し、配慮ある評価をしてくださったので、全く問題はありませんでした。 Bさん あらかじめ学校行事と重ならないことを確認して受講したことと、大学院の先生方や受講する方と日程調整をして授業日を設定することもありましたので、重なることはありませんでした。 Cさん 管理職ということもあり、仕事を優先しましたが、休業日の学校行事はそれほど多くはなく、単位は落とすことはなかったです。 |

| Q7. | 教育実践リフレクションの曜日、時間は決まっているのですか? |
|---|---|
| A7. |
Aさん 年度当初に、大学教員と学生が相談して曜日・時間を決めるので問題はありませんでした。 Bさん 私の場合、前期は火曜日の7限、後期は木曜日の7限を中心に行われていましたが、これもその時々の学生の勤務状況に合わせて変更していただけるので特に問題はなかったです。 Cさん 年度当初に曜日や時間は設定されますがが、ゼミ形式なので、先生方がその時々の学生個々の状況に対応してくださりありがたかったです。 |
| Q8. | 教育実践リフレクションはオンラインで受講できますか? |
| A8. |
Aさん オンラインでも受講できますが、対面の方が刺激があって楽しいと感じました。 Bさん 普段の「教育実践リフレクション」はオンラインで行われていました。半期に1回実施される「学びの発表会」は対面で行われますが、学校での業務によりどうしても対面で受講できない時は、オンラインで参加させていただきました。 Cさん 本コースの学生は現職教諭であることから、ほとんどオンラインでした。 |
| Q9. | 働きながら学ぶことのよろこびは何ですか? |
| A9. |
Aさん 自分の視野が広がり、現場の問題解決にもつながる知見を得られます。心の栄養(プラスのストローク)がもらえ、学びがカウンセリングにもなっているという感じです。これらに加え、悩みや喜びをシェアでき、ふれあいのある人生が送れます(ヒューマンネットワークが広がる)。 Bさん 日頃は目の前にいる子ども達のために、必死になって授業づくりや子ども理解に努めていますが、上手くいかないときなど、壁にあたったり、あるいはアイデアが浮かばなかったりすることも多々あります。そんなときに、一度立ち止って、様々な考えに触れる機会があることは、明日への希望につながることがあります。学校現場では時間に追われ、学ぶ時間があまりとれません。そのような中でも、様々な考えや理論、論文や書物の存在を知ることで、自身の学びを深めることにつながることもあります。それにより悩みが解決したり、壁を乗り越えたりすると、もっと学びたいという気持ちが高まることにつながっていきます。 Cさん 専門性や実践力を高めることができること、ここに大きなよろこびを感じています。 |

| Q10. | 大学院での学びを現場で活かせたことはありましたか? |
|---|---|
| A10. |
Aさん 私は大学院での学びを現場に活かせることばかりで、活かせないことが思い当たりません。 Bさん 前期で受講した「総合的な学習と特別活動のデザイン」の授業では、大学院の先生と私のマンツーマンで行われました。毎回、学校現場での「総合的な学習」の取り組み状況を報告しながら、より実践的な取り組みをするにはどうすれば良いかをディスカッションしてきました。その中で、「キャリア教育」の一環として、社会の第一線で活躍する職業人への「職業インタビュー」のアイデアが生まれてきました。どのような形態で進めていくことが望ましいかや、その手法やまとめ方など、「ディスカッション・アイデア出し ⇒ 実践 ⇒ 授業での報告 ⇒ 検証」を行い、次のステージに進んでいくことを積み重ねていきました。この授業は前期で終了したのですが、学校での実践が1年を通してのものであったため、後期は “特別ゼミ” として自主的に継続して行われていきました。実践としては一区切りしたのですが、その成果を実践論文としてまとめるために、この “特別ゼミ” は2年目も継続して行われています。単位取得とは関係なく、実践の中で生まれた学びであります。 Cさん 初任者や2年次研修の教員の公開授業の際には、大学院で学んだことを指導助言として活かすことができました。 |
| Q11. | 本コースだから生まれた学びはありましたか? |
| A11. |
Aさん 現場を対象にした実践研究なので、全ての学びが実践に役立つように思います。また、すべての講義が少人数なので、対話的な学びが非常に多いとも感じます。また、本コースを修了した後は、道徳教育、特に道徳的行為に関する体験的な学習について連合大学院で研究したいと思っています。 Bさん 本コースのメンバー全員が現職の教員であるため、学校現場での悩みや苦労、試行錯誤といったことなどが、授業を通して共有・共感できることが大きな励みとなりました。夜間の授業の多くが本コースのメンバーと大学院の先生方だけの授業であったため、日頃起きている出来事などを踏まえながら、それぞれが抱えていることを出し合う中で、様々な発見や気付きが生まれてきました。そして、それらのことを、自身の研究テーマと照らし合わせながら、より専門的に考えることが出来るようになりました。 Cさん 同じコースの仲間との意見交換や議論により、一人で学ぶ以上に深い学びができた。 |