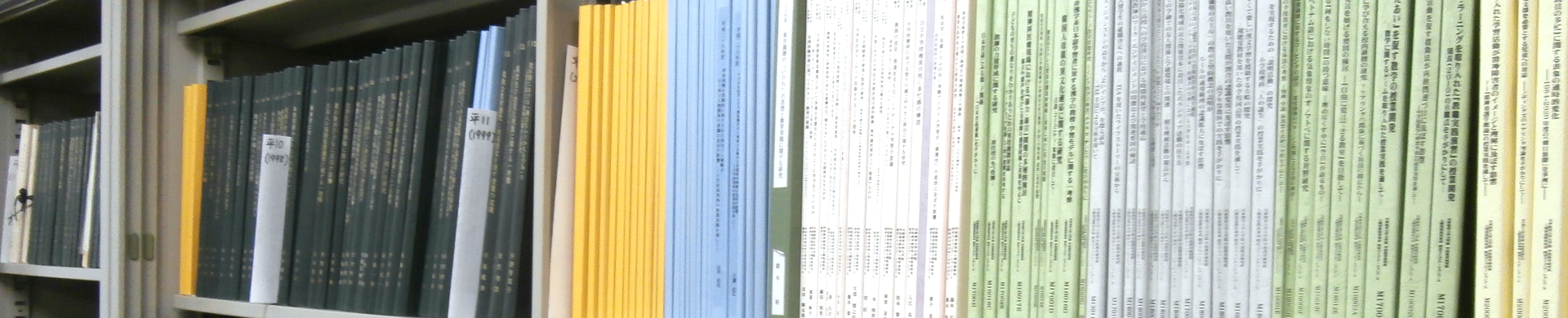修士論文題目一覧
論文の閲覧等につきましては本学附属図書館に直接お問い合わせください。
※表の右欄は担当ゼミ教員です。
| 橋本 和也 | 主体性の教育に関する批判的検討 ―M・フーコー「主体の解釈学講義(1981年~1982年)」から― |
平野 |
| 加藤 正美 | C・ロジャーズ「学生中心教育」理論に基づく大学英語授業の実践的展開 ―学生と教師が共に成長する実践を目指して― |
吉國 |
| 原 直希 | イエナプラン教育の理念と実践に関する研究 ―大日向小学校の教職員の語りに着目して― |
大関 |
| 嶋田 智沙恵 | 在外公館の交流事業を基にした学校教育における異文化交流の再考 ―在上海日本国総領事館及び中国駐大阪総領事館による2022年、2023年の事業比較を通して― |
大関 |
| 赤松 弘揮 | 社会貢献活動に参加する子どもの意識変容に関する研究 ―傍観者から当事者へのパースペクティブ変容に着目して― |
大関 |
| 大崎 美佳 | 教育現場における看護学生と看護教員の相互交流的な関係 ―省察的実践者としてエピソード記述で振り返る― |
大関 |
| 中村 祐介 | 大学入試対策の心理学化 ―【過去→現在→未来】の一貫性を必須とする自己分析が大学入試対策の技術とされていく歴史的地層を『螢雪時代』から探る― |
平野 |
| 赤﨑 洋之 | 教師が学び合う校内研修に関する研究 ―モーリス・メルロ=ポンティの身体論を手がかりに― |
大関 |
| 遠藤 直也 | 柱体の体積の「実体化」が児童の「関係操作」に及ぼす影響 ―小学校6年生の算数の授業実践を通して― |
吉國 |
| 岡田 翔太 | 民主主義を担う学校の道徳教育に関する研究 ―シャンタル・ムフの闘技民主主義の理論を手がかりに― |
大関 |
| 近田 知富美 | 小学校教員が挫折経験を乗り越える過程の探求 ―ライフストーリーを描いたTEM図を手がかりに― |
吉國 |
| 鄭 喆 | 清末における江西省出身の留日学生についての研究 | 平野 |
| 松崎 康祐 | 授業場面における教師の代替不可能性に関する考察 ―メルロ=ポンティの「現象的身体」を手がかりにして― |
大関 |
| 八木 翔汰 | 博学連携の視点から問い直す水族館の存在意義に関する研究 ―みなとやま水族館が目指す環境教育を手がかりに― |
吉國 |
| Chang Ching-Hsuan (張 靖舷) |
分断社会における多文化教育 ―北アイルランドの統合教育と共有教育を事例に― |
平野 |
| 衛藤 裕 | 「共に生きる力」を育む学校に関する研究 ―「社会モデル」アプローチにより照射される教育目標に着目して― |
坂口 |
| 切通 明樹 | 特別権力関係論を手掛かりとした校則による生徒の権利・自由の制限に関する考察 | 平野 |
| 中山 義之 | 小規規校という学校環境における教員の教職アイデンティティの形成 | 須田 |
| 綿貫 克洋 | 自己調整学習の観点からみた学習過程の多様性と学習者の個人差の検討 ―問題解決を主眼とする高校生の探究活動において考慮すべき要因として― |
中間 |
| 田中 康雄 | 幼稚園で展開される「ひとり遊び」についての考察
―観察を通して見える遊び姿の多様性に注目して― |
中間 |
| 髙橋 華奈 | 経済連携協定に基づく外国人介護職員と日本人介護職員の職務継続意向について
―職務面および生活面における満足度との関連から― |
中間 |
| 苆野 大志 | 「謎解き読み」を基盤とした授業プログラムが読みの更新に及ぼす影響
―中学国語科文学教材「盆土産」の実践を通して― |
吉國 |
| 文 敏実 | 朝鮮学校における母国語教育に対する認識に関する研究
―教育者と学習者のアイデンティティに着目して― |
坂口 |
| ほか1本 |
| 上阪 浩一 | 「社会に開かれた教育課程」を実現するための教職員の同僚性に関する研究 ―チームに対する認識や他者とのかかわりの視点に着目して― |
坂口 |
| 大前 晶子 | 日本語教育における意味の伝達と創造に関する研究 ―言語行為におけるコンテクストの共有と意味の脱構築に着目して― |
大関 |
| 北村 里佳 | 教員の語りにみる「チーム学校」に関する一考察 | 坂口 |
| 謝 永喆 | 青年期の恋愛依存に関する研究 | 中間 |
| 竹繁 諒真 | 商業高校に勤務する教員の働き方とその特質に関する研究 | 坂口 |
| 塚本 由利子 | 看護教育における社会保障制度の知識と実習を関連づける授業の研究 ―地域・在学看護論の授業実践を通して― |
吉國 |
| 寺田 英明 | 学校でシティズンシップを育むための体験活動に関する研究 ―デューイの経験論における「試みること」と「被ること」の検討から― |
大関 |
| 名田 文子 | 自己への気づきを促すアート表現の可能性 ―可視化・空間化された自己世界の検討を通して― |
中間 |
| 中根 彰宏 | キャリア教育における高校生の進路指導についての研究 ―生徒に求められる能力と教師のかかわりかたに注目して― |
大関 |
| 中原 竜彦 | 「道徳は教えられるか」 ―貝原益軒の教育思想を手がかりとしたそれが孕む諸問題の考察― |
平野 |
| 中村 宏美 | 「わからないこと」に対する教師と子どもの協同的探究 ―ウィトゲンシュタインの言語ゲーム論を手がかりとして― |
大関 |
| 中村 靖子 | リフレクションを促す教育実践が言語聴覚士の後進指導に及ぼす影響 ―指導経験者を対象としたワークショップを手がかりにして― |
吉國 |
| 増田 悠生 | 機械的公式観を克服し学習者の興味を喚起する算数の援助法の探究 | 吉國 |
| 阿部 崇 | 通常学級における特別な支援を必要とする児童への対応 ―ノディングズのケアリング理論を手がかりにして― |
大関 |
| 木村 滉 | 言説分析を通じた「教員の多忙」に関する表象の通時的変化 ―1984-2020 年度の『朝日新聞』を事例に― |
坂口 |
| 小牧 由美子 | 外国人留学生の進路選択行動に関する研究 ―進路選択自己効力と日本語能力自己評価が及ぼす影響に着目して― |
中間 |
| 高橋 麻子 | 中年期に日本語教師職を選択した女性3名のキャリアテーマ ―異なるライフコースにおける構築の様相― |
中間 |
| 髙橋 利明 | 工業高校生の進路選択の戦略に関する研究 | 坂口 |
| 南山 晃生 | 児童の思考力に関連する学習行動と動機づけについての研究 ―課題解決的な学習を学びの充実につなげるために― |
中間 |
| 深田 美香 | 視聴覚教材を取り入れた学習活動が精神障害者のイメージと理解に及ぼす影響 ―「精神看護学概論」の授業実践を通して― |
吉國 |
| 柳瀬 賢佑 | 自由で平等な意見表出を可能にするコミュニティ・スクールの研究 ─ハンナ・アーレントの公共性の概念に着目して─ |
大関 |
| ULZIISAIKHAN DUKGUUSELENGE | 日本語とモンゴル語における身体慣用句に関する対照研究 | 大関 |
| 浅貝 賢司 | アーユルヴェーダ教育思想研究 ―インド医学古典書『チャラカ・サンヒター』について |
平野 |
| 畑中 敬子 | 授業内での発言を妨げる要因の検討 一「自由に発言できる教室」を目指して― |
中間 |
| 板東 克則 | 教育における「何もしない時間」の持つ意味 ―埋め尽くす中に「空白」が語るもの― |
大関 |
| 菊地 歓 | 近現代日本の学校教育における体罰の考察 ―判例・学説・体罰禁止法制の分析を中心として― |
平野 |
| 田中 健人 | 学習者の操作活動を促す援助法が内的関連づけに及ぼす影響 ―中学校数学「座標平面」の授業実践を通じて― |
吉國 |
| 谷口 祥子 | 教師が主体的に学び合える校内研修の研究 ―ケアリングの関係に基づく対話の視点から― |
大関 |
| 馮 輝 | 青年期の恋愛崩壊に対するコーピングの諸相 ―恋愛崩壊のパターンと性別による差異の検討― |
中間 |
| PHAM THI LINH CHI | 日本語とベトナム語における気象現象のオノマトペに関する対照研究 | 中間 |
| 大島 秀子 | キース・ジョンストンの語りから“よいインプロ”を探る試み ―TAE手法による分析を用いて― |
中間 |
| 石原 優子 | 分かりやすくて楽しい漢文学習を援助する方略の探究 ―視聴覚教材を用いた中学校国語科の授業実践を通して― |
吉國 |
| 原 真奈美 | 外国人が日本において就業しながら資格取得を目指す過程 ―EPAインドネシア人介護福祉士候補者の学習における自律をめぐる考察― |
中間 |
| 前田 真弥 | 外国人留学生の就職決定への過程 ―TEAを用いたライフストーリーの分析から― |
中間 |
| 碓井 大将 | 放課後児童支援員として子どもたちの宿題とどう向き合うか ―ワークショップから見えてくる理想と現実― |
中間 |
| 梶原 健太 | 操作性の高い教具を用いた支援が割合の認識変容に及ぼす影響 ―高学年算数科での実践を手がかりに― |
吉國 |
| 寒川 鉄平 | 中学校教師のワーク・エンゲイジメントの特徴および関連要因の検討 | 中間 |
| 長谷 守紘 | 中学校から高校への学校移行における時間的展望と学校適応 | 中間 |
| 宮澤 尚 | 「深い学び」を実現するための「説明活動」の探究 ―小学校理科「人の誕生」の授業実践を手がかりに― |
吉國 |
| 横江 貴行 | 「競争と価格のルール」の教示と契約概念の説明がルールの適用範囲の認識拡大に及ぼす影響 | 吉國 |
| 渡部 峻 | 少子高齢化地域の社会関係資本に着目したボランティア活動の在り方 | 須田 |
| 川北 香織 | 中学生の学級での友人関係と学級環境との関連 ―相互理解活動の視点から― |
中間 |
| 掛 博彰 | 教員のストレス要因の構造的解明と改善に向けた学校の取組 | 須田 |
| 本土 勝己 | 非漢字系日本語学習者に対する漢字の教授・学習モデルに関する一考察 | 宮元 |
| 松原 渉 | 精神科医療現場における「暴力・暴言」問題の多層的検討 ―暴言や罵声を受けた看護師の感情経験と対処を中心に― |
宮元 |
| 吉田 典子 | 教師の力量形成に関する研究 ―初任校のもつ役割― |
須田 |
| 金 秀英 | 韓国人母親の異文化適応に関する研究 ―言語・コミュニティ・家族に着目して― |
須田 |
| 黒川 さゆり | 子どもの育ちの連なりをわかりあうための異校種間対話 ―ワークショップを通して幼小連携を再考する― |
宮元 |
| 東 豊 | 児童の自発的・自治的な学級活動が心理的安全性の構築と学校への期待感・意欲に及ぼす影響 | 須田 |
| 村上 達哉 | 日本昔話にみる親・子関係 ―『日本昔話通観』を手がかりに― |
平野 |
| 籔内 正明 | 「教えあい」を促す数学の授業開発 ―数学に関するゲームを取り入れた授業実践を通して― |
吉國 |
| 榎元 十三男 | アクティブ・ラーニングを取り入れた「教職実践演習」の授業開発 ―須長(2010)の6観点を手がかりにして― |
吉國 |
| 曽 昕 | 中国における大学生の学習状況は進学動機・専門選択理由とどう関連するのか ―日本語専攻の学生を対象に― |
中間 |
| 小山 亮 | SNS上における自己呈示 ―E.ゴッフマンに依拠して― |
須田 |
| 入江 良子 | 公立中学校教員が抱く多忙感の構造 | 須田 |
| 渡邉 映子 | 日本語教師養成機関において多様な受講生たちはどのように学び合っているか ―修了生へのインタビューから見える現状と課題― |
宮元 |
| 阿曽 奈生 | 教師の成長・発達を支えるノンフォーマル学習の意義 ―過疎部における教師コミュニティでの学びの場づくりを中心に― |
宮元 |
| 大部 慎之佑 | 大正新教育の衰退と変容の諸相 ―関東大震災を契機とした教育言説の変容に着目して― |
平野 |
| 岡本 絵里 | 教室を多声的な場にする授業の研究 ―対話を促す教材/学習材としての古典に着目して― |
平野 |
| 兼子 美佐 | 乳幼児と母親とのふれあい体験プログラム学習が「養護性」の変容に及ぼす影響 ―高校家庭科の授業を通して― |
吉國 |
| 北谷 隆太郎 | 自然体験学習に基づくリテラシー教育の意義 ―J.R.マーティンの「3つのC」の思想を手がかりに― |
平野 |
| 播田 茜 | 大学生がボランティア活動をすることの意味 | 須田 |
| 藤田 知里 | 教師の身体性と身体技法に対する意識化は“関わり方”にどのような変容をもたらすか | 宮元 |
| 曲 五月 | 子どもの不登校経験にみる母親の心理変容過程 ―中年期女性の自己に焦点を当てて― |
中間 |
| 松永 梨沙 | 中学校教師における怒りの感じやすさと表出に関する研究 | 中間 |
| 森本 大吾 | 身近な他者との会話と高校生の進路成熟との関係 ―教育・職業・人生3側面についての検討― |
中間 |
| 李 暁歓 | 相互行為による主体性形成に関する研究 ―ハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論を手がかりに― |
平野 |
| 越田 佳孝 | 政治的教養をはぐくむ教育に関する研究 ―アーレントの「公共性」概念に着目して― |
平野 |
| 青 平 | 中国内モンゴル人青年の民族アイデンティティの諸相 ―出身民族への所属意識と行動面での表出をめぐって― |
中間 |
| 井上 幸治 | 小学校におけるコンピテンシー育成に関する研究 ―知識の概念に注目して― |
大関 |
| 小林 文英 | 「家庭教育」という言葉に内包される規範性と戦略性 ―各種メディアからの分析― |
須田 |
| 澤井 茂和 | 学級集団特性の把握方法とその活用 ―自己・他者評価の調査を通して― |
須田 |
| 末金 真由美 | 日本語教育を社会的な学びにつなげるために ―技術職を目指す留学生と彼らを育てる場との関わりから― |
宮元 |
| 川瀨 直広 | モデルを活用した予測活動が月と地球と太陽の3者関係の理解に及ぼす影響 ―小学校理科の授業実践を通して― |
吉國 |
| 神田 真実 | ガールスカウトという女性主体の活動の意義と課題 ―女子教育,生涯学習,世代間継承を軸に― |
宮元 |
| 菊地 康介 | 学校化するフリースクールの意義に関する研究 ―主体的な学びに着目して― |
大関 |
| 施 姗 | 異年齢交流活動における社会性育成に関する研究 ―特別活動の観察を通して― |
須田 |
| 常 甦丹 | 日本の老舗の特色と現代的役割に関する研究 | 宮元 |
| 高山 美畝 | 中学生におけるレジリエンスと学校適応感・ライフイベントとの関係 | 中間 |
| 武部 美里 | 近代的育児と「母親」像の形成過程に関する一考察 ―『ははのつとめ』(明治23年)を手がかりに― |
平野 |
| 杜 楊 | 理論と実践の融合をめざした教員養成カリキュラムに関する日中比較研究 ―教育実習の位置づけを中心に― |
大関 |
| 山我 拓也 | 身体接触を段階的に取り入れた体ほぐし運動が心と体と人間関係の意識に及ぼす影響 ―小学校体育科の授業実践を通して― |
吉國 |
| 横山 奈穂 | 授業場面における子どもの発言に関する研究 ―子どもの発言行為につながる関わりとは― |
須田 |
| 三浦 良久 | 主体的学習の意義に関する研究 | 須田 |
| 内藤 傑 | 「疑似例外」を用いた探求活動が光合成に関する誤概念の修正に及ぼす効果 ―中学校理科の授業実践を通して― |
吉國 |
| 早水 薫 | 看護学生の「患者理解」に関する研究 ―看護学生の臨地実習に対する解釈学的アプローチ― |
大関 |
| 泉 美穂 | 児童期から思春期の自己概念に対するソーシャルサポートの影響 ―サポートの送り手の要因を考慮して― |
中間 |
| 内澤 梨紗 | “よさ”を考慮した創造の場に関する一考察 ―創造システム理論の視点から― |
宮元 |
| 枝廣 直樹 | 子どもの興味を重視する学校教育の研究 ―セレスタン・フレネの「興味の複合」概念に注目して― |
大関 |
| 王 怡凡 | 通訳者の視点から見る異文化コミュニケーション能力に関する研究 | 須田 |
| 川上 梓 | 愛着と誇りのある学級の特徴と教師の指導行動との関係 | 須田 |
| 小舟 まり子 | 多義語「結構」の歴史的変遷に関する研究 ―コンテクストから探る多義語の特性― |
須田 |
| 才野 恵 | ケニア・マサイ族の学校現場における学習困難児の現状と支援の可能性 ―保護者と教員の声を手がかりに― |
宮元 |
| 佟 寅博 | 「教師―生徒」関係の再構築に関する研究 ―フレイレの教育思想を中心に― |
大関 |
| 野間 千夏 | 戦時期日本映画のもつプロパガンダ性 ―映画における他者表象に注目して― |
須田 |
| 藤井 三和子 | 高校生の友人関係の特徴とアイデンティティ発達との関連 | 中間 |
| 三浦 兼春 | 道徳授業を通じた公共圏形成に関する研究 ―H.アレントの思想を手がかりにして― |
大関 |
| 冨田 幸子 | いじめ撲滅劇参加による中学生の変容 ―短期的および長期的時間経過後の振り返りから― |
中間 |
| 伊東 美智子 | 看護職を選び、看護師になってゆく人たちの語りをきくということ ―社会人学生の人生径路と“unlearn”に着目して― |
宮元 |
| 仲井 勝巳 | 小学校理科・生活科の授業時における科学絵本の活用がイメージ共有化に与える効果 ―新たな理科・生活科教育の可能性― |
須田 |
| 浜中 惠美子 | 身体を拓くキャリア教育に関する研究 ―メルロ=ポンティの身体論を手がかりに― |
大関 |
| 山西 多加 | 柳宋悦の民藝論における民藝美と生活に関する研究 ―身近な工芸鑑賞学習への示唆― |
須田 |
| 湯峯 裕 | 高等学校におけるキャリア教育の再構築 ~ウィトゲンシュタインの言語哲学に注目して |
大関 |
| 荒井 隆一 | 参加型学習を取り入れた学習プログラムが地球市民意識に及ぼす効果 ―小学校6年社会科「世界のなかの日本とわたしたち」の実践を通して― |
吉國 |
| 遠藤 和佳 | 学校図書館利用からみる児童の読書状況と教育現場でのアプローチの可能性 ―学級での関わり合いに着目をして― |
須田 |
| 小俣 直由樹 | 学習者の省察を促進するファシリテーションについての研究 ―プロジェクトアドベンチャーを題材として― |
中間 |
| 楠亀 倫明 | 中学校初期社会科の実態 ―社会科学習指導要領(試案)の理念と実際の教育計画・実践との関連をふまえて― |
須田 |
| 小林 禎明 | 描写のイメージ化と解釈の検証が物語文の読みに及ぼす影響 ―『ごんぎつね』の読み取り場面に着目して― |
吉國 |
| 菅原 舞子 | 農業科に通う高校生の進路意識に関する研究 | 須田 |
| 棚倉 未弥 | 日英の人称概念を比較する教示が3単現の理解に及ぼす影響 ―中学校英語科の授業実践を通して― |
吉國 |
| 長谷 拓郎 | 日本のニューカマー児童における言語教育のあり方についての研究 | 中間 |
| 堀端 優也 | 価値多元化社会における公共圏形成に関する研究 ―コミュニティ・スクールの理念と実際に注目して― |
大関 |
| 平野 通子 | 中高年看護師たちが“ふつうに”働ける場を求めて ―当事者たちとのゆるい学びをつくる試み― |
宮元 |
| 包 晶晶 | 中国内モンゴル自治区における双語教育に関する研究 ―民族小学校における授業と教員への聞き取りをもとに― |
宮元 |
| 和田 敏江 | 専門学校生の学業パフォーマンスに影響を及ぼす心理的要因 ―新入生に対する縦断的調査から― |
中間 |
| 赤松 芳恵 | 人間形成における「受苦的な経験」に関する研究 ―ボルノーの教育人間学を中心にして― |
大関 |
| 安保 育美 | 大村はまの教育観に関する研究 ―幼児教育への示唆― |
渡邊 |
| 大西 理加 | 特別支援学級における数概念形成を目指した教授法の研究 ―語り合いが児童の納得を生み出す過程に着目して― |
吉國 |
| 岡本 恵太 | 授業がゆらぐ時,何が起こり,何が生み出されているか ―「カーニバル化」と「危機」の観点から― |
宮元 |
| 片山 直子 | 専門学校生の「速さ」概念の変容に関する研究 ―ダイヤグラムを活用した授業実践を通して― |
吉國 |
| 瀧本 奈緒子 | 能動的シティズンシップのための教育 ―オランダのシティズンシップ教育の理念と実践から― |
渡邊 |
| 有吉 美咲 | 障害理解教育のツールとしてのICFモデル ―教材としての絵本の分析― |
宮元 |
| 泉 洋輔 | 本とのかかわりかたを“学びほぐす”ワークショップの開発 ―本と本をつなぐブックサーフィン― |
宮元 |
| 桑平 英治 | 長野県師範学校附属小学校「研究学級」における淀川茂重の思想と実践 ―「総合的な学習の時間」への示唆― |
渡邊 |
| 堂本 博之 | イバン・イリイチ 『脱学校の社会』 再考 ―コンヴィヴィアルな学校を目指して― |
渡邊 |
| 永宗 怜子 | パフォーマンス評価に関する研究 ―学校教育における「真正性」の概念に注目して― |
大関 |
| 中村 美由希 | フランスの学校図書館改革 ―ドキュマンタリスト教員をめぐる諸制度を中心に― |
渡邊 |
| 名越 理恵 | 図形の面積学習における平行線に注目した「高さ」の教授の影響 ―小学6年生の「高さ」の認識を手がかりにした検討― |
吉國 |
| 西口 啓太 | アメリカ合衆国におけるアカデミック・ライティングに関する研究 ―大学初年次生を対象としたライティング教育を中心に― |
渡邊 |
| 早川 拓次郎 | 小学校キャリア教育における評価改善 ―「キャリアノート」分析からの提案― |
渡邊 |
| 前田 浩伸 | 複数の象徴事例が歴史的事象の構造的理解に及ぼす効果 | 吉國 |
| 植原 俊晴 | 先行概念と科学的概念の相互交渉を活性化させる教授学習法が概念構築に及ぼす効果 ―中学校理科における金属概念の構築に着目して― |
吉國 |
| 小津 順子 | 高齢者の生涯学習としてのグループ回想法 | 宮元 |
| 中藤 光男 | 持続可能な開発のための教育(ESD)の意義と可能性 ―RCE岡山の取り組みを通して― |
渡邊 |
| 堀 智子 | 看護専門学校における「社会人学生」とは誰のことか ―「社会人学生」を巡るトライアンギュレーション― |
宮元 |
| 木戸 田鶴 | 吉岡彌生の女医養成論に関する研究 ―女医養成と儒教思想の関係を中心にして― |
大関 |
| 清水 輝喜 | 「対話」による人権教育に関する研究 ~「銀行型教育」から「課題提起型教育」への転換~ |
大関 |
| 薗 里奈 | 課題遂行のための使用方略と先延ばしとの関連について ―課題遂行時の状況を考慮して― |
中間 |
| 新島 英樹 | 沖縄県の「新しいタイプの高等学校」に関する研究 | 渡邊 |
| 藤井 雅哉 | 俚諺の研究 ―禁忌の分析を中心に― | 渡邊 |
| 藤原 由香里 | 学びの“新しいメタファー”としての即興演劇 ―相互行為の中で創造される意味とパフォーマンス― |
宮元 |
| 松崎 京子 | 苦手な生徒との出会いが中学校教師に与える影響 | 中間 |
| 吉田 恭兵 | 割合文章題解決過程における認識の研究 ―児童・専門学校生を対象にした調査を中心に― |
吉國 |
| 上田 早也香 | 東井義雄の教育観 ―「いのち」の思想と「ビリ」の思想を中心に― |
安部 |
| 岡林 文崇 | 社会のユニバーサルデザイン化にむけて -ニーズと参加の視点から- |
宮元 |
| 松村 千鶴 | 師道に関する歴史的研究 -雑誌『師道』を中心に- |
渡邊 |
| 松本 きみゑ | 茶書にみる茶道の教育的意義 -『山上宗二記』と『南方録』を中心に- |
渡邊 |
| 髙村 尚太郎 | 中学校運動部活動の社会体育移行に関する研究 -愛知県半田市の取り組みを事例として- |
安部 |
| 五百住 満 | 不登校児童・生徒に対する公立教育施設と学校の連携に関する研究 -兵庫県立やまびこの郷の取組みに焦点をあてて- |
渡邊 |
| 石田 良重 | 明治期茶道の継承と改革 -田中仙樵の茶道改革運動を中心に- |
安部 |
| 梅原 英治 | ハンナ・アーレントの教育思想に関する研究 ~「権威」論を中心にして~ |
大関 |
| 岡田 麻依子 | 木下竹次の合科学習論 -「独自学習」と「相互学習」を中心に- |
渡邊 |
| 木下 孝一 | レッジョ・エミリア・アプローチに関する研究 -「環境を通した教育」の課題と新たな可能性- |
渡邊 |
| 鈴木 真奈 | シャイネスとコミュニケーションに対する抵抗との関連 -話題と発信手段の条件を考慮して- |
中間 |
| 中磯 千佳子 | 生まれ育つ場所に対する意味づけについての考察 -原風景語りを通して- |
宮元 |
| 藤原 希 | 恋愛関係崩壊時の状況がその後の過程に及ぼす影響について | 中間 |
| 河合 俊成 | 部活動に対する自己効力感の変動と部員としての意識との関連 -強豪高校サッカー部員を対象に- |
中間 |
| 雲井 稔 | 大坂平野・含翠堂における知的ネットワークの形成 ―懐徳堂、八尾・環山楼との関係を中心に― |
安部 |
| 小林 清美 | カウンセリングにおける笑いの意味 | 宮元 |
| 太田垣 完児 | 言語学習を通した多文化教育に関する研究 ―アメリカの双方向バイリンガル教育を中心に― |
渡邊 |
| 三野宮 春子 | 高校英語における経験学習のための教具開発とコミュニケーション分析 | 宮元 |
| 中島 健太 | 協同学習についての研究 | 中間 |
| 山村 利香 | 「孤立化」と「主体性の喪失」が教師のバーンアウト傾向に及ぼす影響について | 中間 |
| 木田 祐子 | 重症心身障害児(者)の就学猶予免除に関する考察 ―西宮すなご医療福祉センターでの就学猶予免除者の事例を中心にして― |
宮元 |
| 笹脇 玲子 | 多文化共生の教育に関する研究 ~ハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論を手がかりとして~ |
大関 |
| 陳 秀平 | 中国における親の教育期待としつけに関する研究 ―都市と農村の経済的格差に注目して |
大関 |
| 藤田 耕生 | 近世における和算の教育 ―池田定見の和算塾を中心に― |
安部 |
| 山本 真梨子 | フィンランドにおける教育に関する研究 ―現代社会に求められる「学力」をどう育成するか― |
渡邊 |
| 久原 邦美 | 学級における教師と生徒の教育的関係に関する研究 ―<教える‐学ぶ>関係が成立する構造に注目して― |
大関 |
| 赤鹿 弘和 | 中1ギャップに関する研究 ―小中連携・一貫教育のあり方を中心にして― |
大関 |
| 池ヶ谷 隼世 | オランダのイエナ・プランに関する考察 ―受容過程における変容に注目して― |
渡邊 |
| 池田 英則 | 転職教師の教師アイデンティティに関する研究 ―教員文化との折り合いをつける過程に着目して― |
宮元 |
| 石井 正幸 | 子どもの言語獲得と人間形成に関する研究 ―S.ピンカーの言語本能論を手がかりにして― |
大関 |
| 岡 千種 | 食育基本法に関する研究 ―議会内外の言説を手がかりにして― |
杉尾 |
| 合田 美香 | ケータイ・コミュニケーションにおける他者に関する研究 ―E.レヴィナスの他者論を手がかりにして― |
大関 |
| 小山 直樹 | 江戸後期・生野代官領における学問所の研究 ―『生野銀山孝義伝』の刊行をめぐって― |
安部 |
| 渡久山 さやか | 教師のライフコースにおける「転機」についてのナラティブ研究 | 宮元 |
| 西田 憲生 | 陰山メソッドの批判的考察 | 安部 |
| 松下 史生 | 自立をめぐる重度障害者と介助者のせめぎあい ―ある作業所の事例研究を通して― |
杉尾 |
| 依藤 光明 | 音楽療法におけるコミュニケーションの様相に関する研究 | 宮元 |
| 澤田 真弓 | 岸辺福雄の思想と実践 ―遊戯を基盤とした教育― |
渡邊 |
| 服部 英雄 | 主体的学習における「主体」の問題 ―新学力観における学習「主体」をめぐって― |
杉尾 |
| 善積 亜希子 | 子どもの感受性を育むアートの教育に関する研究 ―レッジョ・エミリア・アプローチを手がかりにして― |
大関 |
| 門田 龍太 | 学習における「わかる」という意味の考察 ~分数のわり算を用いて~ |
宮元 |
| 北川 彰 | 不登校支援における学習の変革 ―ドイツにおけるオルタナティブ学習センターの取り組みを手がかりとして― |
渡邊 |
| 小林 新 | 茶道における「型」の教育 ~身体と精神の統一~ |
安部 |
| 中島 貴子 | ニューカマーの子どもの教育に関する研究 ―教室における多文化共生に向けて― |
杉尾 |
| 井上 温子 | 公立中学校の教員組織文化に関する研究 ―インタビュー調査を手がかりにして― |
杉尾 |
| 谷髙 徹 | 大学進学希望者に対するキャリア教育 | 渡邊 |
| 今北 裕人 | マルティン・ブーバーの教育思想に関する研究 ―対話的関係を中心に― |
大関 |
| 上野 秀敏 | 子ども同士による支え合い ―カナダにおけるピア・サポートの理論と実践から― |
渡邊 |
| 木田 薫 | ライフステージを通しての遊びの質と意味づけの変化 | 宮元 |
| 北山 毅 | 少年院における矯正教育に関する研究 ―成績評価を中心として― |
安部 |
| 小林 良紀 | 「しつけ」をめぐる言説に関する研究 ―歴史社会学的考察― |
杉尾 |
| 堺 昭郎 | 学校教育における民間企業の経営理念に関する研究 ―NPM型組織マネジメントに注目して― |
渡邊 |
| 坂田 良久 | 被差別のアイデンティティを越えて ―ある女性のライフストーリー― |
杉尾 |
| 佐々木 暢子 | 教育におけるミメーシスに関する研究 ―Ch.ヴルフのミメーシス論における身体性に着目して― |
大関 |
| 佐藤 守活 | 学級委員を経験することによる資質の変化 | 宮元 |
| 西本 好男 | 教育における美の研究 ―J.ラカンの精神分析理論を手がかりとして― |
大関 |
| 皆本 大輔 | 日本的野球観の形成に関する研究 ―安部磯雄,飛田穂洲,佐伯達夫を中心に― |
安部 |
| 三好 永子 | 『エミール』にみる教師のことばかけ | 杉尾 |
| 稲垣 尚惠 | コ・メディカル養成課程における学生の臨地実習への「参加」を考える ~学生・卒業生への半構造化インタビューをとおして~ |
宮元 |
| 芦原 玲子 | 大正期の新中間層における家庭観に関する研究 ―『婦人公論』『主婦之友』を手がかりに― |
安部 |
| 石須 雄志 | 但馬聖人・池田草庵の教育思想研究 | 安部 |
| 植松 伸行 | 定時制高校と「不登校」 ―生徒自身からみた変容のプロセスと教師の関わり― |
宮元 |
| 坂本 祐樹 | ハンナ・アレントの「公共性」に関する研究 ~『人間の条件』を中心に~ |
杉尾 |
| 前田 泰資 | 愛国心教育に関する研究 | 大関 |
| 阿部 恵子 | ドラマ教育によるコミュニケーション力の育成 ―理論と実践からその可能性を探る― |
宮元 |
| 石原 清光 | 奄美諸島与路島のくらしと学び ―近代奄美教育史の視角と背景理解にむけて― |
杉尾 |
| 石見 純子 | 教師の語りから学級雰囲気をとらえる | 宮元 |
| 大田 尚美 | 「居場所」としての保健室に関する研究 | 杉尾 |
| 大村 高久 | 「相互成長としての教育」に関する研究 ―デューイのコミュニケーション論を手がかりとして― |
渡邊 |
| 岡田 修司 | 小集団活動を通しての児童の段取りする力の育ちと教師のかかわり ―状況論的アプローチ― |
宮元 |
| 田中 章子 | 読み手・聞き手・絵本の三項関係から見る《読み聞かせ談話》 ―ことばと身体の表出に着目して― |
宮元 |
| 田谷 京子 | 子どもに必要とされる美の経験に関する研究 ―美的人間形成論の観点から― |
大関 |
| 田原 俊記 | 近代学校における教師像の変遷に関する研究 ―師範学校規則の分析から― |
安部 |
| 西門 隆博 | 子どもと学校・教師との関係についての研究 ―地方公共団体Aにおける子どもの権利に関する条例の運用事例から― |
杉尾 |
| 野田 かおり | ドイツの若年就労支援 ―カッセルの生産学校を中心に― |
渡邊 |
| 美本 大輔 | 教育刷新委員会の研究 ―終戦直後の教育改革に果たした日本人の役割― |
安部 |
| 山本 真 | 声としての言葉の性格に関する研究 ―W.J.オングを手がかりとして― |
大関 |
| 青木 武矢 | H・ギーゼッケの「教育の終焉」論に関する研究 | 渡邊 |
| 江口 美保 | 重要な他者との関係のあり方からみた,中学生の自己の捉え方に関する研究 | 島崎 |
| 多井 綾美 | スウェーデンにおける就学前教育に関する研究 ―児童虐待を減少させるためにできること― |
渡邊 |
| 大向 勲 | 教師の「見える力」の形成過程 ~授業リフレクションを通して探る~ |
宮元 |
| 加藤 玲子 | 母親の「子育て観」に関する研究 ―育児雑誌の言説を通して― |
杉尾 |
| 川本 良子 | 自分の誕生の話を聞き,共有し合う学習が児童と家族に及ぼす心理的影響に関する研究 ―人間発達科第2学年の授業を通して― |
宮元 |
| 坂口 肇 | 中学生における学習観と学習行動との関係について ―原因帰属・自己効力感と関わらせながら― |
島崎 |
| 砂田 元未 | 教育における「他者」に関する研究 | 大関 |
| 田中 芙美子 | サマーヒルスクールの理論と実践 ―教育の受け手の意識に着目して― |
渡邊 |
| 中津 俊彦 | 「遊び」を通した自己形成に関する研究 | 大関 |
| 松田 育子 | 児童の自尊感情を育てる要因についての一考察 ―学級づくりにおける教師の働きかけの視点から― |
島崎 |
| 松永 智昭 | メディア空間におけるコミュニケーション ―タイムラグによる他者関係の変化― |
杉尾 |
| 松本 昭一 | ハンセン病差別の実態に関する研究 ―菊池恵楓園未感染児童養護施設「龍田寮」を中心に― |
安部 |
| 森尾 彩 | イギリス・フェミニズム運動とガヴァネス | 渡邊 |