修了生の声

「人」から学ぶ日々
教育コミュニケーションコース2年近田知富美さん
(令和6年度資料より)
小学校教員として勤める中で、学校教育の変容を感じ、維持と変化の必要な部分の双方について考えるようになりました。そこで、これまでの自身の教育実践を振り返るとともに、私が感じるさまざまな問題意識とじっくり向き合ってみたいと思い大学院で学ぶことを選択しました。
大学院では、あらゆる教育課題の根幹に、「コミュニケーション」の存在があることに気付きました。本コースでは、哲学、心理学、歴史学、社会学というさまざまな視点から教育コミュニケーションについて学び、考えることができます。講義やさまざまな文献からの深い学びに加え、先生方や他の院生などとの議論が楽しく、「人」「人とのつながり」から得られるものの大きさを実感しながら、充実した学生生活を送っています。

学びほぐしの旅
教育コミュニケーションコース2年衛藤 裕さん
(令和5年度資料より)
公立中学校で14年間勤務の後、教育を深く問い直したいと思い、選びました。コースでの学びは、対象である「教育」に多様なアプローチから迫ることが可能で、自分の問題意識に沿った研究ができます。コースの先生方はフレンドリーで、コース全体がオープンマインドな雰囲気です。所属ゼミの垣根が無く、学生同士の交流が活発です。
研究と並行して、これから教育現場に出る学部生と積極的に対話しています。学部のゼミ生に自身の教育実践を伝える一方、研究の仲間として多くの学びを得ています。教員時代から、子どもの居場所づくりに興味がありました。学内のボランティアステーションを介し、子ども食堂のボランティアに参加しています。

果てのない学びの旅へ
教育コミュニケーションコース2年苆野 大志さん
(令和4年度資料より)
天台宗の祖、最澄は「一隅を照らす、これ即ち国宝なり」という言葉を残しています。世間の片隅にあっても、その場所で懸命に努力できる人は尊いものだという思いが込められた語です。私は中学校教員をしながら本学に通っていますが、教育とは何か、コミュニケーションとはいかなる営みなのかといった問いに日々頭を悩ませています。
本コースでは、哲学や歴史学、心理学、社会学の視点から、それらの問いに光を当てていきます。しかし、そこに答えがあるわけではありません。一隅の問いを照らすその光は、新たな問いを生み出す光です。問いに光を当て次なる問いを発見していく過程そのものが学びなのかもしれません。果てのない学びの旅を心行くまで楽しめる場所がここにあります。

素朴な問いが
あか抜けるまで
髙橋 利明さん
(令和3年度資料より)
教育って何だ?コミュニケーションって何だ?と、素朴な問いにつまずいたとき、教育コミュニケーションコースではその答えを教えてくれる・・・わけではありません。より広く、より深く学問の裾野を広げられ、先生方の知の宝庫に一層溺れ、苦しみ、もがくことになります。学ぶ者にとってこれほどの幸福はありません。
また、授業やゼミにおいても、自ら探究するような学びは飽くことも尽きることもありません。際限なく湧き出る好奇心を上回る無尽蔵な英智がここにはあります。だからこそ苦しい、大海を遠泳するような学びの営みはまさに教育コミュニケーションの真理なのかもしれません。
つまり、最高に楽しい日々なのです。
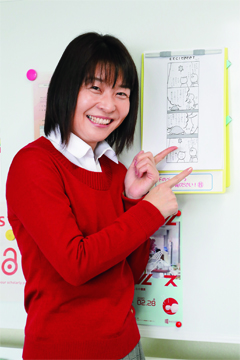
「離見の見」を持つこと
教育コミュニケーションコース2年谷口 祥子さん
(令和2年度資料より)
「離見の見」は室町時代の猿楽師、世阿弥の言葉です。「自分の姿を自分で見ることはできない。しかし、客観的に自分を外から見る努力が必要だ。」という意味です。私は小学校の教師をしていますが、教室は意外に閉鎖的で、経験を重ねる程、視野が狭くなっているのではないだろうかと思うことがありました。
現在、私が所属する「教育コミュニケーションコース」は、「離見」の一歩を踏み出した私にとって理想的な学びの場です。様々な分野の探究課題を寛容に受けとめ研究が迷路に迷い込まないように適切に指導してくださる先生方と、凝り固まっている考えをほぐし視野を広げる議論ができる同コース院生の仲間の存在があるからです。

今までの実践を見つめ直し、
視野を広げる機会に
川北 香織さん
(令和1年度資料より)
今、学校現場で直面している問題は、既存の知識では解決できないものとなっています。また、その内容も多岐にわたります。そこで、私はそれらの問題をより広い視野と専門的知識を持って、学校の中堅として、多角的・多面的視点から考察したいと思い、本コースへの入学を決意しました。
各分野で専門的に研究を重ねてこられた先生方の講義は魅力的で、コミュニケーションが持つ意義を深く捉え直すものであり、自分自身の実践を見つめ直すことにつながっています。また、多様な職種の仲間との対話は、今まで当たり前だと思ってきたことを改めて問い直す機会となっています。大学院での学びを現場で活かし、未来ある子どもたちと共に成長していける教師でありたいと思います。

研究者としての第一歩
教育コミュニケーションコース2年籔内 正明さん
(平成30年度資料より)
中学校教員になり8年が経ち、授業での様々な課題と向き合う中で子ども同士の会話に注目しました。教え学び合いが成立するためには、どんなことが必要なのかを探求したいという思いが強くなり、兵庫教育大学大学院に進学することとなりました。
研究に関しては、無知の状態から始まりましたが、情報収集や実験方法など、先生方の細やかな指導により順調に進めることができています。研究することで視野が広がっていくことを日々実感しています。また、大学院生活での対話が研究の新たな発想や発見に繋がっています。今後さらに様々な場面での対話を意識し、研究を発展させていきたいと考えています。
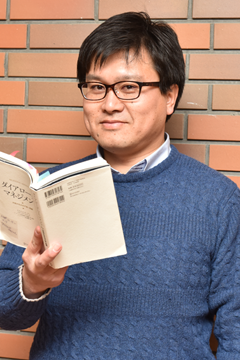
よりよい教育コミュニケーションとは何か?
人間発達教育専攻教育コミュニケーションコース2年
阿曽 奈生さん
(平成29年度資料より)
小学校教員になって10年が過ぎ、学校では中堅として充実した日々を過ごす一方で、何か物足りなさを感じていました。そこで、数年前から自ら問題意識を持って学びたいという思いが強くなり、兵庫教育大学大学院に進むことにしました。
本コースでは「よりよい教育コミュニケーションとは何か?」という根源的な問いがあります。専攻科目では、子ども―教師、子ども―大人をはじめとする関係性について、社会学、心理学、哲学、歴史学の観点から問い直したり、「演劇と教育」などのテーマごとにグループでフィールドワークやインタビューを行ったりしました。学校教育では「当たり前」とされる関係性を捉え直す機会は大きな学びとなりました。
大学院生活でのたくさんの出会いと対話は大きな財産となります。今後も出会いと対話を大切に、「学び続ける教師」でありたいと思います。

子どもたちと共に成長し続けることができる実践者を目指して
教育コミュニケーションコース平成28年3月修了
泉 美穂さん
(平成28年度資料より)
小学校での勤務を通して、子どもたちや保護者とのかかわりの重要性を感じ、大学院に入学しました。
授業では、教育における"コミュニケーション"に関する知識や理論を学び、特に、「教育コミュニケーション実践論」では、酒造りという師弟関係の中で、心・技・態(態度)がいかに伝承されるのかという課題を設定し、学校教育の中でなされるコミュニケーションと比較しました。
ゼミでの意見交流は刺激的なものでした。それぞれの立場からの意見や専門的な知見を聞くことで、小学校で求められている教育の姿、次の段階では子どもたちがどのように学び続け成長していくのかという、系統だった視点をもつことができるようになりました。今後も謙虚に学び続ける姿勢を失わず、子どもたちと共に成長し続けることができる実践者を目指していきたいと思います。

院生仲間とのディスカッションからも大いに刺激を受けます
教育コミュニケーションコース2年三浦 兼春さん
(平成27年度資料より)
教育コミュニケーションコース2年
川上 梓さん
(平成27年度資料より)
(三浦 兼春さん)
「教育」という営みをじっくりと考えたいと思い、学部から大学院に進みました。コースには、専攻分野の知識を背景に教育を語る方、経験豊富な現職教員の方、日本とは異なる社会・教育事情を語る留学生、学部から進学した同年代の仲間たちなどさまざまな方々がおり、日頃の会話からも大いに刺激を受けています。
(川上 梓さん)
今までの教員生活を振り返り、子どもたちとの関わり方についてもっと深く学びたいと考え、このコースを選びました。「教育におけるコミュニケーションとは?」という観点に立ち、それぞれの専門分野の先生方から示唆に富んだ学びを受けられます。世代や国を超えた仲間たちとのディスカッションはとても充実した楽しい時間です。新たな知見を得た上で、マクロとミクロの視点で考えることができると実感しています。

「教育」という営みについてあらゆる視点から学びを深められます
教育コミュニケーションコース2年荒井 隆一さん
(平成26年度資料より)
教育コミュニケーションコース2年
遠藤 和佳さん
(平成26年度資料より)
(荒井 隆一さん)
小学校教員になって16年。「不登校」「いじめ」「学級崩壊」など、深刻な問題を目の当たりにし、その解決方法を求めて入学しました。「教育」という営みを成立させている要因について、心理学をはじめ、さまざまな観点から多元的に学んでいます。新しい知見を得るたび、自分の中で混沌としていたものが整理されていき、「学ぶ楽しさ」を実感します。先生方は一人一人に懇切丁寧な指導をしてくださいます。大変充実したコースだと思います。
(遠藤 和佳さん)
「教育」という営みについて多様な視点から学びを深め、自分の幅を広げたいとの思いで、学部からストレートで進学しました。時に厳しくも愛情を持って接してくださる先生方、経験知に基づく話を熱く語ってくださる現職教員の院生、共に教員を志す同年代の仲間たちがいて、自分の課題にじっくりと取り組める環境が整っています。「教員になりたい」という志がより明確になり、視野の広がりを感じています。

ストレートマスターと現職教員が意見を交わす実践論の講義は貴重な時間
教育コミュニケーションコース2年薗 里奈さん
(平成25年度資料より)
教育コミュニケーションコース2年
松崎 京子さん
(平成25年度資料より)
薗 学部で中学校の技術について専門的に学んだ後、大学院に進みました。現在はさまざまな分野から教育を考えることができ日々、視野が広がっていると実感します。
松崎 私は現職の中学校教員です。講義を受ける立場になって、今までの教員生活を振り返ることができました。自分の経験と理論とを結び付け、さらに深い知識を学ぶことに喜びを感じています。
薗 院生控室ではゼミや学年に関係なく、研究のことや日常生活について相談に乗ってもらっています。また、現職教員とストレートマスターが意見を交わし、一つの課題を追究するという他コースにはない実践論の講義は、とてもためになります。
松崎 先生方は厳しくも愛情を持ってご指導くださいます。先生方の学問に対する熱い思いに触れ、教員になったころの初心に戻れたような気がします。
薗 将来、このコースで学んだ人との関わり方を教育現場で生かしたいと思います。


