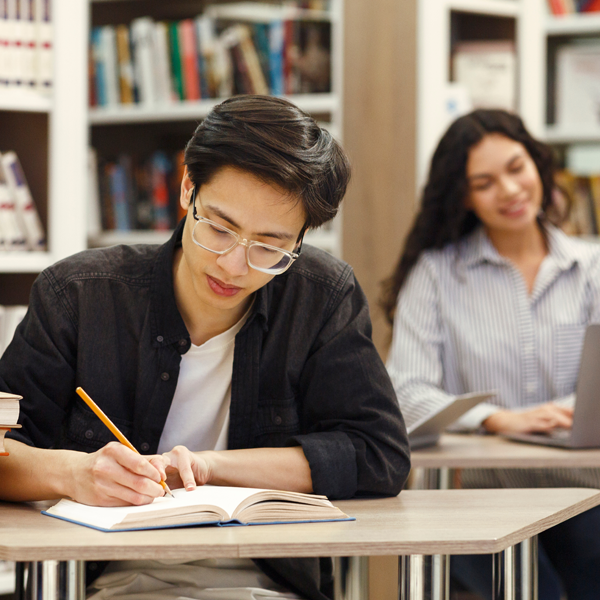アーカイブ
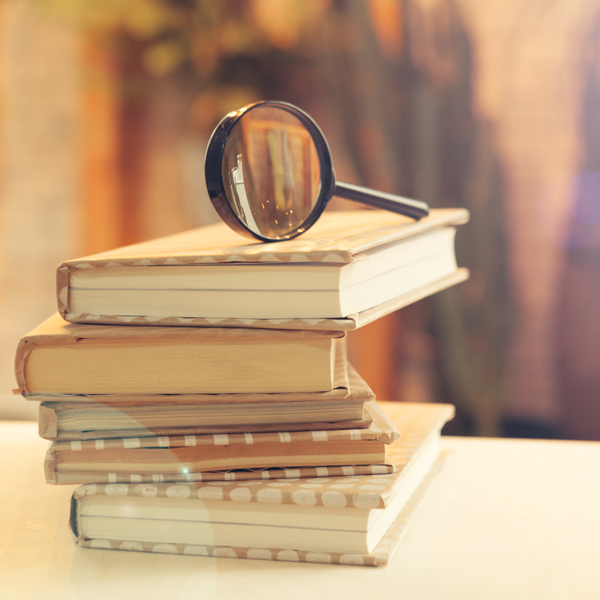
これまでの新着情報
| 2025年04月 | 山本康司先生が着任されました。 |
|---|---|
| 2025年03月 | 原田誠司先生が退職されました。 |
| 2025年03月 | 𠮷水裕也先生が関西学院大学に移られました。 |
| 2024年04月 | 吉川修史先生が着任されました。 |
| 2023年04月 | 濵野清先生、小倉拓郎先生が着任されました。 |
| 2023年03月 | 關浩和先生が兵庫大学に移られました。 |
| 2022年11月 | ホームページをリニューアルしました。 |
| 2021年07月 | ホームページを更新しました。 |
| 2021年12月 | 南埜猛先生がご逝去されました。 |
| 2021年09月 | 阪上弘彬先生が千葉大学に移られました。 |
| 2021年04月 | 渡邉正先生が着任されました。 |
| 2021年03月 | 小南浩一先生、米田豊先生が退職されました。 |
| 2020年05月 | ホームページを更新しました。 |
| 2020年04月 | 今出和利先生が着任されました。 |
| 2020年03月 | 難波安彦先生が退職されました。 |
| 2019年03月 | ホームページを更新しました。 |
| 2019年03月 | 吉本剛典先生が退職されました。 |
|---|---|
| 2018年05月 | ホームページを更新し、重要なお知らせを掲載しました。 |
| 2017年05月 | ホームページを更新しました。 |
| 2017年3月 | 原田智仁先生が退職されました。 |
| 2016年10月 | 福田喜彦先生(社会科教育)が着任されました。 |
| 2016年04月 | 山内敏男先生(社会科教育)が着任されました。 |
| 2016年03月 | 児玉康弘先生が逝去されました。 |
| 2014年03月 | 首藤明和先生が長崎大学に移られました。 |
| 2013年10月 | 森田猛先生(西洋史)が着任されました。 |
| 2013年04月 | 小南浩一先生(政治学)が着任されました。 |
| 2013年03月 | 河村昭一先生が退職されました。 |
| 2013年03月 | 坂口一成先生が大阪大学に移られました。 |
| 2012年09月 | 児玉康弘先生(社会科教育)が着任されました。 |
| 2012年03月 | 中村哲先生は関西学院大学に移られました。 |
| 2011年04月 | 坂口一成先生(政治学)が着任されました。 |
大学院

報告書・修士論文一覧
| 有馬 大貴 | 協同的探究学習を活用した小学校社会科授業開発研究 |
|---|---|
| 岩橋 嘉大 |
未来洞察型教育理論に基づく高等学校「歴史総合」の授業開発 ―「グローバル化」における域内経済システムに着目して― |
| 栗山 大輝 | 絵画資料を用いた中学校社会科歴史学習の授業開発 |
| 筒井 幸介 | 「概念レンズを活用した小学校社会科カリキュラムの開発と実践に関する研究」 ―経済の視点に着目して― |
| 友居 秀行 | 尼崎市における地域学習のあり方の研究 ―地域学習の授業実態と教師の意識調査を通して― |
| 中井 健一郎 |
伝統に根ざした主権者の育成を意図した中学校社会科授業開発 ―マイケル・オークショットの政治思考様式を視点にして― |
| 畠中 悠輔 |
デザイン思考を組み込んだPBL的単元構成により社会形成力を育成する授業実践 ―中学校地理的分野「地域の在り方:泉北ニュータウン少子高齢化問題」― |
| 土方 麻由 | 歴史的分野・地理的分野における「対立と合意」を視野に入れた中学校社会科授業開発 |
| 藤春 竜也 | 社会環境の変化が学校教育に及ぼす影響と適応についての考察 |
| 松尾 晋汰 | インターネット・SNS等を主体的に活用する資質・能力を身につけさせるための情報モラル育成に関する研究 |
| 山本 希望 | 小学校社会科における地図活用に関する研究 |
| 上原 瑞生 | 「視点の移動」を組み込んだ中学校社会科授業開発 |
|---|---|
| 小野 太郎 | 小学校社会科における「市民的リテラシー」を育成するカリキュラム−「対話」を取り入れた歴史学習の実践を通して− |
| 金本 和大 | 高等学校における生徒の対話的学習を促すICT活用と歴史授業開発−GIGAスクール構想に基づく日本史学習の提案をもとにして− |
| 亀田 まゆみ | 自己の意識を相対化する高等学校「歴総合」の授業開発−近代国家における国民形成の学習を通して— |
| 杉山 正人 | グローバルヒストリーの視点を組み込んだ「歴史総合」の授業開発−空間的スケールの拡大による「歴史の問い直し」を意図して− |
| 關 陸稔 | 字を素材とした中学校社会科授業開発−身近な地域の形成主体の育成をめざして− |
| 谷川 耕平 | 高等学校における「歴史的思考力」を育成する日本史授業モデル開発−防災カードゲーム教材「クロスロード」を活用した授業改善を目指して− |
| 春名 大誠 | 地理的分野と公民的分野の「意図的接続」を図る中学校社会科授業開発−「対立と合意」「効率と公正」を視点とした課題解決力の育成を目指して− |
| 藤田 真樹 | 資料の批判的読解を通して概念の再文脈化を目指す中学校社会科歴史学習の開発−単元「近代国家への改革」を事例にして− |
| 藤本 佳奈美 | 法原理を獲得する中学校歴史学習の開発−現代と過去の対比による法教育の実践− |
| 本田 晃寛 | <考える「倫理」>へ転換する「倫理」の授業開発−原典資料と対話を活用して− |
| 本田 洸介 | 主体性を育む授業開発−中学校社会科を中心に− |
| 松岡 大樹 | 大英帝国と海賊-私掠から東インド会社へ- |
|---|---|
| 浅野 晴良 | 六甲山における道迷い遭難の現状とその対策-「都市山」の山岳遭難について- |
| 伊藤 佳子 | 歴史教材としての「稲むらの火」に関する研究 |
| WU REN TU YA | 中国におけるモンゴル民族教育とアイデンティティの形成-内モンゴル民族学校とモンゴルの初等社会科教育の比較を中心に- |
| 後藤 義揮 | アナロジー思考の理論に基づく小学校社会科地域学習の開発-第3学年単元「伊丹市の酒造り」の場合- |
| 德永 行哉 | 近代イギリス社会の変化-余暇と娯楽- |
| 中野 佳和 | 大正期の受験競争と新教育運動をめぐる史的考察-『平生釟三郎日記』を史料として- |
| FRANCINI ELISA | 学校から職場への移行に関する一考察 -日本とイタリアの若者の状況の比較から- |
| 松岡 茉奈 | 中学校社会科地理的分野における復興まちづくり学習の授業開発-震災後の地域の在り方を構想する- |
| 松岡 優輝 | 課題解決型学習における「問い」の機能に着目した小学校社会科の授業モデル開発-地理的表示(GI)に登録された「神戸ビーフ」を題材にして- |
| 山岡 潤 | 「語りえないもの」について論じるとはいかなることか |
| 森 清成 | Society5.0時代に求められる小学校社会科産業学習のカリキュラム開発-システム・デザイン思考モデルを手がかりにして- |
| 軀川 法真 | 「人権」から「共生」へ―「共生」の社会科教育への示唆― |
|---|---|
| 髙齊 惠 | 主体性を尊重する支援のあり方について―中途診断された発達障害を出発点として― |
| 小島 栞 | ゴシック小説と近代イギリス社会―女性・身分・グランドツアー― |
| 猿渡正一朗 | インクルーシブ教育に向けた中学校社会科授業のモデル開発―小単元「発達障害と共生社会」の授業づくりを事例にして― |
| 杉浦 公香 | 18世紀イギリス社会と諷刺画―ホガース・中間層・社会規範― |
| 谷 直紀 | ルネサンス期イタリアにおけるパトロンのはたらき―ヒューマニズムとの関係を中心に― |
| 松本 誠也 | 鎌倉前期における重犯の取り締まりについて |
| 三木 教郎 | ビスマルクの「植民地政策」―ベルリン=コンゴ会議を手がかりとして― |
| 三嶋 文子 | 「構え」を中核とした高等学校「歴史総合」の授業開発―「現代的な諸課題」の解決を意図して― |
| 宮内 俊輔 | 高等学校地理歴史科地理における比較動態地誌学習の開発―省察による地域的特色の再構築を促す単元プラン― |
| 安永 虎吉 | 子どもが主体的に「問い」を立てる中学校社会科公民的分野の授業開発―「社会的な見方」と「社会的な考え方」を働かせた「問い」の機能に着目して― |
| 筏 信一郎 | 教育格差の現状と要因 |
|---|---|
| 池田 雄基 | システム論的視点による小学校社会科歴史学習の開発―第6学年単元「近代日本の成立-日露戦争-」の場合― |
| 井上 隆太郎 | 現代日本における年金財政の悪化 |
| 岩下 志麻 | 「民衆心理」から社会のしくみの認識を目指す中学校歴史授業の開発―小単元「幕府政治の揺らぎとお救いへの不満」を事例に― |
| 大迫 伎 | イギリス産業革命期における労働者と旅行―トーマス・クックの団体旅行を中心に― |
| 奥元 みゆき | 18世紀イギリスのコーヒーハウス―開放性と閉鎖性― |
| 川野 将寛 | アクティブリスクテイカーを育成するための高等学校地理A防災意志決定学習 |
| 佐竹 弘佑 | 地域社会形成主体を育成する中学校社会科地理的分野の授業開発―記号論的読みを活用した景観読み取りを通して― |
| 城谷 尚吾 | 生徒の主体的学習を促す中学校社会科授業開発―複数のEntry pointを用いた地理的分野「日本の諸地域」授業を例に― |
| 田中 悠也 | 思惑を視点として認識の深化を目指す中学校社会科歴史授業の開発―小単元「太平洋戦争までの国際関係と政治の動向」を事例に |
| 八田 友和 | 物質資料の変遷から社会構造を認識する中学校社会科授業開発―単元「残された物から古代社会のしくみを探れ」を事例に― |
| 松本 朋也 | 共和政ローマにおける「皇帝」の出現―支配・権威・自由― |
| 伊藤 剛史 | 徳川家康の天下掌握過程 |
|---|---|
| 伊藤 大介 | 兵庫県自然学校における指導補助員の実態と指導に与える影響―教員・指導補助員双方の立場から見た自然学校― |
| 今井 景子 | フランス革命期におけるフェミニズムの萌芽―コンドルセとオランプ・ドゥ・グージュを中心に― |
| 王 青 | 日中年金制度の比較―少子高齢化に対応した改革を中心に― |
| 岡本 啓介 | 問い続ける子どもを育てる小学校社会科学習―「問い」の誘発と「学習問題」の質を重視して― |
| 曽根 脩平 | 日本統治時代台湾におけるマラリア防遏事業と衛生思想の普及について |
| 竹原 昌伸 | 政治的視点を組み込んだ高等学校地理「農業」の授業開発―スケールの重層性および内発的発展に着目して― |
| 田村 尚基 | 現代の経済格差に関する一考察―雇用格差を中心に― |
| 長川 智彦 | 小学校社会科における社会問題学習の教育内容編成原理―合理的意思決定力の育成に焦点をあてて― |
| 長﨑 裕史朗 | 初期教育令(1879年制定)の再検討 |
| 原 孝彰 | 学校教員を対象としたGISの教育利用促進の検討 |
| 福田 真望 | 和辻哲郎は構造主義の夢を見るか? |
| 南 健太 | グローバル化の時代の世界史授業開発研究―同時代史的大観を原理として― |
| 山本 淳貴 | 法を視点とした歴史大観学習の授業開発―中学校歴史的分野「近世の日本」を事例として― |
| 渡辺 絵里 | 構成主義的アプローチによる小学校社会科情報産業学習の開発―第5学年単元「情報産業とわたしたちのくらし」を事例に― |
| 宮脇 愛子 | 戦後日本の平和教育の変遷と平和教育への提言 |
|---|---|
| 北川 雅史 | 太閤検地の実態に関する一考察―「百姓三分一・給人三分二」の分配法と石高制を中心に― |
| 片田 暁美 | 小学校社会科地域学習における論争問題の授業開発―嫌悪施設建設をめぐって― |
| 高 克文 | 曽国藩の思想研究―人材育成・経世致用を中心に― |
| 小菅 貴紀 | 中世興福寺による関所支配について |
| 坂本 晃子 | 経済格差と教育格差 |
| 佐藤 太紀 | 構成主義的アプローチによる小学校社会科防災学習の開発―第5学年単元「自然災害を防ぐ」を事例として― |
| 程 琪 | 日中の学校教育における社会参画に関する研究 |
| 中谷 真梨子 | 日米法関連教育の比較研究―Teen Peer Courtを手がかりにして― |
| 野口 権人 | リスク・コミュニケーションの視点を導入した中学校社会科防犯学習の授業開発 |
| 馬場 幸平 | 地方教育行成の組織及び運営に関する法律の成立における地域の実態~高砂市を事例として~ |
| 坂東 真理子 | 近代日本における「少女」の変遷 |
| 平林 幸 | 食品加工業におけるリスク・マネジメントの視点を取り入れた小学校社会科地域学習の開発―第3学年単元「梅干し工場ではたらく人びとの仕事」の場合― |
| 宮井 沙耶加 | 中国宋代における服飾の変遷 |
| 村越 政美 | ARアプリ「Junaio」を用いた教員研修用教材の開発―兵庫県篠山市を事例に― |
| 横矢 咲穂 | 中等歴史教育におけるメタヒストリー学習の理論と方法 |
| 渡邉 幸太 | ESDの視点を取り入れた溜池学習プログラムの開発―東播磨地域を事例として― |
| 周 立佳 | 日本統治時代台湾高雄の上水道事業について |
| 伊藤 剛史 | 徳川家康の天下掌握過程 |
|---|---|
| 伊藤 大介 | 兵庫県自然学校における指導補助員の実態と指導に与える影響―教員・指導補助員双方の立場から見た自然学校― |
| 今井 景子 | フランス革命期におけるフェミニズムの萌芽―コンドルセとオランプ・ドゥ・グージュを中心に― |
| 王 青 | 日中年金制度の比較―少子高齢化に対応した改革を中心に― |
| 岡本 啓介 | 問い続ける子どもを育てる小学校社会科学習―「問い」の誘発と「学習問題」の質を重視して― |
| 曽根 脩平 | 日本統治時代台湾におけるマラリア防遏事業と衛生思想の普及について |
| 竹原 昌伸 | 政治的視点を組み込んだ高等学校地理「農業」の授業開発―スケールの重層性および内発的発展に着目して― |
| 田村 尚基 | 現代の経済格差に関する一考察―雇用格差を中心に― |
| 長川 智彦 | 小学校社会科における社会問題学習の教育内容編成原理―合理的意思決定力の育成に焦点をあてて― |
| 長﨑 裕史朗 | 初期教育令(1879年制定)の再検討 |
| 原 孝彰 | 学校教員を対象としたGISの教育利用促進の検討 |
| 福田 真望 | 和辻哲郎は構造主義の夢を見るか? |
| 南 健太 | グローバル化の時代の世界史授業開発研究―同時代史的大観を原理として― |
| 山本 淳貴 | 法を視点とした歴史大観学習の授業開発―中学校歴史的分野「近世の日本」を事例として― |
| 渡辺 絵里 | 構成主義的アプローチによる小学校社会科情報産業学習の開発―第5学年単元「情報産業とわたしたちのくらし」を事例に― |
| 揚村 剛 | 伊沢修二の台湾教育構想 : 混和主義を中心に |
|---|---|
| 阿拉坦蘇布達 | 日本のサービス業におけるホスピタリティ精神 |
| 王 涵 | 日本における多文化共生をめぐって : 国際化政策に関する条例の考察から |
| 澤田 裕貴 | 清朝末期の革命結社 : 光復会会員の異民族王朝打倒思想 |
| 戚 斌 | 台湾土地改革史研究 : 第一回・第二回土地改革の分析を中心に |
| 詹毅男 | 日本と中国の社会起業に関する比較研究 |
| 其楽木格 | 台湾原住民の服飾について : ツオウ族,ルカイ族,アミ族を中心に |
| 寺田 孝晃 | 日本の南方進出 : 軍政期および南洋庁による民政期を中心に |
| 計倉 康和 | 「法教育」を視点にした小学校社会科授業構成論研究 |
| 中岡 真一 | 大阪市における「生活介護」の現状と課題 |
| 白烏雲塔娜 | 現代中国の大学生の結婚観 |
| 藤原 砂織 | 絵画史料を活用した中学校歴史授業開発 : 「南蛮屏風」の読み解きをとおして |
| 胡日査必力格 | 中国の退耕還林還草プロジェクトの計画と実際 : 内モンゴル奈曼旗を中心として |
| 山﨑 光哲 | 個人の意思決定の精緻化を目指す高等学校公民科の授業開発 |
| 吉崎 雄貴 | 子どもによる知識の構造の精緻化を目指した社会科授業開発 : 「事象の分割」と「因果関係」に着目して |
| 稲葉 武大 | 現代メイドの死への渇望とエクスタシー : 家庭崩壊,ネットと個人化,発達障害傾向にある少女たち |
|---|---|
| 岩本 剛 | 部落史研究の成果を組み込んだ小学校歴史授業の開発 : 「部落差別を知る」から「部落差別のしくみが分かる」へ |
| 宇和 誠 | ヒューマンインターフェースを視点とした電子黒板活用による小学校社会科授業の開発 : 第3学年単元「松山市ってどんな町~城下町のひみつ~」の場合 |
| 大西 慎也 | 小学校社会科授業における子どもの「思考」の評価 : 探究過程における「思考」の構造を視点として |
| 大本 健次朗 | 土佐国大忍荘の支配と在地動向 |
| 岡本 怜子 | 文覚論 : 神護寺復興と後白河院・頼朝との関係を中心に |
| 小倉 猛昭 | 社会科問題解決的な学習におけるICT活用の一考察 : ガニェの「教授事象」による学習過程を視点とした分析 |
| 郭 三三 | 日本の対華直接投資に関する一考察 |
| 金成 拓哉 | 高等学校日本史におけるBC級戦犯裁判に関する内容開発研究 : 単元「戦犯裁判を考える―BC級戦犯裁判を中心に―」 |
| 光 明 | テレビニュース番組の娯楽化に関する研究 |
| 紅 蘭 | 日本と中国における初等教育社会系教科の比較研究 : 内モンゴル自治区を事例として |
| 齋藤 俊太 | 戦国期齋藤氏の美濃国支配の確立過程 |
| 坂元 亮 | フィールドワークを通して公共性の構築を目指す高等学校地理Aの授業開発 : 中山間地域における地域活性化を題材として |
| 薩楚拉 | 内モンゴル・モンゴル民族における家庭教育の変遷 |
| 繁畑 里奈 | いじめのネットワークとコミュニケーション |
| 島袋 ゆい | 多元的な自国史認識を育成するカリキュラムの開発 : 地域(琉球・沖縄)の視点から |
| 謝 青 | 中国都市部の年金制度と日本の年金制度の比較研究 |
| 譚 双双 | 中国の医療保障制度の現状と改善策に関する一考察 : 日本の医療保障制度との比較を通して |
| 趙 銀淑 | 1990年代以降における中国朝鮮族農村の変容 : チーリン(吉林)省チャンパイ(長白)朝鮮族自治県シーアルタオコウ(十二道溝)村を事例に |
| 仲尾次 弘教 | 差別論から見る「沖縄問題」 : 排除のメカニズムに着目して |
| 哈斯図力古爾 | 寧波紡織繊維産業の研究 : 紅幇と寧波紡織繊維企業を中心に |
| 畑 和馬 | 子どもの思考の連続性を導く中学校地理的分野の授業開発 : 既習知識の活用による「学習課題」・「仮説」の設定方法を中心として |
| 古塚 明日人 | グローバル世界の市民性教育としての世界史 |
| 宝 金頂 | 中国の養老保障の現状と今後の課題に関する研究 |
| 簑田 心一 | 古代播磨における諸勢力の進出 : 『播磨国風土記』を中心に |
| 安田 博貴 | 高等学校日本史における伝統と文化に関する授業構成と授業開発 : 中世・近世の伝統と文化に関する授業事例を手がかりに |
| 吉田 翔大 | 中学校社会科歴史的分野における思考力形成を意図する授業開発 : 歴史的価値判断型の授業モデルの事例をもとに |
| 飯野 卓 | 近世前期松江藩における農政の展開 : 岸崎左久次の村落類型観を通して |
|---|---|
| 内本 侑希 | 平安・鎌倉期における大学別曹の機能 : 勧学院を中心に |
| 王 亜林 | 第一次日本占領時期における青島地区の初等教育の状況 |
| 小田 浩平 | 探究過程における「視点」の獲得と応用 : 立場の転換による認識の変化に着目して |
| 小田口 尚史 | 平安・鎌倉期摂津国猪名荘における支配と在地動向 : 鴨御祖社と東大寺の抗争を中心に |
| 郭 春 | 現代中国における大卒者の就職意識と実態 |
| 金 国花 | 中国雲南省の観光開発と地理的要因 |
| 芝 貴文 | 中核となる問いの設定条件を明確にした社会科授業設計 : 「なぜ疑問」の「質」に着目して |
| 吉米斯 | 中国内モンゴル自治区ウーシン旗における自然環境と社会環境に関する地理学的研究 |
| 城嶋 亮佑 | 宇喜多氏の戦国大名化 |
| 曹 昕ブン | 中国近現代女性服飾文化の変遷 : 上海を中心に |
| 松 迪 | 外国人研修生・技能実習生制度の現状と課題 |
| 張 静 | 日中の新規大卒労働市場の比較 |
| 德永 正彦 | 中等歴史教育における時代総括型主題学習の教育内容開発 : 「総動員帝国」理論を手がかりとして |
| 中田 将樹 | 地理歴史科の世界史と日本史の内容関連に基づく単元開発 : 世界史の単元「大航海時代」を事例に |
| 西沖 尚士 | クリティカル・シンキングの因果関係決定方略を用いた社会科授業設計 |
| 哈森高娃 | 内モンゴルフルンボイル地域モンゴル族の社会変動と民族生活の変容 |
| 馬場 順平 | 「制度」から時代の特色をとらえる歴史授業の開発 : 高等学校地理歴史科日本史Bにおいて |
| 馬 撒仁 | 中国の農業生産と農産物の輸出入 : 内モンゴルの農地牧草地の保全のために |
| 三浦 哲史 | 中世三河における真宗教団の展開 |
| 宮下 貴光 | 中学校社会科歴史的分野における博物館との連携に基づく授業開発 : 赤穂市立歴史博物館との連携を事例として |
| 社谷内 健太 | 社会参画を意図するNIEとしての中学校社会科公民的分野の授業開発 : 裁判員制度を事例として |
| 李 明麗 | 近代中国東北に於ける糧桟の状況 |
| エンセツ | 現代社会における「かわいい」概念の生成と変容 |
|---|---|
| 王 洋 | 中国における伝統文化に関するカリキュラム構成と授業開発:―小学校「品徳と社会」教科を手がかりに― |
| 太田 達志 | 地域教材を視点にした中学校社会科公民的分野の授業開発:―経済単元を手がかりにして― |
| 川端 夕貴 | 中国資料に見られる麒麟の一考察 |
| 格希格代 | 日本と中国における環境教育の歴史と現状 |
| 後藤 順子 | 現代日本の若者のアイデンティティ再考:―キャラ的コミュニケーションからみる自己概念のダイナミズム― |
| 酒井 貴史 | 近世における播州三木金物の流通:―仲買問屋の活動を中心として― |
| 祝 穎楠 | 映画作品の翻訳とその受容:―宮崎駿『千と千尋の神隠し』の受容の日中比較 |
| 蘇倫高娃 | グローバル化時代の民族文化:―モンゴルの伝統歌舞を事例として― |
| 趙 従勝 | 戦前期における海南島の農業調査:―日本人の農業調査を中心に |
| 張 せい | 中国都市部の年金制度と日本の年金制度の比較研究 |
| 張 芳 | 中日中等地理教育における世界地誌学習の比較:―科学的社会認識を形成する地理授業を目指して― |
| 陳 長江 | 内モンゴルにおける観光地域に関する地理学的研究 |
| 任 偉 | 嘉靖年間における倭寇の研究:―王直の評価を中心に― |
| 宝山 | 中国の政策・制度が内モンゴル・モンゴル人にもたらした影響について:―赤峰市オンニョード旗バローンゴールスアイリを事例として― |
| 哈斯巴特尓 | 中国・内モンゴルにおける民族教育の現状と課題:―インタビュー調査の分析を中心にして― |
| 藤澤 亮二 | 高校世界史における「帝国主義」の授業開発:―「長い20世紀」論を手がかりに― |
| 包 金財 | 中国の農村における社会保障制度に関する研究 |
| 松永 哲郎 | 「人間類型」論を用いた社会科授業の構築:―地理的分野における社会認識形成を事例として― |
| 村上 悠史 | 日本統治時代台湾における在来製紙業の展開 |
| 山縣 重宣 | 寧波における土地改革 |
| 和田 壮平 | 絵画史料を活用した中学校社会科歴史的分野の授業開発 |
| 渡邉 希 | 寛政期前後の大田南畝:―狂歌界との関わりを中心に― |
| 天野寛子 | 織田政権と王権 |
|---|---|
| 荒木宗太 | 多田銀銅山の観光資源化に関する政策研究 |
| 石丸晃一朗 | ソ連型社会主義計画経済についての一考察 |
| 岩西紀幸 | 関東地方における被差別地域の歴史と課題-東京の皮革産業を中心として- |
| 郭維テイ | 台湾の社会保障改革に関する一考察 |
| 北川智恵 | 市民性教育としての「子どものための哲学」 |
| 高青菁 | グローバリゼーションにおける家族再生産領域の移動-台湾のベトナム人花嫁を事例として- |
| 河本尚 | グローバリゼーションにおける個人化と個人の新たな社会的存立基盤-U.ベック「リスク社会論」の批判的検討を通じて- |
| 小鷹狩美菜 | 子どもの発見的認識能力形成のための生活科授業構成論研究 |
| 齋藤尚文 | 鈴木商店と台湾開発-樟脳事業を中心に- |
| 蔡娜娜 | 現代中国の若者の意識とライフスタイル-改革開放30年で成長した「80后」の分析から- |
| 宋ハンハン | 中国と日本の年金制度改革の比較 |
| 立石秀一 | 非行少年の更生保護に関する一考察 |
| 谷 聡 | 習得した知識の活用場面を組み込んだ「日本の諸地域」学習の授業設計-「人口や都市・村落を中核とした考察(近畿地方)」を事例として- |
| DANG THI LOAN | ドイモイ期を中心としたベトナムの経済発展過程 |
| 埴岡靖司 | 「マルチスケール」の観点を利用した小学校社会科学習-産業学習の内容開発を通して- |
| 浜野勇貴 | 日本統治時代台湾のバナナ産業-台中州・高雄州青果同業組合を中心に- |
| 東田健 | 既修得内容及び経験を活用した社会認識形成-高等学校地理教育を事例として- |
| 前田智子 | 「親水」の概念を取り入れたまちづくりに関する社会科授業開発 |
| 三枝修 | 高等学校における伝統と文化に関する教育のカリキュラム編成と開発 |
| 向井隆盛 | 小学校社会科における伝統や文化に関するカリキュラムの構成と開発-内容の領域と配列を視点にして- |
| 茂崎江里子 | 小学校社会科における読解的歴史教材構成論 |
| 森本晃弘 | 地域史との関連を視点にした中学校社会科歴史的分野の授業開発-「近世の日本」と「現代の日本と世界」の単元を手がかりに- |
| 秋山和夫 | 中世非人の研究 |
|---|---|
| 浅野光俊 | 問い続ける子どもの育成を目指した社会科授業設計-概念探究型社会科における仮説の機能を手がかりとして- |
| 有光昭洋 | 「法教育」学に関する基礎的研究-日本国憲法の基本理念実現をめざす法教育実践- |
| 池原一磨 | 日本統治時代中期の台湾の糖業~品種改良を中心に~ |
| 井上敏孝 | 日本統治時代基隆港築港事業 |
| 植原優子 | 韓国の映像世界にみる地理空間の再現性 |
| 楫直樹 | 少年犯罪の更生保護における保護司制度の現状と課題 |
| 近藤誉輔 | 社会認識教育としての人権教育の創造-人権総合学習との峻別を意図した中学校歴史的分野授業開発- |
| 鈴木祐子 | 中学校地誌学習における世界像-「空間認識」及び「社会と自己の関係性」の形成を視点として- |
| 立花良祐 | フードシステム・アプローチによる小学校社会科授業の教材開発-第5学年単元「日本の食料生産」を事例として- |
| 轟和也 | 慶応三年・王政復古政府期における越前藩の政治動向 |
| 野村直道 | 近衛家領丹波国宮田荘における悪党について~悪党生西の評価について~ |
| 船引洋志 | 明治前期における教育制度及び教員の特権・拘束内容 |
| 堀内哲 | 若年層の労働市場の現状-特に若年層の学力低下が労働市場に与える影響を中心に- |
| 松井仁志 | 社会科授業における情報読解力育成のための授業構成論-兵庫県のNIE実践報告書を手がかりに- |
| 松原聡嗣 | 知的特別支援学校における社会科学習指導の性格と改善 |
| 美見卓 | 概念地図法を組み込んだ社会科授業設計 |
| 宮崎貴臣 | 明治初期中央官員に関する研究 |
| 山内紀明 | 中学校社会科に関連する伝統や文化に関する授業開発-地理的分野「世界と日本の伝統的な生活と文化」を手がかりにして- |
| 蓮花 | 中日国交の正常化に関する一考察-中国のアジア外交の主導権確立にむけて- |
| 石原善知 | 世界史教育における「中央ユーラシアの遊牧世界」の授業開発~前近代の遊牧国家の構造を題材にして~ |
|---|---|
| 上田茂 | 多民族学習としての「日本史」教育の研究-近現代のアイヌ・沖縄人の視座から- |
| 額日徳木図 | 蒙古連合自治政府時代の教育事業について-チャハル盟、シリンゴル盟を中心に- |
| 大垣輝行 | 戦後の部落差別解消策-姫路地方を中心として- |
| 大友秀一 | 小学校におけるGISの学校安全への応用に関する研究 |
| 岡昌子 | 絵巻物を活用した歴史的思考力の育成-高校「日本史」の授業開発を手がかりとして- |
| 折坂悠太 | 日本登山の現状とアルピニズム再構築 |
| 勝山一郎 | 空港が地域に与える経済効果に関する一考察 |
| 金龍哲 | 中国の高齢化社会における都市と農村の社会保障-養老保障の社会学的考察- |
| 河野紘行 | 初等教育におけるGISの援用 |
| 新地比呂志 | 汪兆銘の対日政策の変遷について-1930年代を中心にして- |
| 末永琢也 | 社会科授業におけるグローバル教育の教材開発研究-大津和子氏の実践事例を手がかりにして- |
| 鈴木俊 | 歴史的思考を育てる歴史授業構成の論理に関する研究-高校歴史授業の先行実践分析を手がかりに- |
| 戸田克典 | 視点と複眼的思考を鍵概念とした社会認識・市民的資質の育成-アジアにおける国際的トランスファー教材の開発を通して- |
| 西田裕子 | ネパール中央区における都市・農村の生活様式とその変容 |
| 服部太 | 子どもの暗黙知を生かした社会認識形成-エネルギー問題の学習を事例にして- |
| 東元信浩 | 科学的判断を基盤とした市民的資質の育成-社会事象における人間の行為から分析的視点を育てる社会科授業- |
| 藤井健太 | ユリウス・クラウディウス朝と皇帝家解放奴隷-クラウディウス帝及びネロ帝の治世を中心に- |
| 藤尾智勝 | 地理分析とコンピュータ利用技術-開発環境とネットワーク・システム- |
| 藤本将英 | 知識創造の法則性を組み込んだ社会科授業設計-「テンプレート論」を手がかりにして- |
| 虫本隆一 | 歴史解釈学習の開発と実践分析 |
| 森本孝伸 | 学校選択が個人に及ぼす経済的影響についての一考察 |
| 米澤和哉 | 高等学校地歴科における科目「日本の文化」の性格と授業実践 |
| 東淳子 | 女性史に着目した近代日本の歴史教育内容論~中学校歴史的分野を事例として~ |
|---|---|
| 天野拓夫 | 知識の質と思考の働きに着目した社会科授業設計-社会認識形成を図る評価規準の開発を通して- |
| 池野綾 | キャリア教育カリキュラムに基づいた小学校社会科の単元開発 |
| 植田修平 | 戦国期の奉公衆について-丹波久下氏と筑前麻生氏を中心として- |
| 植野晃浩 | 聖武天皇「東国巡幸」の歴史的意義 |
| 上前康和 | 日本の公的年金改革に関する一考察-特に2004年の年金改革を中心に- |
| 宇都宮明子 | 現代社会の考察をめざす日本史授業研究-「総力戦体制論」の批判的学習を通して- |
| 小田昭善 | ニケフォロス2世とヨハネス1世の軍制改革~10世紀ビザンツ帝国における軍事関連著作の考察から~ |
| 上赤義人 | 小中一貫教育における社会科公民的領域のカリキュラムと単元の開発~政治単元を手がかりとして~ |
| 紙田路子 | 地域経済とインタラクションする小学校参画型社会科授業の設計-地域商店の活性化をめざして- |
| 上出正彦 | 民間信仰を活用した高等学校日本史教育の研究 |
| 喜瀬典彦 | イギリス中等地理教科書 New KEY GEOGRAPHY for GCSE における内容知・方法知の構造 |
| 記村公輔 | 中世後期兵庫津における商品流通と関料-兵庫北関入船納帳の分析を手がかりとして- |
| 櫛田正幸 | 中学校社会科歴史的分野における授業改善を目指して-「人物学習」を取り入れた授業開発を中心に- |
| 河本学 | 「コスト意識」に焦点を当てた小学校社会科における金融教育-セルフ・ライフプランニングのスキル獲得をめざして- |
| 小山真永 | 中世高野山領における宗教構造-御影堂陀羅尼田寄進をめぐって- |
| 佐藤義晃 | 林則徐の黄河治水事業 |
| 皿池健二 | 兵庫県南部における中小企業の経済状況 |
| 史静 | 明・清時代北京における娯楽について |
| 白井征彰 | 日本統治時代台北の上下水道について |
| 菅良樹 | 幕末期における大坂定番制度について-播磨国山崎藩本多家の事例を中心に- |
| 須谷哲章 | 幕末維新期における姫路藩の政治的位置に関する研究 |
| 角田正和 | 内容知と方法知の統一的習得をめざす「身近な地域の調査」の授業開発-三澤勝衛の「郷土地理教育」を援用して- |
| 辻寿一 | 世界史教育内容編成の研究~国民国家論の視点から~ |
| 中井健博 | 第一回総選挙における神奈川県第四選挙区の研究 |
| 中園貴之 | 清代後期黄河流域水災史研究 |
| 中山達也 | 近年の少年犯罪とそれをとりまく言説 |
| 橋本巧 | 環境史の視座からの歴史教育内容開発-中学校社会科歴史的分野を事例として- |
| 春名美佳 | 海浜堆積物からみた石垣島の完新世環境変化 |
| 宮崎竜彦 | 土佐海援隊の研究-長岡謙吉を中心とした人的構成の研究- |
| 本吉健太郎 | 中世後期京郊荘園の研究 |
| 物應忠 | クレオパトラと共和政ローマ |
| 山岸藍 | 少年犯罪と子どもの人権-青少年保護の関点から- |
| 山田央 | 戦国大名後北条氏の水軍編成 |
| 吉田正太郎 | 大学教育が個人に及ぼす経済的影響に関する一考察 |
| 梁海山 | 中国内モンゴルの地域変化と都市形成に関する地理情報システム(GIS)分析 |
| 青木章浩 | 風刺画を活用した中学校歴史の授業構成~ビゴーの『トバエ』を手がかりに~ |
|---|---|
| 東大介 | 地域社会における少年犯罪の実態と分析-日本とくに大阪府の動向を中心として- |
| 安藤史子 | 学生の結婚観に対する夫婦・親子関係の影響について-非婚大学生を対象としたアンケート調査から- |
| 池田宏 | 相互作用にみる社会的ひきこもりの構築 |
| 池田有気 | 教科書の国際比較を通じた高校日本史の授業開発-関係国と第三国の近現代史記述を手がかりとして- |
| 岩野清美 | 「経済を通して社会がわかる」中学校社会科の授業構成-岩井克人氏の経済認識を中心として- |
| 上田浩一 | 地域独自の教養知・体験知を生かす社会科の授業設計-ホーム・リージョナル・スタンダードの設計を通して- |
| 内田賢一郎 | 中学校社会科における戦後史学習の教材開発-「プロ野球」を手がかりとして- |
| 金子徳孝 | グローカル的資質形成を意図する小学校社会科の単元開発-国際理解に関連する実践事例分析を手がかりにして- |
| 加用卓也 | 高等学校における経済教育に関する一考察 |
| 坂内健太郎 | 中等歴史教育におけるメタヒストリー学習の視点と方法-英国ナショナルカリキュラム「歴史」を手がかりに- |
| 佐野薫 | 国際理解のための小学校社会科歴史学習の構想と実践-地域の中の「世界」に着目して- |
| 谷口勲 | 中学校社会科公民的分野「経済」単元における授業開発-先行オーガナイザとしての「家計簿」を教材として- |
| 徳田淳 | 構造化論を生かした世界史教育の研究-内容・指導・評価の観点から- |
| 戸澤由子 | 清代末期江浙地方の蚕糸業 |
| 中田隆文 | 兵庫県における、祭りと民衆支配に関する一考察~姫路地方を中心として~ |
| 中田智晴 | 現代社会におけるネイチャースポーツ-山と人間との関わりの変遷から- |
| 西岡政哉 | 鎌倉幕府の奥州支配の展開~「奥州惣奉行」を中心に~ |
| 西尾仁志 | 世紀転換期のインド帝国におけるヒンドゥーとムスリム |
| 野崎雅敬 | 日本統治時代の台湾塩専売事業-明治28年~大正12年まで- |
| 松原茂仁 | 民間企業による学校経営-日本に適応するチャータースクールに関する社会学的一考察- |
| 矢田浩太郎 | 韓国南西部と西日本におけるレスの特質 |
| 渡辺敬宏 | 学校教育の成果による人的資本の蓄積に関する一考察 |
| 今井豊 | 鎌倉末~南北朝期における仏教の地方展開~浄土から禅への転換をめぐって |
|---|---|
| 圓谷大介 | 「丹波杜氏」の酒造出稼ぎに関する実証的研究-「伝統型出稼ぎ」の一考察- |
| 大迫拓也 | 社会科における授業設計と連動した評価の在り方-「内容知」と「方法知」の評価の枠組みの構築を通して- |
| 笠松弘 | 太平洋戦争期・陸軍の対外観-軍務局長 武藤章を中心として- |
| 熊木浩之 | アメリカ合衆国連邦体制の確立-ハミルトンからジェファソンへ- |
| 古賀義彦 | 社会科地理的分野における評価内容・方法-イギリスにおける地理評価問題の分析を通して- |
| 小橋拓司 | 日本における教育GISの展開に関する研究 |
| 小林秀行 | アメリカ初等法関連教育の単元構成と授業構成-Primary VOICEとVOICEのプロジェクトを手がかりにして- |
| 小林慎 | 小学校における起業教育プログラムの構成と開発-社会科との関連を視点として- |
| 坂井誠亮 | 知的な認識形成をめざす生活科の授業設計-「知的な気付き」を深める学習過程と指導に生かす評価- |
| 鈴木巨裕 | 教養としての空間認識形成を目指す社会科学習-小学校産業学習を通して- |
| 陳瑜 | 蔡元培の高等教育思想についての研究 |
| 中嶋巨人 | 大久保忠寛の議会制度論に関する一考察 |
| 成瀬康洋 | 極東軍事裁判再考-東條英機を中心として- |
| 平井敏之 | 儒学者谷三山の尊皇攘夷思想の研究 |
| 古田克己 | 戦没者追悼施設の研究 |
| 本間恵介 | 日本統治時代の台湾におけるマラリア防遏事業について |
| 松本真光 | 小学校社会科における国際理解単元の教材開発-開発教育の実践事例を手がかりにして- |
| 三原慎吾 | 日本における博物館の設置と活動の分析と展望-地域社会および学校教育との連携をめざして- |
| 山根正也 | 女性労働者の現状~兵庫県南部の状況を中心として~ |
| 池辺和彦 | 近世における関東相給村落の構造:上総国山辺郡台方村を事例として |
|---|---|
| 生駒義郎 | 小学校社会科カリキュラムにおける「内容知」・「方法知」の構造:アメリカ合衆国「地理ナショナル・スタンダード(National Geography Standards)」の検討を通して |
| 磯部剛司 | 多面的な見方を育てる人物学習の研究:小学校の近現代史教育を事例として |
| 浦恵理 | 『大鏡』の研究:作者論を中心に |
| 漆野篤 | 高卒労働市場の縮小とその諸要因 |
| 大上博右 | 現代日本社会と宗教:世俗化論再考:イエ宗教の視点から |
| 香川定昭 | 愛知県の人口分布および用水地域の空間分析 |
| 菊池八穂子 | フードシステムの概念を生かした農業学習:川下重視の傾向の中,自立経営をめざす農家を事例として |
| 木下春雄 | 小学校社会科におけるまちづくり学習の授業設計:子どもの参画の資質形成を視点にして |
| 小谷恵津子 | 社会科における概念の獲得と経験:地理学習で用いられる資料の検討を通して |
| 齊藤昌長 | 「食の安全」から見た社会科授業の開発:消費者教育の視点を取り入れて |
| 齋藤裕磨 | WEBサイトを活用した「和文化教育」の単元開発:小学校社会科を手がかりにして |
| 菅原弘貴 | 小学校社会科における「情報」を柱とした教材開発:情報教育との統合を意図して |
| 鈴村克徳 | 中学校社会科における多文化共生に関する公民シミュレーション教材の開発:定住外国人との共生を図る「希望が丘団地」を事例にして |
| 曽欣誼 | 「日本と台湾におけるボランティア活動に関する比較研究」:震災時におけるボランティア活動を通して |
| 高野雅信 | 「学制」頒布前後における名東県(現徳島県)の教育情況 |
| 滝脇隆一 | 中学校社会科公民的分野における環境学習プログラムの開発:アメリカ環境学習プロジェクト・ワイルドの考察から |
| 竹本周史 | 中学校社会科公民的分野「人間の尊重」単元の授業開発:子どもの人権を視点として |
| 塚本隆司 | 過去の有事法制研究からみた現在の有事法制の成立への経過と意義 |
| 中島正登 | 政治家西郷隆盛の再評価:福沢諭吉『丁丑公論』を中心として |
| 永田敏彦 | 社会参加を意図する小学校地域学習の授業構成:「まちづくり」に関する実践事例の分析を通して |
| 中西聡子 | 天保期における川浚と大坂の民衆:「御救大浚」と「天保山」の誕生を中心に |
| 楢原裕一 | 小学校令改正期における兵庫県下小学校教員の諸問題 |
| 西村卓洋 | 海からの視点を生かした歴史の教育内容開発:高校歴史単元「東アジアの地中海」の場合 |
| 沼田知正 | 近世の家訓・遺言・家法に関する考察:幾内・近国とその周辺地域における「庶民」を中心として |
| 濱田明利 | 揖保川流域のたたら製鉄による地形改変 |
| 岡澤順治 | 「人権」に視点をおく小学校社会科歴史学習の研究 |
|---|---|
| 金崎正規 | 都市交通システムにおける路面電車/LRTの地理学的研究:日本とドイツおよび周辺国の現状考察と再評価 |
| 鎌田隆男 | 地域素材を通して歴史の学び方を身に付ける中学校歴史授業開発:港湾都市神戸を事例にして |
| 河野真也 | スコットランド長老派教会の成立に関する研究 |
| 木村公則 | 中学校社会科地理的分野「地域の規模に応じた調査」単元のWEB教材開発:系統的な地域調査の方法を視点として |
| 黒田雅秀 | 架橋と距離短縮に伴う島の地域変化の研究:周防大島と小豆島の比較考察より |
| 桑田卓郎 | 外資系金融機関によるM&Aが日本の金融機関の経営に及ぼす影響 |
| 謝明智 | テレビCMにおける性差意識の比較研究:日本と台湾の比較を中心に |
| 新福大健 | 台湾総督府の糖業政策と糖業連合会の活動:1895年から1914年を中心に |
| 田野雅寛 | 旧ユーゴスラヴィア崩壊の要因に関する研究:コソボ問題を中心として |
| 照屋信治 | 『琉球教育』(1895~1906)に見る沖縄教育の原型:新田義尊の論を中心に |
| 時村孝完 | 高等教育事情からみるベトナムの地域性:南北間の比較考察から |
| 中谷昇 | 対抗文化認識をめざす社会科の授業設計:山村生活者の視点から見た現代社会 |
| 中野雄介 | 明治維新政権樹立に対する坂本竜馬の貢献に関する研究 |
| 馬場勝 | イギリス初等地理の内容構成:A scheme of work for key Stages 1 and 2 , Geography(England)の検討をとおして |
| 濱本晃宏 | 地図生成プログラムにおける地図投影法の類型と選択可能性:小縮尺地図の変換機能を中心に |
| 渡邉優子 | 中学校社会科における福祉教材の開発:福祉分野への民間参入問題を中心に |
| 浅尾篤哉 | 三浦参玄洞の人間観と国家観:初期水平運動と真宗信仰の視点から |
|---|---|
| 阿部健志 | アメリカ社会科におけるサービスラーニングの実践形態:NCSS「BUILDING BRIDGES」の実践例を手がかりに |
| 石川照子 | 高校公民科における学校設定科目「環境問題研究」のカリキュラム設計:社会問題研究としての環境学習 |
| 井戸垣忠男 | 子どもの追究活動を育てる小学校社会科指導法:有田和正氏のネタ活用の授業を手がかりに |
| 大牟田孝夫 | 規制緩和による米市場の多様化に着目した米作農業学習:小学校第5学年「稲作」を事例として |
| 加藤有悟 | 子どもがする社会科学研究としての社会科授業設計:中学校地理的分野「矢作川流域」の開発 |
| 栗原邦広 | 学習基地としての社会科Web教科書の開発:小学校第5学年教科書を手がかりにして |
| 小林学 | 中国レイ陽平原の自然環境と稲作の起源 |
| 佐藤明広 | 明治末期の新聞における対朝鮮観の形成に関する研究:大阪毎日,大阪朝日,東京日日,国民,万朝報各新聞社の閔妃虐殺,乙巳条約,ハーグ密使事件に関する報道を中心として |
| 下村隆之 | オーストラリアにおけるマイノリティ教育の実証的研究:アボリジニーを事例として |
| 泰井茂樹 | 東大寺領播磨国大部荘における在地動向と荘経営:鎌倉・南北朝時代を中心として |
| 高田聡 | 学びの意味を追究する小学校歴史学習の研究:課題化的比較史の手法を手がかりに |
| 高間裕策 | イギリスの小学校における地図指導の系統:地図教科書の分析を通して |
| 谷口康治 | 「移動と交流」に着目した世界史教育内容開発:近代における世界の一体化を事例にして |
| 長澤靖典 | 清末内蒙古における官辧墾務事業と西路墾務公司事件について |
| 永野裕一 | スキーマ理論およびメタ認知を活かした社会科授業設計:中学校地理的分野「身近な地域」を事例として |
| 西田哲士 | 中世兵庫津における関支配の展開 |
| 橋本誠司 | 革田村・夙村の研究 |
| 福本良之 | 超低出生体重児の親のライフヒストリーに関する社会学的研究:「困難」の分析を中心に |
| 藤川由香里 | 若者におけるコミュニケーション手段の対人関係に及ぼす影響に関する一考察:中学生の移動電話利用を中心に |
| 藤原正治 | 「地域の特色」をとらえる視点と方法:地理的分野における「地域の規模に応じた調査」を事例にして |
| 溝口潤一郎 | ベッドタウン型住宅地からポスト・サバーブへの転換に関する社会学的研究:京都府八幡市の事例を中心に |
| 蓑輪貴治 | 福島県矢の原湿原におけるモンスーン変動の復元 |
| 山本清之 | 多文化時代の世界史教育:地域から見た世界史カリキュラムの開発 |
| 秋山明之 | 自らの生き方とつながる異文化理解教育の創造:アイデンティティ形成方略という視点から |
|---|---|
| 伊藤聖二 | 野宿者問題に関する社会学的考察:神戸市におけるフィールドワークを中心として |
| 乾則夫 | 法意識を視点とした中学校歴史学習の研究:「中世の罪と罰」を手がかりにして |
| 今澤幸代 | 「従軍慰安婦」問題についての一考察:日韓高校生意識調査を手がかりにして |
| 上原菜穂子 | 小学校社会科における地球社会理解教育の構想:グローバル-ローカル・モデルを手がかりとして |
| 王栄 | 日本統治時代台湾における工業教育について |
| 岡本茂雄 | 住民投票制度の意義と問題点 |
| 奥村公英 | 滋賀県地場産業の地理学的研究:存続理由の考察を中心にして |
| 武田明敏 | 社会科教材研究ベースサイトの開発と利用:小学校中学年社会科を手がかりとして |
| 谷和樹 | インターネットによるWeb型マーケットの事例を取り入れた産業学習 |
| 坪内康朗 | 中学校社会科におけるポートフォリオ活用の指導と評価:公民的分野「平和主義と自衛隊」の単元を手がかりにして |
| 中尾瑞紀 | 共同体意識の変容と愛国心に関する一考察 |
| 中濱久喜 | 播磨地方における後期古墳文化の展開:特に横穴式石室の構造と変遷を中心にして |
| 中村剛之 | 1902-17年(大選挙区制)・政党活動に関する一考察:兵庫県を中心として |
| 藤井賢二 | 日韓漁業問題の研究:李承晩ラインとは何だったのか |
| 藤井健司 | 在日韓国・朝鮮人の法的地位改善に関する一考察:在日本大韓民国民団兵庫県地方本部の活動を中心として |
| 増田英雄 | 住民自治の意識を培う中学校社会科の授業構成:公民的分野「地方自治」を手がかりにして |
| 三宅康文 | 「生活・文化」の科学的な社会認識をめざす中学校社会科の授業開発:「都市化」「生活の社会化」を視点として |
| 結城修 | 伊東氏の日向国支配の展開 |
| 和田幸司 | 播磨国部落寺院の成立と展開:近世北播磨西本願寺派を中心に |
| 和田倫寛 | 地理学的景観・生態学に視点をあてた環境教育の授業設計:小学校社会科における環境学習を想定して |
| 安達一紀 | 国民国家時代の世界史教育:アイデンティティ・差異・他者の表象 |
|---|---|
| 渥美寿彦 | 未来予測を中核とする中学校社会科の授業設計:事実認識に基づく設定型問題の追究を視点として |
| 石原純 | 「生命の質」を視点とした公民科における生命倫理問題の授業構成:熊田亘・大谷いづみ氏の公民科授業を手がかりとして |
| 大柴博之 | 小学校地域学習における科学的社会認識形成:体験・表現と知識の成長過程 |
| 荻野俊明 | 長岡文雄氏の社会科実践における学習指導活動の解明:ドナルド・ショーンの「反省的実践家」の概念を手がかりに |
| 小泉憲和 | 昭和戦前期、外務官僚の研究:重光葵の政策構想と戦略性 |
| 恋田剛彰 | 学校教育における「生と死の教育」に関する研究:生命尊重教育充実のために死を用いる必要性について |
| 提嶋信行 | 古代ギリシアにおける奴隷制に関する研究:古典期アテナイを中心として |
| 塩路良枝 | 青年期における学校不適応傾向と対人関係スタイルに関する一考察 |
| 多井中慶司 | 情報ネットワークを活用し創造性を培う社会科授業構成:周辺情報の活用を視点として |
| 高崎隆一 | 農業の技術革新を視点とした社会認識形成:中学校社会科における日米の農業の取り扱いを事例として |
| 瀧本真一 | 世界的視野に立つ小学校歴史学習 |
| 田崎洋人 | 小学校社会科における環境学習の内容構成:「資源観」「環境認識」を視点として |
| 多田清志 | 戦時下『ユタ日報』にみる在米日系人の戦争観 |
| 棚田勝幸 | 北条得宗領の支配と構造:摂津国多田荘を中心として |
| 辻定 | 社会認識の形成と創造的想像:「体験」「表現」を視点として |
| 中司廣志 | 明治前半期の新聞に見る朝鮮政策の研究:江華島事件および壬午軍乱・甲申政変時の新聞報道を通して |
| 新谷和幸 | 中世安芸・備後における浄土真宗の展開 |
| 野崎彰 | 歴史の中の子どもからせまる小学校歴史学習:中世史の内容を手がかりとして |
| 花畑一吉 | 地域からせまる昭和戦争期の学習:中学校歴史分野を事例として |
| 林信男 | 教材を視点にした教科書内容の開発:中学校社会科公民的分野「経済単元」を手がかりにして |
| 古山知己 | 企業と同和問題 |
| 前田和也 | 少年事件の報道と少年法に関する研究:少年の実名報道と少年法61条の解釈を中心に |
| 松本哲也 | 中華人民共和国における教育改革について:大躍進期から文革期を中心として |
| 水元誠致 | インターネット活用による公民科単元「地方自治」の教材開発:学習集団ネットワーク作りによる問題解決方法を視点にして |
| 三宅泰徳 | 社会科における新聞を活用した授業方略:アメリカ合衆国におけるNIE実践を手がかりにして |
| 矢田貝真一 | 韓国済州島における最終氷期の風成塵堆積とモンスーン変動 |
| 矢野徹 | 戦国大名大友氏の権力編成:玖珠郡・国東郡に於ける在地領主と大友氏 |
| 山田達夫 | 観光地化された社会における近代学校教育:インドネシア・バリ州の事例研究 |
| 祐谷瑞穂 | 現代中年女性の倫理観に関する研究:近代以降の社会倫理思想の変遷から見た女性 |
| 林泓偉 | 青少年と情報化社会に関する研究:現代中国における情報ネットワークの現状と将来 |
| 渡邉元彦 | 行政施策と地域住民の意思表示に関する社会学的研究:山陽町における意識調査を中心に |
| 足立龍彦 | 守護山名氏の権力構造 |
|---|---|
| 有吉研治 | 「モノ」教材に関する社会科授業理論の比較研究:実践者における「モノ」教材理論の形成過程を視点にして |
| 吉柳義雄 | 福岡県筑豊地区における地域振興の現状:トヨタ自動車工場進出による地域の変容 |
| 楠本健二 | 大衆文化としてのマンガ論:マンガに関する意識・行動調査を踏まえて |
| 小瀬和彦 | 社会科学的認識形成のための授業設計の理論と展開:理解説明型授業構成原理に基づく教育内容の抽出 |
| 木幡一彦 | 体験と科学との結合をはかる中学校社会科授業構成:へき地・小規模校での実践を事例として |
| 塩谷裕司 | わが国島嶼空間の変容:架橋開通に伴う瀬戸内海中部、田島・横島の地域変化を中心として |
| 鈴木覺 | 高齢化社会へ向けての税制 |
| 立石敏彦 | 中学校社会科歴史分野における図像資料活用の授業構成とカリキュラム開発:解釈内容・方法の系統性に着目して |
| 田村誠志 | 世相に視点を置いた歴史の授業構成に関する研究:中学校社会科歴史的分野における「戦後日本史」の取扱い |
| 戸村龍一 | フランス革命の授業構成に関する研究:解釈の多元性をふまえて |
| 中川洋文 | 小学校社会科授業実践における資料活用方法:社会科教育論の相違を手がかりにして |
| 中本和彦 | 社会認識形成をめざす世界地誌学習:理論を中核にした教科内容の設計 |
| 西村康幸 | 地域教材に基づく小学校高学年社会科の単元構成とその開発:地域事例活用と教材内容構成を視点にして |
| 平林和男 | 都市型社会科カリキュラム開発:自己認識と宗教認識 |
| 藤原美代子 | ベトナム中部ホイアン市の町家における中庭の研究:町並み保存をめぐる動きを通しての一考察 |
| 別井渉 | 教育個人情報の開示と子どもの人権:内申書・指導要録の開示の問題を中心に |
| 松井克行 | ホリスティック価値アプローチを基底とするグローバル教育の理論と開発:Betty A. Reardonの人権教育論を手がかりとして |
| 松下誠 | 社会認識における探究能力・技能育成の理論:中学校社会科地理的分野を事例にして |
| 松元伊知郎 | 子どもの歴史認識を深めるディベート学習のあり方:小学校社会科歴史学習を通して |
| 水田綾子 | 世界史教育におけるヨーロッパ中世史の取り扱いに関する研究:社会史的視野に立つ主題学習 |
| 矢島晃弘 | モダニティとポストモダニティにおける文化に関する一考察 |
| 山崎誠 | 中世山陰水運の展開と地域経済 |
| 山梨弘樹 | 「技術革新」「社会変容」の相互関係を視点とした産業学習の創造:自動車産業を事例とした教科内容の構成 |
| 吉井克行 | 兵庫県における最終氷期の風成塵の堆積とモンスーン変動 |
| 秋岡祥介 | 経済的リテラシーを育成する公民教育の研究:高等学校の経済学習を事例として |
|---|---|
| 阿部健 | 西洋封建制社会成立期の研究:城主支配圏の形成を中心に |
| 今城喜久男 | 発達段階に応じた小学校社会科授業のディベート活用:ディベートの目的と指導過程を手がかりに |
| 大橋勇 | 教師の利他性に関する一考察:倫理・心理学的アプローチ |
| 岡田竜也 | 学校組織存立における「信頼の論理」に関する一考察:J.W.マイヤーらのアプローチを中心に |
| 小河達之 | 代議士に関する研究 |
| 奥西功二 | 社会科における問いの発生とその成長過程 |
| 斧原孝守 | 雲南少数民族教育史研究 |
| 香川祐理子 | 平安初期政治の構造:良房政権期を中心として |
| 笠木勝範 | 日本亡命後における梁啓超の思想的変遷について |
| 川内啓詩 | 小学校社会科歴史学習における資料活用能力の育成と評価 |
| 北智裕 | 市川流域における水利調整と流域管理 |
| 霧島一浩 | 豊臣政権下の島津領国 |
| 志賀照明 | 在日外国人の定住過程にともなうエスニシティ変容に関する研究:神戸市のベトナム人を事例として |
| 島田龍太 | 社会史の方法を生かした歴史教育の研究:社会結合を視点として |
| 下村功次 | 隋・唐代科挙と切韻系韻書との関係 |
| 杉浦弘毅 | トルコ,アナトリア高原,トゥズ湖沿岸の地形発達 |
| 鈴木宏 | 太平洋西岸,偏西風帯における風成塵の供給源と古風系 |
| 須本良夫 | 視点,創造的思考を鍵概念とする社会認識・市民的資質の形成 |
| 陶山浩 | 文化変容の視点に基づいた歴史教育の研究:高等学校「日本史」を事例として |
| 武田寿博 | 合理的意思決定能力の育成と消費者教育 |
| 田中秀子 | 日本近世の都市社会 |
| 丹後靖史 | 小学校社会科における表現力の育成と評価:作文指導を手がかりに |
| 津留一郎 | 社会認識における「理解」と「説明」の結合:「理解」・「説明」の深化過程を通して |
| 得能弘一 | 中世における瀬戸内海海賊衆の展開:三島村上 氏を中心として |
| 早川寿樹 | 中世伊勢湾をめぐる太平洋海運の展開 |
| 泥谷智明 | 南四国の海洋性観光の地理学的研究 |
| 平岡郁子 | 相反・共存感情(Ambivalence)としての「愛」と「憎」について:異性愛を中心として |
| 藤澤國治 | 長岡文雄氏の社会科教育実践史研究:問題解決学習の理論構築過程の解明 |
| 藤田健一 | 兵庫県地場産業の地理学的研究 |
| 本間達也 | 太平洋島嶼地域の地理学的研究:パラオ共和国(ベラウ)を事例として |
| 松岡靖 | インターネット利用による社会科のコラボレーション的教材開発:小5伝統産業を事例として |
| 水谷康夫 | 姫路市のある定時制高校の教育実践に関する教育:教育の原点を求めて |
| 森井裕史 | フィリピン・ネグロス島におけるバナナの経済地理学研究 |
| 森田卓 | 同和行政・同和対策事業の現状と課題:政治史的考察を中心に |
| 山口偉一 | 少子高齢社会における市民的資質の育成:「共生と経済的合理性」,「グローバル・スタンダード」の視点から |
| 横井香織 | 台湾における「南洋」調査と南進政策 |
| 劉恵 | 近代中国における社会認識教育の歴史:ドルトン・プランの導入過程を中心として |
| 石原一則 | 小学校社会科における地域学習の授業設計:社会変動にともなう個・集合体の価値対立の変化を視点として |
|---|---|
| 一瀬裕之 | 戦國趙・武靈王政権の構造について |
| 伊藤正志 | 個性的社会認識と科学的思考能力を育てる複線型授業設計 |
| 井之上良一 | 社会科歴史教育と神話学習 |
| 王圓 | 在日華僑青少年の社会意識とその変容に関する研究:青少年の民族アイデンティティの持続性を中心として |
| 大川武彦 | 社会科授業における討論の意義と活用方法に関する研究:小学校における活用を意図して |
| 蔭木原洋 | 洪武帝期・対日外交政策考:明使仲猷祖闡・無逸克勤来朝を中心に |
| 金田正美 | グアテマラにおけるコーヒー生産の地理学的研究 |
| 川本吉則 | 戦前における児童融和教育の成果と限界 |
| 國枝義隆 | 共生する社会における国際理解教育としての在日外国人教育:社会科地理的分野における教材開発と授業設計 |
| 小林隆 | 地球市民的資質形成を意図する「参加型体験学習」の構造と実践:ユニセフの「開発のための教育」をてがかりにして |
| 近藤雅裕 | 兵庫県における満蒙開拓青少年義勇軍と教育 |
| 鈴木裕治 | 敦賀、中池見湿原における風成塵の堆積と古環境 |
| 塚田良子 | 教科書疑獄事件と文部省廃止論 |
| 津田博 | 兵庫県議会制度の成立に関する一考察 |
| 露無啓介 | 後漢末・三国時代、青州兵についての史的考察 |
| 中井修 | イギリスにおける「全国カリキュラム・地理(Geography in the National Curriculum)」の成立過程と展開 |
| 永添祥多 | 明治中期・中学校設立問題と政治的背景:大分県を例として |
| 西尾正仁 | 近世村落成立期における家伝承の研究:丹波国桑田郡山国郷の事例 |
| 樋口博子 | 生活科カリキュラム編成の分析と開発 |
| 松下敏郎 | 主体的な追究を意図する小学校社会科の学習指導:観察・調査活動を手がかりに |
| 松島康之 | 社会認識形成におけるイメージ的認識の理論と実際 |
| 皆木秀司 | 細川氏一門の守護支配と京兆家 |
| 三宅修 | 中学校社会科における環境教育に関する教材開発 |
| 宮地昌一 | 「社会問題探求としての社会科論」 |
| 山本伸夫 | 織田政権の領国支配体制:近江・若狭・越前を中心として |
| 横山一利 | 社会科事例学習における社会認識形成と評価 |
| 石亀伸弥 | 社会科授業におけるディベートの活用方法: 論題と論議過程を視点にして |
|---|---|
| 上谷繁之 | 貧困問題への取組みの過程における河上肇の思想の変化: 大正期の研究活動を中心として |
| 江口忠宏 | 高校生の無気力に関する社会学的一考察:儀礼主義と冷却理論を中心として |
| 大木辰史 | 兵庫県・翼賛選挙下の政治構造 |
| 大谷隆 | 国際理解教育における小学校社会科の授業構成:グローバル的視野の育成を目指して |
| 笠木秀樹 | 余暇活動における地域スポーツ行動とスポーツ施設の研究:津山市を中心として |
| 加藤孝之 | アメリカ大統領のリーダーシップについて |
| 亀井章 | 初期イタリア・ルネサンスの研究:寡頭政期フィレンツェを中心として |
| 児玉典彦 | 自己学習能力の育成を意図する中学校社会科の授業方略:附属中学校の実践を手がかりにして |
| 後藤美利 | 個を生かす社会科授業の分析と設計:個の体験的知識・価値観を重視する視点から |
| 小西正晃 | 金融政策をめぐる諸問題 |
| 近藤圭亮 | 明治前期における地主家憲の研究 |
| 朱阿根 | 清末中国人日本留学生の文化活動:翻訳・出版活動を中心に |
| 杉山晋一 | 南北問題と環境問題の接点に焦点をあてた社会科の内容構成 |
| 竹部嘉一 | シラス台地の地形改変による海岸地形の変遷 |
| 田中豊之 | 滋賀県における大規模宅地開発の展開 |
| 堤和幸 | 清末、広東の米穀需給構造と潮州商人の活動 |
| 東郷孝仁 | 西系紅巾考:元末の政治と彭瑩玉・徐壽輝 |
| 中原道宣 | 地理学の研究成果を生かした授業内容の革新:地理学の五大テーマを視点として |
| 中村健 | 中学校におけるスクールカウンセラーの活用に関する実証的研究:教師と臨床心理士の意識調査を中心に |
| 成田勝俊 | 荘園公領制の形成とその特質:保を中心として |
| 乗田政長 | 「多元的価値に基づいた世界史構成の研究」:高等学校「世界史」カリキュラム論の視点から |
| 福永英雄 | 物象化とhabitus-pratiqueに関する一考察 |
| 伏見健 | ハイパーカードを活用した高校日本史歴史教材の開発:鎌倉時代を例に |
| 前重幸美 | 「分業」を視点とした社会科教科内容の検討と授業設計:農業を事例として |
| 松田薫 | 地域教材を活用した社会科のカリキュラムと授業の開発:加古川地域における独立型教材を手がかりにして |
| 森下律子 | 婦人運動団体にみる売春問題:売春防止法成立前後を中心にして |
| 柳井義孝 | 戦後教科書制度の変遷:教科書法案を中心に |
| 山崎明宏 | 社会科における市民的資質形成の理論と実践:経済的自立を支える概念を中心として |
| 山西康之 | 幕末・維新期被差別部落の復権闘争:但馬国の事例研究 |
| 山本裕二 | 社会科教育における歴史的景観の取扱いに関する研究:小学校社会科を事例として |
| 山本善幸 | 兵庫県瀬戸内海沿岸漁村の研究 |
| 山脇多代 | 1968-69における学園紛争の政治史的研究 |
| 飯沼博一 | 春川常緑会事件研究:常緑会事件訊門記録をとおして |
|---|---|
| 伊賀なほゑ | 近世在郷町の構造と展開:播磨美嚢郡三木町を中心として |
| 江口孝之 | 世界史教育における「戦争」理論の探求 |
| 大重満明 | 島津重豪の藩政改革の研究:幕府中枢との関連において |
| 大橋洋二 | 小学校社会科における価値判断能力の育成:教科書及び授業実践における「論題」の分析を通して |
| 小倉礼 | 室町期播磨における守護支配機構の研究 |
| 梶村敏 | 世界の自明性(Selbstverstandlichkeit)について:フッサール現象学の地平概念による一考察 |
| 加藤正宏 | 中華人民共和国における愛国主義教育の変遷:「甲午中日戦争」関係の教科書記述分析を中心に |
| 城戸茂 | 中学校社会科における地域学習の授業設計:社会認識の概念装置形成をめざして |
| 木戸恒徳 | 生きんとする意志の客観化 |
| 久保哲成 | ダム建設と水利調整:加古川水系・川代ダム直下流域を対象として |
| 久保雅英 | 社会認識形成過程における関心・意欲の関与およびその評価 |
| 隈元理人 | 「技術革新」「地域形成」の因果関係を視点とした社会科授業内容の検討および授業設計 |
| 佐藤健 | 身近な地域の「物質循環」に視点をあてた環境教育の創造 |
| 佐藤廣 | 歴史教育における絵画史料の活用に関する研究 |
| 四宮章裕 | 外交官・重光葵の研究:対支新政策を中心として |
| 多久島文樹 | 中学校社会科授業における教材構成の目的と方法:公民的分野の授業事例をてがかりにして |
| 冨永六郎 | 幕末期広島藩の政治過程:国事周旋と政治選択 |
| 内藤英一 | 兵庫県佐治川流域における水利調整の展開 |
| 中西正和 | 大化前代の「筑紫大宰」についての考察 |
| 平田伸幸 | リーガルマインドを育成する社会科授業構成の研究:中学校社会科公民的分野を事例にして |
| 藤野剛志 | 資源管理と人間環境系に関する研究:ブルース・ミッチェルの地理学と資源分析に基づいて |
| 堀口俊雄 | 自己評価システムを組み込んだ社会科の授業設計:自己評価例の分析を通して |
| 室谷茂 | 政治的意図による地名命名の研究:その背景と影響について |
| 柳精司 | 山陰東部と北陸西部における最終間氷期以降の広域風成塵の堆積量と古環境 |
| 山田榮 | 明治初年・解放令反対一揆:いわゆる「播但一揆」を中心に |
| 山之口公一 | 対外硬運動と対韓政策の一側面:黒龍会・内田良平とその周辺 |
| 吉崎幸男 | 社会科授業における児童の主体化を意図する体験活動の活用:社会科の初志をつらぬく会の授業実践を手がかりにして |
| 李景子 | 現代中高生の社会意識に関する研究:日本・香港・中国を事例として |
| 渡口洋 | ハンガリー大平原の研究 |
| 幾島雅裕 | 地域社会の変容と生活史:広島県佐伯郡大柿町大君の事例をとおして |
|---|---|
| 石井清文 | 鎌倉中期幕政史に関する考察:泰時・経時執権期をめぐって |
| 伊平充宏 | 明治・大正期北遠地方における企業進出と地域の対応:王子製紙気田工場の事例を通して |
| 岩瀬康幸 | 歴史教育における「倒叙法」に関する研究 |
| 大久保哲史 | 社会認識形成の論理と目標・内容・方法・評価のシステム化をめざす理論と実際 |
| 岡崎均 | 社会科ハイパーメディア教材の設計理論と開発:小5自動車工業を事例として |
| 岡本昌浩 | 開発と保全の接点を探る地域経済学習:第4学年「開発単元」「各地のくらし単元」を例に |
| 川上周二 | 考古学の方法を生かした歴史授業構成の研究:中学校社会科歴史的分野「古代の日本」を事例として |
| 栗栖卓男 | 一向一揆の授業構成に関する研究:公民的資質を育成する歴史学習 |
| 小林英二 | 社会科における未来予測学習と創造性の育成:環境教材を事例として |
| 小南浩一 | 大正デモクラシーと河合義一:東播磨高砂地方を中心として |
| 酒井喜八郎 | 食を主題とする社会科授業の設計:生活文化教材の科学化をめざして |
| 坂田恵一 | 都市再開発事業と財産権の保護:宝塚市と川西市の駅前再開発の事例を中心に |
| 芝田俊哉 | 占領史及び地域史の視点からの農地改革 |
| 竹中亮造 | 台湾の皇民化と国家神道 |
| 武林淳 | 地方都市における祭りの研究:鳥取・米子・松江の祭りを中心として |
| 田中美代 | 医業広告の自由と規制:医療消費者の権利と表現の自由の問題として |
| 田平篤史 | 明治初年鹿児島藩における桂久武の研究 |
| 林康男 | 昭電事件とGHQ |
| 原田京子 | 丹波国被差別部落「別村」闘争の研究 |
| 藤本百男 | 明治21ー23年・兵庫県の政党活動に関する一考察 |
| 藤原健剛 | 古ゲルマンの社会状態に関する研究:Tacitus、Germaniaを中心として |
| 前田茂 | 都市経営的コミュニティ施策に関する一考察:神戸市の地域活動助成の意味に着目して |
| 松尾光雄 | 他者の行為理解を深める地歴科地理の理論と授業構成:共感を手がかりとした社会認識形成 |
| 森泰三 | 都市域における人口高齢化の空間的組織 |
| 矢野健治 | 小学校社会科ビデオ教材の活用目的と構成形態 |
| 山口真吾 | 小学校社会科授業における発問の性格とその活用:教授・学習活動と授業過程の関連をてがかりにして |
| 山本真宏 | 広島県・第一回衆議院議員選挙に関する一考察 |
| 吉田幸嗣 | 旧韓末(1897~1910)の日本の教育政策とそれへの抵抗 |
| 秋元直樹 | 「体験」にもとづく歴史認識形成論 |
|---|---|
| 足立年樹 | 西宮市域の都市開発に伴う大規模地形改変 |
| 稲木実 | 古代日本における太陽信仰と宮廷祭祀 |
| 稲山安生 | ブルネイにおけるブミプトラ政策の展開構造 |
| 猪瀬洋一 | プラトンの知識論:『テアイテトス』(184-186)における感覚知識説 |
| 臼木智昭 | 公共サービスの地域的分配構造に関する実証的研究 |
| 笠島修 | 播州久米皮田村の研究:非「皮田村」的部落の事例的考察 |
| 川越正博 | 中世興福寺における公人の存在形態 |
| 河村克典 | 治水事業と洪水絵図:佐波川流域における近世洪水絵図の地域分析を中心として |
| 寒川忠俊 | 都市域の拡大と交通システムの変貌:京阪神都市圏を例として |
| 久保正彦 | 平和研究の視点からみた戦後日本の教育政策:昭和20年代・30年代を中心として |
| 熊木宏 | 「生活者」の視点からの社会科授業内容の検討及び授業設計:第4学年「水道」単元を事例にして |
| 白神千曉 | 奈良県大正村小学校差別事件の研究 |
| 竹林康司 | 社会科における基本的内容に関する個別学習の授業実践とその改善:小学校5年「産業学習」の実践事例を手がかりとして |
| 田中修一 | 情報化に対応する中学校社会科学習ソフトウェア活用の実践とその改善 |
| 田淵修 | 小学校社会科学習における調査活動と概念形成 |
| 東郷達夫 | わが国労働時間の国際比較研究 |
| 中北義久 | 日本人と宗教:キリスト教の土着化を中心に |
| 中野照雄 | 『歴史地理教育』における低学年社会科授業実践の変遷:生活科授業実践との関連を意図して |
| 二井正浩 | 現代史の授業構成に関する研究:地球システム論を手がかりにして |
| 西端幸信 | 文化史学習の方法論的考察:中学校社会科歴史を事例として |
| 野村秀樹 | 歴史教材としての「技術」に関する研究:小学校歴史学習を事例として |
| 古田望 | 社会科におけるイメージと社会認識形成:人物への共感を通して |
| 逸見優一 | 姫路平野の地形発達史 |
| 水田佳正 | 地域経済の再生と地域生活:兵庫県朝来郡生野町の事例より |
| 籔元晶 | 古代における祈雨について |
| 山根秀明 | 幕末維新期かわた村名望家の存在形態:因幡国八東郡南下村小谷家の場合 |
| 吉岡保 | 明治前期北播における身分学校の研究:多可郡中町東嶺小学校の場合 |
| 米澤伯典 | 石英粒SEM分析による鳥取砂丘の形成に関する研究 |
| 上谷浩一 | 中国古代史上における地方行政の諸問題:後漢時代の郡太守制を中心にして |
|---|---|
| 梅田斉 | 伊勢国被差別部落の研究:近世後期明治維新期を中心に |
| 大畑健実 | 小学校社会科教育ソフトウェアの基本的性格とその活用実践:コンピュータ活用の授業実践事例を手がかりとして |
| 小川孝 | 比喩の働きを活用した社会認識形成論と社会科授業設計 |
| 小河文雄 | 工業化の進展と河川水利の調整:兵庫県高砂市域を事例として |
| 小原健 | 薩摩藩郷士と西南戦争 |
| 葛西攻 | 青森県屏風山砂丘の形成 |
| 片岡正光 | 井堰構築と水利慣行:近世における加古川流域を例として |
| 木下昭次郎 | 「幕末・維新期における柳河藩の政治的動向」:家老立花壱岐を中心として |
| 小泉邦彦 | 中学校の地理教育における地誌的内容の構成論と実践例の分析 |
| 佐々木俊彦 | 宗教改革期における寛容思想に関する研究:カルヴァンとカステリヨンを中心に |
| 塩見良三 | 西舞鶴平野の古環境 |
| 仲容生 | 日本の捕鯨地域史の研究:紀州太地を中心として |
| 西畑俊昭 | 入浜塩田における「一軒前」経営の成立とその限界:安芸国竹原塩田の「分け浜」を中心として |
| 畠中誠 | 近代におけるスペインの海上支配権に関する研究 |
| 原堅 | 生活科授業実践における基本原理とその事例分析:生活科研究推進校の授業実践を手がかりに |
| 東博晃 | 社会科授業実践における子どもの思考変容の研究:「社会科の初志をつらぬく会」地域学習の授業実践を手がかりに |
| 別府陽子 | 社会史をふまえた歴史授業構成の研究:中学校社会科歴史的分野「中世の日本」を事例として |
| 松田至功 | 圃場整備と地域農業の展開:兵庫県印南野台地を中心として |
| 松本真輝 | 近代後期農民の生活防衛意識の研究:岡山藩領備前国和気郡の場合を中心に |
| 磨矢明人 | 小学校社会科学習指導過程における指導技術の解明:大阪市小学校教育研究会社会部のVTR授業記録をてがかりに |
| 水山光春 | 環境科学・環境経済学の成果を組み込んだ環境教育の構想 |
| 溝上芳秋 | マルクスの思想研究:学位論文を中心として |
| 森本義則 | 高校生活と法:デュルケイム法理論の適用をめぐって |
| 山内正樹 | 近代イギリスの都市計画における「アメニティ」の創出過程:ハムステッド田園郊外計画を中心として |
| 山岡哲史 | 近代美作における皮多身分の支配構造 |
| 山口詳二 | 日本の労使関係 |
| 山本文彦 | 兵庫県但馬地域における大型店立地の展開構造 |
| 和田寛 | イメージによる理解と社会認識形成:「視点」研究の成果を生かして |
| 赤井由和 | 地場産業としての播州釣針工業地域の研究 |
|---|---|
| 赤木直行 | 生活科における「遊び」と認識形成 |
| 石原隆 | 会津藩の寛政改革の研究 |
| 伊藤裕康 | 現代日本の地域構造を踏まえた「日本とその諸地域」の年間指導計画と授業設計:中学校社会科地理的分野 |
| 宇野賢治 | 理科学習に関する成果を取り入れた概念探究型社会科 |
| 大谷正敏 | 都市化の進展と土地改良区の対応:兵庫県東播土地改良区を例にして |
| 岡田有弘 | 近代ドイツにおける「改革」の研究:ヴェンテルベルグを中心として |
| 尾張豊 | 消費者保護法と経済分析 |
| 勝男義行 | 近世後期かわた村経済構造の研究:播磨国宍粟郡を中心に |
| 川勝睦美 | ビルマ独立と日本 |
| 小久保義直 | 福沢諭吉の天皇観 |
| 米田豊 | 民族学の研究成果を組み込んだ社会科内容・授業設計論:中学校社会科歴史的分野を中心として |
| 佐溝理 | 播磨における稲作の起源と古環境 |
| 清水雅寛 | 近世後期綾部藩の藩政改革の研究 |
| 関藤一智 | 日本における平和運動の政治的意義:1982年の反核平和運動を中心に |
| 田原豊 | 中世九州における修験の構造と展開:豊前彦山を中心として |
| 丹後政俊 | 享保期幕府領の新田開発の研究:播州青野原新田の場合 |
| 辻本直子 | 学校事故の救済法理:損害賠償請求の法的構成を中心として |
| 所正恭 | 個人評価表を活かした生活科学習活動の評価:低学年社会科・理科における評価実践の分析を通して |
| 西尾嘉尉 | 小・中・高の歴史教科書の内容分析とその考察:日本史に関する人物・年代・地名を分析視点として |
| 橋本大治 | 「個」を生かし,認識を深める社会科授業の設計:学習者の相互作用を生かす小集団学習を通して |
| 畠中伸王 | 黄河中流域における自然環境の変遷と地形改変 |
| 藤井正和 | 我が国の所得再分配政策 |
| 豆崎章三 | 備中松山藩儒山田方谷の海外侵略論の研究 |
| 森井基容 | 中学生の社会意識の研究:義理・人情を中心にして |
| 山方純 | 溜池の多目的利用と維持管理:播州平野における事例を中心として |
| 大和道生 | アメリカ独立革命の研究 |
| 東直彦 | コーホートデータによる年齢・賃金率プロファイルの研究 |
|---|---|
| 新井宏昌 | 近世被差別部落の存在形態:播州皮多百姓の意識とその経済基盤 |
| 池永英樹 | 社会科学的視点を導入した産業学習:運輸・通信業を中心として |
| 猪野滋 | 科学的な社会認識形成をめざす社会科教科内容の構造化:内田義彦氏の経済認識のモデル化を通して |
| 植木洋一 | 兵庫県加東台地における水利開発と地域の発展 |
| 馬野範雄 | 子どもの探究的活動に基づく小学校社会科授業の改善:国立大学附属小学校の社会科授業事例を手がかりにして |
| 大津和子 | グローバル教育のカリキュラムと授業構成の新構想:社会科における地球市民的資質の育成を目指して |
| 大庭隆志 | 概念探究型社会科における人物学習の展開:「動機理解の説明モデル」を組み込んだ授業構成 |
| 沖野清治 | 近世浄土真宗の寺檀関係と講中組織:芸北地方を中心として |
| 幸田和洋 | 宋代の鉱山業 |
| 小谷康夫 | プラトンにおける探究の方法:「パイドン」(99D-102A)における「ヒュポテシスの方法」 |
| 佐藤千江子 | 日本社会党と構造改革論 |
| 澤田義宗 | 総合の考え方を生かした中学校社会科地理分野における教材開発 |
| 白石秀寛 | 地域開発に伴う地域構造と住民意識の変容:熊本県阿蘇郡西原村を事例として |
| 杉本佳雄 | 社会認識形成における探究形式の類型化に関する研究:松元清張の推理形式を視点として |
| 關浩和 | 小学校社会科における「ネタ」教材構成の方法論と授業モデルの開発:有田和正氏の実践事例を考察対象として |
| 田中東吾 | コンピュータを活用した小学校歴史的学習:子どもの思考過程を大切にした資料提示 |
| 内藤美知子 | 小学校社会科シュミレーション・ゲームにおける教材構成:アメリカ合衆国の歴史シュミレーション・ゲーム教材をてがかりとして |
| 永田智章 | マクロ政策協調の経済分析 |
| 中村文彦 | 近世新居宿の研究:宿場・関所の機能とその補完諸制度 |
| 西住徹 | 戦後日本政治史における北村徳太郎 |
| 野呂瀬秀幸 | 観光開発と農山村の再編成:八ヶ岳南麓におけるペンション立地を中心として |
| 船引規正 | 認識を深め行動をおこさせる環境教育の授業構成:ディベートを用いた学習行動 |
| 船本秀忠 | 高冷開拓地蒜山原における農業的土地利用の展開構造 |
| 松藤倫子 | 中世都市の市壁と市民意識:イタリア北・中部を中心として |
| 三宅康成 | ダム開発と水没補償:神戸市域の呑吐ダムを中心として |
| 山口勝成 | 「論語」にみられる神秘思想について |
| 山本憲令 | 知識分析を視点とした社会科授業の分析と授業モデルの展開 |
| 吉崎朗 | 共感を通して分析へいたる歴史学習システムの開発 |
| 渡邊玄 | 個人差に対応する社会科学習指導方法論に関する研究:社会科個別化学習実践事例を手がかりとして |
| 明山修 | 新古平民騒動の研究 |
|---|---|
| 朝倉隆行 | 陸軍教育制度の研究:陸軍教化隊を中心に |
| 飯沼暢康 | 小学校社会科における地域教材の構成:日本生活教育連盟の社会科授業実践をてがかりにして |
| 石飛公士 | 小学校社会科における比較学習の研究:比較思考力の系統的な育成をめざして |
| 大山治 | 問題解決学習の集団思考分析に基づく社会科授業の改善:愛教大教科教育センター所蔵「中学校社会科歴史的分野の授業記録」を手がかりにして |
| 兼本雄三 | 姫路藩寛延一揆の研究 |
| 北風公基 | フェステンガーの社会的比較過程理論の再検討:基本的仮説を中心として |
| 楠元精文 | 小学校歴史学習における「郷土」の文化遺産活用に関する一研究 |
| 甲津和寿 | 社会認識過程におけるスキーマと概念形成 |
| 酒井義仁 | 社会科教科書における学習資料の構成形態と活用方法:中学校社会科公民教科書を分析対象として |
| 角倉耕一 | 小学校社会科におけるこどもの問いの活用に関する研究 |
| 田中英二 | 地域学習における意志決定能力の育成:小学校中学年を事例にして |
| 佃達也 | 明治元年米沢藩の研究:奥羽越列藩同盟を中心として |
| 坪野賢一郎 | 紀伊半島南部の完新世における海岸地形の発達 |
| 西裏慎司 | 民間教育団体の小学校低学年社会科授業実践における学習指導方法論:社会科の初志をつらぬく会の場合 |
| 西出和弘 | 表現活動を通して考えを深める社会科授業 |
| 西村孝司 | 中世後期における代官請負制の展開:東寺領備中国新見荘の場合 |
| 藤原洋子 | 播州田安領における徴租体系の研究 |
| 南埜猛 | 兵庫県加古台地における水利事業の展開構造 |
| 村上隆勇 | 青函トンネルの経済効果 |
| 森本俊一 | 所謂「帷幄上奏権」に関する一考察:吉野作造を中心として |
| 安本和由 | 近世中期における外様小藩の藩政改革:備中国岡田藩の場合 |
| 矢田和宏 | 算数科の方法を取り入れた概念探究型社会科 |
| 山中賢司 | 社会認識形成における比較法のはたらき |
| 吉村純三 | 小学校社会科における教育技術の学習方法論的考察:「教育技術の法則化」の事例を手がかりにして |
| 渡邉美千代 | 歴史学習における「地球史」の取り扱いに関する研究 |
| 青木宗昭 | 萩生徂徠の経世論 |
|---|---|
| 浅井啓言 | 中学校社会科公民的分野の学習指導方法論とその改革 |
| 新直之 | 靖国問題に関する一考察:政治的アプローチを中心にして |
| 幾田喜憲 | 児童の歴史意識をふまえた授業構成の研究 |
| 石田至宏 | 小学校歴史的学習における人物の取扱いに関する研究 |
| 大迫利久 | 中学校社会科歴史的分野における資料活用についての一考察 |
| 大矢幸雄 | 松江・米子都市圏における商業活動の研究 |
| 隠岐鉄雄 | 国学における幽冥観の系譜:宣長、篤胤から柳田国男へ |
| 甲斐勝 | 王陽明思想の一考察:「戒慎恐懼」の説をめぐって |
| 河島敏文 | 学級適応に関する社会心理学的研究 |
| 齋藤尚文 | 社会科授業過程における比喩的思考と概念形成 |
| 坂本満 | 善に関するカントのモラル・センス批判について:シャフツベリーとの関連から |
| 佐々木博司 | 資料批判を視点とした小学校社会科授業の分析と構成 |
| 三田耕一郎 | 人権としての環境権 |
| 下川仁夫 | 日明交渉史の研究:洪武・永楽帝治世下における冊封関係をめぐって |
| 鈴木敏雄 | 旧制中等学校における前史的社会科の教科教育学的考察 |
| 鈴木直樹 | 中学校歴史的分野における「郷土」学習の視点と方法 |
| 高津光彦 | 元禄期藩営新田の研究:備前国幸島新田の場合 |
| 田尻由朗 | 小学校社会科放送学習における教授方略 |
| 辰田芳雄 | 14・5世紀東寺領丹波国大山荘における支配と在地動向 |
| 千田健一 | 農村社会における家族構造とその変容に関する一考察:宮城県栗駒町栗原沖部落を事例として |
| 中島永至 | 民間教育団体における社会科授業実践の展開と課題:「歴史地理教育」の小学校授業実践事例を手がかりにして |
| 長島一浩 | 律令国家解体期における文人貴族の動向 |
| 中田正浩 | 中学校地理教科書の分析とカリキュラム構成:科学的な社会認識形成をめざして |
| 羽賀公彦 | 愛媛県銅山川の分水と地域の発展 |
| 藤井一亮 | ソクラテスの正義論:「弁明」と「クリトン」を中心として |
| 矢追賢次 | 過疎地域における村落生活に関する研究:兵庫県生野町黒川区を事例として |
| 横山健二 | 社会認識形成過程の階層的構造を視点とした評価の研究 |
| 安楽浩平 | 小学校低学年における社会認識形成を中核とした総合学習の研究 |
|---|---|
| 飯田精一 | ダム開発と水利調整:兵庫県東条川流域の場合 |
| 飯田誠一郎 | 最近の兼業農村地帯での商品化の深化と村落社会の変容:兵庫県加東郡社町下久米部落鹿野最寄りを事例として |
| 池田忠 | 小学校における地図作成・読図能力の育成過程に関する研究 |
| 伊藤真史 | 宋代市易法について |
| 今村巖 | 薩摩藩天保改革の研究:薩摩藩糖業政策と徳之島島民の対応 |
| 岩見英信 | 宋代商税制度新考 |
| 恵津森義行 | 中世東国における熊野先達の存在形態 |
| 加藤豊 | 戊辰戦争期における桑名藩の研究:恭順派と抗戦派の動向を中心に |
| 川崎二三雄 | 探究に基づく社会科教授メディアの構成:ホルト・データーバンク・システム社会科の「アメリカ史についての探究」をてがかりとして |
| 木原正和 | 社会科における評価問題の内容及び作成方法に関する研究:比較法を視点にして |
| 児玉祥一 | 高校「日本史」における主題学習の研究:主題選定の観点を中心に |
| 小山邦將 | NNW指標の計測:倉敷市と鳥取市の比較 |
| 坂田仁志 | 朝鮮通信使聘礼改変の研究 |
| 佐藤章 | 社会的問題場面における意志決定と行為過程の研究 |
| 佐藤寿輝 | 「わかる」ことをめざす社会科授業の構想:検証過程を中心として |
| 鈴木啓史 | 小学校低学年における教育課程と社会科学習指導の改革:社会科を中心とした合科・総合学習の実践を手がかりにして |
| 高橋芳宏 | 宋代市舶司貿易の研究 |
| 長野代志美 | 中学校社会科における教科課程の変遷と単元構成の原理 |
| 照屋建 | 沖縄の戦後八重山開拓とその村落構造:石垣市星野部落を事例として |
| 豊嶌慎司 | 幕末・維新期の農兵隊の研究:豊前小倉藩の場合 |
| 花木正彦 | 現代社会における小・中学生の自殺:社会学的一考察 |
| 松村喬 | ルソー研究:ルソーにおける政治と教育の交錯 |
| 峯岸由治 | 「地域に根ざす社会科」実践における授業理論:兵庫県日高町立府中小学校の場合 |
| 森義勝 | 社会科カリキュラムの編成原理に関する研究 |
| 矢野真也 | 旱ばつ地帯の水利構造:兵庫県飯盛野疎水地域を中心として |
| 池田芳和 | 児童の基本的認識を組み込んだ社会科教育の構想:日本基層文化に見られる認識構造を視点にして |
|---|---|
| 石川律子 | アーバニゼイションと社会科教育:広島市域における児童の実態を中心に |
| 稲生淳 | 近代イギリスにおける海上支配権の起源に関する研究:J.ホーキンズとF.ドレークの活動を中心として |
| 太田久 | 歴史教育の目的論に関する研究:わが国近代以降を対象として |
| 大野敦司 | 中学歴史的分野における「生活文化」学習の視点と方法 |
| 大原政代 | 播磨における尊王思想家の存在形態:河野鉄兜の交友関係を中心に |
| 加藤武行 | 地理学の概念と方法論からみた高校地理教育の体系化 |
| 櫻井治夫 | 後漢豪族の農業経営:後漢崔寔の「四民月令」を中心として |
| 佐藤正一郎 | 授業成立条件の一考察:歴史授業の実践を通して子どもの変容をさぐる |
| 末吉良治 | 沖縄南部石灰岩地域の湧水に関する地理学的研究 |
| 高松武司 | 明治期における淡河川・山田川疎水事業の展開過程 |
| 田崎一彦 | ブーバーにおける対話的思惟について:我-汝を中心に |
| 堤豊 | 社会科事例学習における社会認識形成の論理と評価方法 |
| 西川敏之 | 授業料クーポン制の検討 |
| 藤原尚幸 | スコットランド歴史学派の成立 |
| 麓純雄 | 我が国における近世社会系教育の特質と近代教育への影響に関する一考察 |
| 古田真隆 | 近世関東河川水運の構造と展開:鬼怒川・板戸河岸を中心に |
| 益田啓三 | 「史記」の基礎的研究:司馬遷と「客」論 |
| 松澤八千代 | サルトル哲学研究:「存在と無」を中心に |
| 宮城能彦 | 沖縄本島南部農村の構造的特質:東風平町世名城の「門中」を中心に |
| 宮地泉 | 近代朝鮮における儒学者の一動向:義兵将崔益鉉を中心にして |
| 山中秀郎 | 社会科学習における「問題」の成立に関する一考察:「問い」の誘発を中心にして |
| 阿部俊彦 | 大庄屋制度の史的研究:地方支配機能を中心として |
|---|---|
| 池田寿仲 | 加古川左岸台地における灌漑水利の研究 |
| 石川芳己 | 自由民権家法貴発の研究:明治12年「国安論」事件を中心として |
| 石盛正純 | 明代嘉靖期の倭寇について:その背景と王直を中心に |
| 和泉正治 | 社会認識形成をめざす地域学習の構想:四年生「上・下水道」単元を事例として |
| 市村泰隆 | 近世港町の商業機能に関する研究:播州高砂湊の場合について |
| 今中孝実 | E.フロムの人道主義的倫理学の研究:疎外克服の可能性 |
| 上井加寿子 | 社会諸科学の分析視点・分析方法を育成する社会科の研究 |
| 内田和子 | 我が国における遊水地の地理学的研究 |
| 遠藤利明 | 社会科授業における児童の自己評価に関する一考察 |
| 岡崎健 | 近代日本における社会事業家留岡幸助の研究 |
| 沖田孝夫 | 社会科における概念形成に関する評価研究 |
| 勝俣得男 | 幕藩体制下の災害復旧の研究:宝永の富士噴火と駿河国御厨領の動向 |
| 加茂幸男 | 近世における皮革生産・流通の研究:姫路藩領高木村を中心として |
| 工藤護 | 中学校社会科歴史分野における人間の取扱いについての研究:戦後の歴史教育に関する二つの論争を中心に |
| 佐伯健次 | 小学校社会科における学習の個性化についての研究 |
| 設樂富男 | 公民(政・経・社)的分野における目標の変遷に関する研究 |
| 志村益司 | 近世後期における譜代小藩の藩政改革:駿河国田中藩の天保改革の場合 |
| 進木富夫 | 山鹿素行の教育思想研究 |
| 杉村啓治 | 美濃国裏木曽三箇村の研究:尾張藩林政改革との関連において |
| 瀧常晴 | 社会認識形成における「問い」のはたらき:問題把握過程・検証過程を中心にして |
| 田原哲夫 | 小学校社会科学習における地域教材の開発:開発視点を中心として |
| 田渕孝正 | シンガポールの社会変動にともなう教育の展開 |
| 冨塚秀樹 | 明治元年における徳島藩の政治選択 |
| 西村馨 | インドにおけるカースト内解放運動の研究 |
| 丹羽孝昭 | 社会科における概念形成とイメージ形成に関する研究 |
| 橋田博臣 | 中学校地理的分野における地理的見方・考え方の育成に関する研究 |
| 花澤秀文 | 高山岩男の哲学:人と著作に関する研究 |
| 阪東本得 | 小学校社会科における「問い」の研究:問題把握過程における「問い」の内発を中心に |
| 細田恒生 | 近世後期但馬出石藩の財政問題の研究 |
| 吉村政宣 | 社会科教育における意志決定能力育成の研究 |
| 家永國廣 | 近世後期における「封建官僚」養成の研究:佐賀藩弘道館の教育を中心として |
|---|---|
| 伊崎和雄 | 中学校社会科における憲法教育に関する研究:象徴天皇の行為を中心として |
| 石上昌弘 | 宋代の官栄出版事業 |
| 伊藤善文 | 神戸市域における市街地化の地理学的研究 |
| 今村直樹 | 兵庫県内陸部の農林資源管理に関する研究 |
| 今村裕昭 | 小学校における歴史的思考力の育成に関する研究 |
| 岩浅昭治 | 近世日朝交渉史上の朝鮮通信使:1764年の使節を中心に |
| 太田春樹 | 社会認識形成における知識・理解と思考のはたらき:小学校社会科授業記録の分析を中心として |
| 大槻雅俊 | 小学校社会科教育における関心・態度の評価に関する研究 |
| 刑部之康 | 但馬地方における酒造出稼ぎと地域農業の展開 |
| 片岡洋二 | 平田篤胤の研究:幽冥界思想を中心にして |
| 加藤正俊 | 溜池灌漑と水利秩序:兵庫県加西台地の溜池卓越地域を例として |
| 金兒利明 | 操作活動・技術を組み込んだ社会科学習の研究:小学校中学年教科書の分析を中心にして |
| 川原輝明 | 大正新教育運動期における歴史教育の研究:師範系附属小学校を中心にして |
| 菅野宏一 | 都市化地域における農業水利の変化:加古川市域の土地改良区を例として |
| 祇園全禄 | 社会認識形成の視点からみた福岡県地理教育史:「学制」頒布時から「戦時教育令」公布時まで |
| 作山雅宏 | 総合的社会認識の育成をめざす教材構成の研究:農業学習を中心として |
| 佐藤博美 | 昭和初期における歴史教育論の研究:中川一男の歴史教育論を中心として |
| 佐長健司 | 社会科授業構成に関する記号論的研究 |
| 清水雅裕 | 社会認識形成過程における思考操作の研究 |
| 武田薫 | 二宮尊徳の研究:尊徳の教育観とその実践について |
| 西野治 | 社会科学習におけるイメージ思考と概念形成 |
| 原誠治 | 小学校社会科における資料活用能力の育成に関する研究:教科書のさし絵・写真を中心にして |
| 広岡俊二 | 近世兵庫津の流通機能に関する研究:諸問屋・浜本陣の問題を中心にして |
| 藤本正博 | 幕末維新期の部落問題の研究:「解放令」と明治初期農民騒動 |
| 藤山政彦 | 知的発達段階をふまえた社会科指導:問題把握過程を中心にして |
| 藤原茂洋 | 備中における綿織物業の成立と発展:備中後月郡旧一橋領(井原市)の場合 |
| 三宅義明 | カントの歴史哲学:歴史主義克服の可能性に関する一考察 |
| 村上良典 | 佐治川流域における治水の展開に関する地理学的研究 |
| 森田敏夫 | 小学校社会科教育における認知と情意の形成についての研究 |
| 柳瀬佳子 | 中等学校に学ぶ生徒の学習意欲に関する社会学的研究:家族、友人、教師関係を中心として |
| 山下恭 | 赤穂前川浜の開発資本に関する研究:赤穂塩問屋と竜野醤油造元の結合 |
| 吉原照昌 | 社会科における憲法記述に関する研究:教師用指導書を中心にして |
|---|---|
| 天野哲孝 | 子供の社会的形成について:社会心理学的接近 |
| 後山慶晶 | 小学校社会科における態度育成とそのための授業構成 |
| 臼井英治 | 近世備中における紙漉き経営の研究 |
| 臼井光裕 | 日本古代の牧及び貢馬に関する基礎的研究:古代信濃地域史研究の一環として |
| 岡部隆 | 中学校における「郷土」教材化の研究:大堰川と人々の生活 |
| 岡部良一 | 高麗における宋及び遼との外交関係:年号・使節・儀礼を軸として |
| 木山久雄 | 地域素材の教材化とその単元構成:小学校中学年を中心として |
| 黒田明雄 | 小学校中学年の地域学習における社会認識形成の研究:瀬戸内北木島を事例として |
| 小森理臣 | 近世前期における新田開発の研究:駿河国駿東郡阿多野新田の場合 |
| 諏訪田陽三 | 日本国憲法制定過程の研究 |
| 田中嘉明 | 帝国都市コンスタンツにおける宗教改革の成立 |
| 筑波啓一 | 生活文化を中心とした地域素材の教材化 |
| 寺本蜂雄 | 児童期における社会認識形成過程の実証的研究 |
| 戸枝浩 | 旧幕臣江原素六の研究:その思想と行動の評価 |
| 西岡信吾 | 児童の社会認識過程と授業の構成:全理解を視点として |
| 西山富治雄 | 伝統的町並の形成とその産業史的研究:蝋の町・愛媛県内子町の場合 |
| 野島悟 | 小学校における文化遺産の活用に関する研究 |
| 早川求 | 地域の文化遺産と小学校の歴史教育 |
| 福永佳子 | 小学校社会科における国際理解教育の研究:グローバル教育との関連において |
| 古相伸博 | 社会科授業における問いの研究:小学校社会科授業の分析を通じて |
| 本元義明 | 小学校における人物学習の視点と方法 |
| 前田洋子 | 伝統的職業技術の現代的意義 |
| 村上るみ子 | ダム建設に伴う水没補償と環境整備:兵庫県呑吐ダムを事例とする中学校社会科教材の開発 |
| 森山義人 | 現代社会における生涯教育 |
| 安田達也 | 同和教育と社会科教育の課題:心理的差別の解消にむけて |
| 山田勝彦 | 小学校の歴史的学習における国民意識の形成 |
| 吉田正生 | 小学校社会科における「政治学」学習の研究 |
| 渡辺友文 | 家計負担における教育費:新分類による経済分析 |
| 伊藤剛 | 高橋財政の歴史的意義に関する研究:軍事費の膨張と新興財閥との関連を軸として |
|---|---|
| 碓井欣一 | 社会科における用語・概念の研究:小学校社会科教科書の分析と教材構成 |
| 大倉研二 | 日露戦時財政の歴史的役割に関する研究 |
| 尾崎功 | 地形図を通しての日本地誌学習の考察:新旧地形図の比較による探究的学習の提案 |
| 小野間正巳 | 播磨平野北東部の地形発達史 |
| 香川善平 | 三多摩地域における自由民権運動の系譜:神奈川県豪農民権家の動向を中心として |
| 柿原宗伸 | 「郷土」教材化の視点と方法 |
| 川口靖夫 | 宋代の武科挙:武官任用試験制度の運営とその実際 |
| 河野勝行 | 中国自動車道開通に伴う内陸地域の変化:高等学校社会科における地域教材の開発 |
| 木下孝 | 小学校の歴史的学習における郷土の人物 |
| 斉藤実信 | 土地改良と地域の発展:兵庫県東条川流域を例とする地域教材の開発 |
| 佐堂正義 | 社会科教育における態度の育成と評価 |
| 菖蒲谷義人 | 地図指導の構造とその展開:地図学の視点による中学校地図指導の分析を通して |
| 芹澤重義 | 社会科教育における学力の育成 |
| 田中嘉明 | 柳田民俗学の基礎研究:「一国民俗学」を対象として |
| 田村明敏 | 「悪党」問題からみた領主と農民の対応関係の分析:高野山領紀伊国荒川荘の場合 |
| 千葉憲次 | 播州織物業地域の変貌 |
| 徳岡努 | パスカルにおけるモラルの研究 |
| 中川正昭 | 小学校社会科における地域学習の構想:川がもつ教材性の開発 |
| 野崎純一 | 郷土教材の開発とその教材構成 |
| 東田充司 | 小学校社会科教育課程についての考察 |
| 平松義樹 | 児童の歴史意識の発達についての一考察 |
| 廣岡正昭 | 教育の人間化と社会化教育 |
| 松尾鉄城 | 知的発達段階を組み込んだ地図学習の構成:描図に基づく空間概念発達の分析と教材開発 |
| 水野治明 | 小学校社会科における地域学習についての研究:副読本を中心として |
| 宮崎和夫 | 中等教育不適応者の教育社会学的研究 |
| 村上孝治 | 近世社会を支えた精神文化:江戸末期の家の思想を中心として |
| 村上久幸 | 歴史的思考力の育成とその授業構成 |
| 山根明人 | 酒造業の合理化と出稼ぎ母村:丹波篠山盆地を事例として |
| 若林寛之 | 日本の近代化における新興宗教の歴史的役割と社会的機能:天理教を事例として |
学部
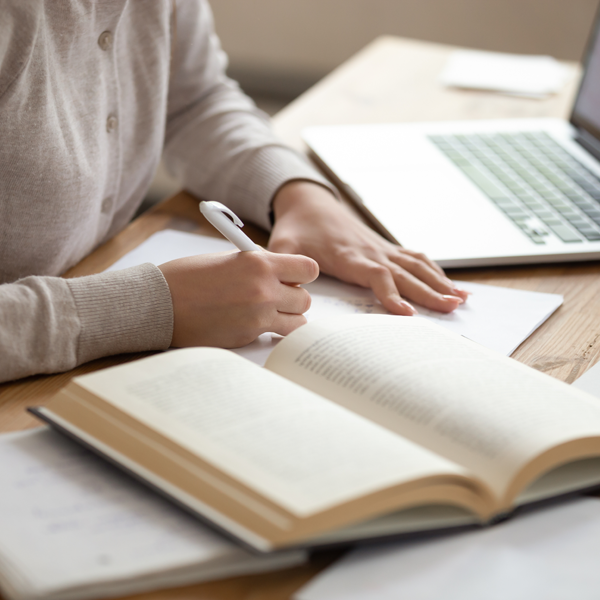
卒業論文一覧
| 井上 興 | ナチスによるユダヤ人虐殺の計画性について |
|---|---|
| 今井 敦史 | 歴史上の政策を吟味し児童の価値観形成を促す小学校歴史学習ー「異なる立場からみる刀狩り」を事例にー |
| 大土 紗苗 | 魔女と近世ヨーロッパ |
| 沖村友一朗 | 仮説吟味を通して再概念化を促す授業開発研究ー小単元「人々のくらしと路面電車の役割」を事例としてー |
| 尾﨑大一郎 | 小中連携を視野に入れた社会科授業研究 ―アニメを活用した歴史の授業づくりをもとにして― |
| 小澤 楓音 | 小学校における主権者教育の授業開発ー市民科の実践を手がかりにー |
| 葛 淳綾 | タロットカードを用いて占うとはいかなることか? |
| 小林ななみ | 民話の分布と地域特性 ~兵庫県丹波篠山市を事例として~ |
| 小紫 真拓 | 社会認識形成をめざし、文化の生成・変容を用いた小学校の歴史授業開発-「和服と洋服」を事例として- |
| 坂本 淳也 | 批判的思考力を育成する中等学校歴史授業開発 ―明治期の自由民権運動を中心にして― |
| 助岡 晴菜 | 行動経済学を教育に活かす |
| 鈴見 魁希 | 小学校社会科におけるため池学習の提案~東播磨地域のため池学習の実践例をもとに~ |
| 竹内 颯馬 | 受け継がれる優生学-ナチズムをこえて- |
| 出口 奨馬 | 持続可能な社会に向けた中学校社会科授業研究ー次世代自動車とSDGsの授業づくりをもとにしてー |
| 野口 稜太 | コンスタンティノープル1453年 |
| 樋口 陸 | これまでの道徳教育の考え方と対話を取り入れた道徳教育の考え方の対比 |
| 藤原 魁人 | 鎌倉時代における法について |
| 松本 拓海 | 規範認識能力の育成を目指す小学校歴史授業の開発ー小単元「ジェンダーから見る日本の社会構造」を事例にー |
| 森野 美晴 | ヴィルヘルム2世のドイツ帝国 |
| 山台 健太 | 中学校社会科における官民一体事業を用いたまちづくり学習の教材開発 ―プロロジス猪名川プロジェクトを対象として― |
| 池田 光佑 | 絵画史料の多解釈性に着目した小学校歴史授業の開発研究 |
|---|---|
| 井上 大幹 | 写真教材を用いた社会科教材の作成 |
| 祷 翔太 | 過疎地域におけるICT教育を用いた小学校社会科授業開発-第四学年「わたしたちのまち」を事例にして- |
| 植木 崇仁 | アメリカ南北戦争期における黒人奴隷-「地下鉄道」を手がかりにして- |
| 小田 裕貴 | これからの教育-哲学対話から見る教育- |
| 加地 尚弥 | 17世紀におけるオランダ東インド会社の繁栄-出島とバタヴィア- |
| 片山 直輝 | SDGsの視点を取り入れた小学校社会科授業開発ー総合的な学習の時間との関連をもとにしてー |
| 加茂 祐樹 | 夢前川流域における景観形成過程-治水事業と地域資源に着目して- |
| 河合 絵里菜 | 主権者教育-若者の投票率が高い国の比較- |
| 来田 勘太郎 | 魔女とヨーロッパ社会-中世後期を中心に- |
| 小林 ほの香 | 日本史探究と歴史総合をつなぐ授業の展開 |
| 佐々木 悠里 | 社会科教育におけるUDを取り入れた主題図の提案-通常学級における指導の観点から- |
| 橘 和秀 | 社会を形成する力を養う小学校社会科歴史授業開発 |
| 田辺 勇真 | 三木市における中古車販売店の分布 |
| 寺西 円 | 19世紀イギリスの階級社会-ミドル・クラスを中心に- |
| 中島 僚太 | 児童の主体性を引き出す小学校社会科授業研究 |
| 中塚 萌 | 戦後の日米関係-対米従属化への道- |
| 能島 旭希 | 根拠を明確にした仮説吟味を促す授業の開発研究 |
| 婦木 裕介 | 国勢調査と地図を用いた新たなハザードマップの作成-兵庫県丹波市を事例として- |
| 藤村 美穂 | 石橋湛山の先見性-戦後の国際関係の視点から- |
| 藤原 さくら | 政治参加への当事者意識を育てる小学校社会科授業開発-スウェーデンと日本の社会科教育の比較を通して- |
| 藤原 翔 | 戦後日本の暮らしと麺類 |
| 前野 真太朗 | ICT×思考ツールを活用した小学校社会科における授業モデルの開発-丹波立杭焼の体験型学習と関連させて- |
| 宮本 悠平 | 哲学対話におけるリフレクション |
| 三輪 一喜 | 「ドラゴンボール」は何をもって「ドラゴンボール」と呼べるか。-内容の路線変更による人気獲得と、今後の展望- |
| 矢延 香代 | 投票率に関する一考察 |
| 浅井 健太郎 | カナダ植民地政策の変遷―19世紀を中心に |
|---|---|
| 有馬 大貴 | 日本と世界が融合する「歴史総合」の授業開発―スポーツと政治の関係をもとにして― |
| 石堂 友都 | 空間認知形成と通学手段に関する地理学的研究 |
| 伊藤 渉太 | 外国人市民権について |
| 草野なつみ | エトランジェールのヨーロッパツーリズモ |
| 井上 凜太朗 | アジア・太平洋戦争の背景―満州事変から日中戦争へ― |
| 岩木 美佳 | マンガ資料を教材とした小学校社会科の授業開発―手塚治虫のマンガとミュージアムを活用して― |
| 大西 憲吾 | 時点と時代の比較を用いた授業開発研究 |
| 重永 慧太 | システムアプローチに基づく小学校社会科地域学習の授業開発―第3学年 単元「有馬温泉」の場合― |
| 住本 瑠世 | 社会主義経済について |
| 誓山 航大 | イスラム教徒がみた十字軍―「フランク人」の記憶― |
| 出水 千裕 | 立地の異同に着目した歴史授業の展開 |
| 寺田 うた | 100円ショップの経済学 |
| 中井 翔吾 | 労働者とサッカー ―イギリスにおける非労働時間の誕生― |
| 南條 功貴 | 近代ドイツの強国化―ビスマルク時代を中心に― |
| 西谷 美咲 | 教育格差について |
| 増田 瑞穂 | ユニバーサルデザインをもとにした小学校社会科授業開発―課題達成場面での振り返りを中心にして― |
| 水上 瑞紀 | ジェントルマンとスポーツ―パブリック・スクールを手がかりに― |
| 森 まどか | 高等学校における「世界史探究」の授業開発―中世ヨーロッパの紋章を読み解く学習活動を中心にして― |
| 井奥 望実 | ナチスによる政権掌握-支持基盤を手がかりに- |
|---|---|
| 太江田美奈 | 熊本城を取り巻く熊本市の景観形成 |
| 小野 太郎 | 市民的リテラシーを育成する小学校社会科のカリキュラム-お茶の水女子大学附属小学校の「市民」を事例として- |
| 上村 晶 | コミュニケーションとは何か |
| 草野なつみ | エトランジェールのヨーロッパツーリズモ |
| 桑木 将伍 | 19世紀ヨーロッパの娯楽-チェスを中心に- |
| 杉岡 広絵 | 教育格差について |
| 谷邊 弘二 | アメリカ南部の思想 |
| 春名 大誠 | 経済理論と経済政策-戦後日本の経済政策の場合- |
| 日名 優美 | バブルの発生と崩壊-1980年代後半のバブルを中心に- |
| 福本祐太朗 | オスマン帝国の第一次世界大戦参戦 |
| 増本 和希 | 長崎地方の地域資源と歴史遺産 |
| 宮本 若奈 | 政策の意図から社会の変化を認識する小学校社会科歴史学習の開発 |
| 目叶 和希 | 神社の成り立ちを巡る散策-兵庫県神戸市を中心として- |
| 下勝 和樹 | 小学校社会科における地域学習と地域教材開発 |
| 伊保 諒太 | 神風特別攻撃隊について |
|---|---|
| 岡﨑菜々瀬 | フランス革命と女性-ロラン夫人を中心に- |
| 岡崎 亘 | 日米安保条約と地位協定から見る日本とアメリカの関係 |
| 梶川 碧衣 | 歴史的思考力を育成する小学校社会科単元開発-第6学年単元「江戸時代の産業」の場合 |
| 川口 拳生 | 近代イギリスと服飾-ラウンジ・ス-ツの誕生- |
| 川村 將馬 | 魔女と社会-近世イギリスとドイツを中心に- |
| 古泉 啓悟 | 社会形成力の育成を目指した小学校社会科におけるまちづくり学習の開発 |
| 佐光 俊亮 | 伊藤博文の立憲構想-明治憲法制定過程を通じて- |
| 佐々木裕人 | デュ-イの教育論 |
| 下勝 和樹 | 町の広がりと地域の特徴 |
| 高瀬ひかり | アニメツ-リズムの経済効果 |
| 高見 佳樹 | 土地の測量と社会の中の基準点-国土と歴史に対する理解を深めるために- |
| 都藤 大誠 | 日本の過疎化の現状とその対策 |
| 寺西 達也 | 第三の波の視点による小学校社会科地域学習の授業開発 |
| 西本 賢汰 | 「文化間の摩擦」はいかにして生じるか? |
| 濱野 航暉 | 桃太郎像の変容 |
| 眞嶋 結音 | ICT活用による地理的思考力の育成のための小学校社会科授業開発-第3学年「神戸市の農家の仕事」の場合- |
| 三木 大輔 | 原発の戦後史 |
| 水野 啓太 | グリム童話と19世紀ドイツ-民族・文化・教育- |
| 宮苑 聖輝 | プラスサムの問題解決を目指した小学校社会科の授業開発-第六学年単元「よりよいくらし」の場合- |
| 夜久沙保里 | 日本の教育格差-家庭的要因を中心に- |
| 山口 麻美 | 近代イギリス社会と女性-ガヴァネスから学校教師へ- |
| 山口 桃子 | 与謝野晶子の教育観 |
| 山路 正志 | 日本の道路と自動車の現在-兵庫県の道路走行および自動車とミニカ-の遠近望- |
| 山下 敦 | 尖閣諸島をめぐる日中の対立についての一考察 |
| 宮崎 琴葉 | 旅から広がる世界の理解-南相馬からオ-ストラリアへ- |
| 生友 駿 | アニメ作品の世界にみる地理空間の再現性-京都アニメーション『氷菓』と『けいおん』の分析- |
|---|---|
| 川中 壮真 | 批判的思考力育成のための小学校社会科授業の開発-自己の思考過程を省察対象として- |
| 神部 楓凜 | 第二次世界大戦後から見る戦争犯罪と戦後保障―日本とドイツの違い― |
| 北野 敬寛 | 東播磨地域の溜池に残された伝説−現代のフィールドワークからの観照− |
| 久語 千尋 | 社会システム理論に基づく小学校社会科の授業開発−第3学年「小野市の工場の仕事(播州そろばん)」の場合− |
| 倉元 鮎紀 | 安保法制についての考察~集団的自衛権・PKO協力法を事例に~ |
| 小林 環己 | 日本の教育格差~原因と改善策を中心に~ |
| 佐藤 真衣 | イギリス食文化の断絶-18・19世紀を中心に |
| 芝地 素直 | 小中学校の防災・減災教育と溜池ハザードマップの利用―神戸市西区岩岡町を事例として― |
| 谷田 明彦 | 近代精神医学の成立-18・19世紀フランスを中心に- |
| 玉脇 健太 | 山陰海岸ジオパークの実際とガイド活動の展開―兵庫県豊岡市に着目して― |
| 戸川 大輔 | 日本近世社会史の一考察 |
| 中川 貴普 | 加西台地における水利事業―加古川西部土地改良区の事業を主として― |
| 中島 佳織 | 地域間格差~兵庫県を中心に~ |
| 原 孝拓 | 多面的視点を用いた高等学校地理授業開発~農業分野を例に~ |
| 春風 直樹 | 道と鉄道写真の展開U13122H―近現代の社会と個人の経験― |
| 廣瀬 綾香 | 異文化適応力の育成をめざした小学校社会科授業の開発-カンボジアを例に- |
| 藤浪 航大 | 対話における「聴く」ことの重要性 |
| 三谷 将慶 | 東アジア地域における貿易構造の変化-多国籍企業の役割を中心に- |
| 宮内 俊輔 | 高等学校「地理B」における比較動態地誌授業開発研究 |
| 森田 琢朗 | 18歳選挙権により問われる主権者教育 |
| 青木 一真 | 子どもの知的創造を目指した小学校社会科学習法の開発―第3学年単元「工場のしごと―ヒガシマル醤油工場―」の場合― |
|---|---|
| 足立 祥生 | イギリスのインド植民地支配 -抑圧と促進- |
| 井上 陽香 | 日本の教育格差についての一考察 |
| 大西 草平 | 「言語力」を育成する小学校社会科の授業設定 -体験活動の振り返りを中核にして- |
| 小國 彬仁 | 日・中・台における歴史教科書記述の比較検討 -十五年戦争期を中心として- |
| 小倉 蒼太郎 | 学習材としての図解式小学校社会科副読本開発研究-半完成の図を用いて- |
| 北川 淳也 | 鉄道駅の立地と周辺地域の変化-兵庫県姫路駅とはりま勝原駅に注目して- |
| 藏辻 駿 | 日米プロ野球経営の比較分析 |
| 小西 つかさ | ナチス台頭の社会的背景 -中間層を中心に- |
| 坂本 夏奈 | 稲美町における溜池の安全対策と住民イメージ |
| 杉内 翔太 | シンボリック相互作用論による小学校社会科地域学習の教材開発 -第3学年 みかん農家の仕事の場合- |
| 鈴木 孔明 | 社会の中の交通-自動車を中心として- |
| 鈴木 誠 | 満州事変期における政党と陸軍との対立 |
| 橋詰 郁弥 | 福井県の産業の現状と課題 |
| 春名 響子 | イエズス会と細川ガラシャ |
| 福井 涼太 | 論理的思考を組み込んだ小学校社会科授業の開発 -第5学年産業学習「水産業」において- |
| 松田 速斗 | 英国サッカーとフーリガニズム |
| 森岡 夕貴 | 地域活性化の方策について ~和歌山県を中心として~ |
| 山川 友貴 | 四国遍路の変容と地域の取り組み |
| 芳村 謙一郎 | 霧社事件の経緯とその真相 |
| 石原 康平 | 現代世界におけるイスラーム復興運動の意味とその教材化 |
|---|---|
| 植田 和興 | 御成敗式目の一考察 |
| 魚谷 亮太 | 清風奴隷の研究ー紅棲夢の分析を中心にー |
| 糟谷 優貴 | 知識構成型ジグソー学習を組み込んだ小学校社会科ごみ問題授業の開発 |
| 菅野 聖治 | 道徳における絵本を題材とした対話的授業について |
| 小西 椋太 | 世界的視野に立つ中学校歴史学習 |
| 島津 雄太郎 | 加東市の溜池の名称と地域のイメージ |
| 徐 波 | 女性の就労に関する一考察 |
| 住元 麻耶 | 神戸港をめぐる時間と空間—歴史的発展と地理的世界— |
| 高橋 知佳 | 思考力を高める小学校歴史授業の研究—モノ教材の活用を手がかりにして— |
| 冨田 いずみ | 沖縄県における観光と平和教育—修学旅行に注目して— |
| 中筋 菜生 | 日本統治時代台湾の羅福星事件について |
| 坂東 宏紀 | 日本における美術史教育の一考察 |
| 藤井 葉月 | 読解力育成のための小学校社会科地域学習の教材開発 |
| 藤川 武朋 | サッカーの戦術と育成に関する社会学的考察 |
| 古谷 彰梧 | 兵庫県播磨地域の古墳の現在 |
| 松尾 駿 | 鹿児島に伝わる郷中教育について |
| 南 和樹 | 兵庫県北播磨地域の飲食店の立地と学生の動向 |
| 諫山 和秀 | 日本近世前期村社会の一考察 |
|---|---|
| 市原 久士 | 独裁政治に関する社会学的考察 |
| 岩佐 琢司 | 現代ラグビーにおける戦術の社会学的研究 |
| 岩﨑 文江 | 大河ドラマの経済効果 |
| 久保田 悠生 | 経験の再構成を中核とした小学校社会科地域学習の授業開発 |
| 坂本 晃子 | 少年非行の現状と学校の取り組み |
| 城谷 卓哉 | 貨幣から迫る中学校歴史学習~「近世の改革」の教材化を事例として~ |
| 髙瀬 悠一郎 | 新幹線と新幹線網の変遷と発達 |
| 武石 美翔 | 小学校歴史学習における「卑弥呼」の教材化に関する研究 |
| 多田 美咲 | 美術館と絵画芸術-大塚国際美術館の時間と空間- |
| 立岩 千佳 | 考える力を育む対話型授業 |
| 谷水 恵太 | スポーツイベントの経済効果 |
| 富田 絢子 | 『オイディプス王』の神話論的解釈 |
| 中嶋 紘也 | 「食」を視点とした小学校社会科地域学習における教材開発研究 |
| 真砂 智博 | 小学校社会科授業における資料活用能力の育成に関する研究 |
| 柳田 敬史 | 自然環境の中の人間と教育-沈黙の春からセンス・オブ・ワンダーへ- |
| 山本 里保 | 姫路市の小学校と地域学習 |
| 横矢 咲穂 | 人物の意思決定に着目した歴史学習―源頼朝を事例として― |
| 吉永 旭希 | 小学校社会科における災害に関する学習の内容開発 |
| 渡瀬 紘生 | 近代日本にみるファシズム論に関する一考察 |
| 安藤 光紀 | 食育活動を取り入れた小学校社会科の授業実践 |
|---|---|
| 伊藤 大介 | 都市伝説に関する社会学的研究 |
| 大西 智史 | 兵庫県のスキー・スノーボード場の立地展開とレクレーション機能 |
| 垣内 薫 | 舞踊としての「よさこい」の現代的意義 |
| 神田 江梨奈 | 家庭環境と子どもに環する社会学的研究 |
| 菅野 聖治 | 道徳における絵本を題材とした対話的授業について |
| 岸本 純 | 地図を活用した産業学習(工業)における小学校社会科授業の開発 -言語力を視点として- |
| 庄治 優生 | 学校教育における生きがいの模索-フランクルの思想をもとに- |
| 宗得 千鶴 | 源義家の研究 |
| 髙見 彩菜 | 政治経済的側面からみたフランス革命 |
| 寺本 理沙 | 教育格差の現状について |
| 泊 翔介 | プロ野球の球団経営について |
| 中嶋 将史 | 近世の「城と城下町」の教材化に関する研究 -中学校歴史的分野を事例にして- |
| 鉈橋 慶之 | 構造改革と格差 小泉構造改革が国民経済に与えた影響 |
| 橋口 龍太 | 学歴が個人の地位・経済状況に与える影響 |
| 橋田 勇人 | バスケットボールにおけるチーム作りの社会学的研究 |
| 濱口 百花 | 歴史学習における「原爆投下」の授業開発 |
| 東村 拓 | 道徳教育の現状と新しい道徳教育 |
| 兵頭 千絵 | 小学校における地球儀の活用を効果的に取り入れた授業づくり |
| 藤田 和己 | 概念の習得をめざした中学校歴史授業開発-下剋上概念による戦国時代の学習- |
| 平間 由紀 | ニート、ひきこもりと家族の関係について |
| 真鍋 博光 | 子どもの知的好奇心を喚起する小学校社会科授業開発研究 |
| 宮嵜 匠 | 中学校歴史学習における地域素材の教材化-「平清盛と神戸」を事例として- |
| 森川 和輝 | スポーツとナショナリズムの社会学的考察 |
| 山本 佳奈 | 幼小連携を視点にした生活科授業開発研究 |
| 池田 悟 | 社会の中の正義 |
|---|---|
| 井上 学 | 紀伊国、隅田氏の研究 -葛原氏を中心として- |
| 井本 大喜 | サッカースタイルと戦術の社会学的研究 |
| 笠原 ちなみ | 修学旅行と個人旅行の経験と構成 |
| 岸本 佳奈子 | 中学校社会科地理分野での開発教育実践の研究 -学生団体の活動を例として- |
| 光月 美里 | 中学校社会科における外国人参政権問題の授業開発 -学習内容と現実社会を近づけるために- |
| 小松原 樹 | 九条家領播磨国 田原荘・蔭山荘に関する研究 |
| 小南 哲郎 | 戦国期孟嘗君の事績について |
| 佐藤 衣里子 | ディズニーランドの仕組みと人材育成 |
| 社領 麻美 | 少子高齢化と女性の就労 |
| 田野 珠望 | 学校ソーシャルワークの課題と展望 |
| 長井 裕志 | ラグビースタイルと戦術の社会学的研究 |
| 中津 英一郎 | 部活動における組織論 |
| 登尾 拓哉 | スポーツの経済効果 |
| 畑中 美里 | 教育格差の要因と問題点 -教育格差と経済の関係に注目して- |
| 平髙 佑太郎 | 多自然居住地域におけるまちづくりの成果と課題 ~北播磨北部地域を対象として~ |
| 増田 里奈 | ケース・スタディとしての世界史学習 -国民国家形成を事例として- |
| 矢内 陽次 | 博物館を利用した小学校社会科学習 -姫路平和資料館を事例にして- |
| 吉崎 雄貴 | 人物学習を中心とした歴史学習の授業 |
| 妙見 健太郎 | 初等社会科教育におけるGISの活用と実践 |
| 安部川 舞 | 読解力形成を視点にした小学校社会科授業の開発研究 |
|---|---|
| 今西 淳 | チームスポーツの大学部活動におけるリーダーシップのあり方 |
| 岩橋 嘉大 | 中学校社会科歴史的分野における「日露戦争」の授業作り |
| 木下 和信 | 小学校社会科における伝統・文化学習の授業開発 -播磨地域の秋祭りを例に- |
| 小西 崇久 | 企業の経営と株式価格の変動 -大手通信企業を中心に- |
| 齋藤 俊太 | 戦国期末美濃齋藤氏の研究 |
| 田嶋 要造 | 経済格差の拡大が学校教育に及ぼす影響について |
| 田畑 信人 | 中国娘娘廟の社会的諸機能 |
| 恒吉 泰行 | 「合理的意志決定能力」を育成する社会科授業の開発 -第5学年産業学習「農業」において- |
| 德田 章栄 | デジカメによる空間の認識と景観の記録 |
| 藤田 夏樹 | 黒田孝高についての研究 |
| 前川 亮太 | 中学校社会科歴史的分野の授業作り -アメリカにおける「日本人移民」について- |
| 松浦 良介 | 前田利家についての研究 |
| 森 雅恵 | 十字軍をどう教えるか -中学校社会科の教材開発- |
| 振角 正和 | 南北朝・室町初期の赤松氏について -円心 ~則祐期を中心に- |
| 吉松 拓哉 | プロサッカーの収益構造 |
| 荒木 務 | 加藤清正の研究 |
|---|---|
| 市村 真希 | ライフステージからみた観光地の選好と観光行動の実際 |
| 今田 健太郎 | 加東市におけるコンビニエンスストアの立地と展開 |
| 上田 知佳 | 読解力の育成を目指す小学校社会科授業の教材開発 |
| 牛居 弘樹 | マンガ産業の経済効果 |
| 王 亜林 | 山東省における軍閥の進出およびその影響 |
| 小川 信也 | 明治維新と大村益次郎 |
| 佐伯 千紘 | 天皇機関説事件に関する研究 |
| 高尾 悠司 | 「言語力」を育成する小学校社会科の授業設計-中学年地域学習「伝統工業」において- |
| 筒井 幸介 | 世界的視点に立つ「開国」期の研究-中学校歴史的分野の教材開発- |
| 土居 晋一郎 | 豊臣政権における石田三成の役割 |
| 成田 信太郎 | 小学校社会科における平和学習の研究-「沖縄戦」を事例として- |
| 藤田 透 | 日本の野球場の立地とその地域展開 |
| 水田 有美 | 淀殿の研究 |
| 和多田 真 | 中学校歴史学習の教材開発-ローマ帝国とキリスト教- |
| 朝川 大樹 | 第一次山東出兵と北伐 |
|---|---|
| 安達 英祐 | 中世末期における真田氏の政治的動向 |
| 奥村 敏之 | 第3セクター事業に関する一考察 |
| 加古 裕樹 | 小学校社会科における日本の領土問題の取り扱い ~竹島問題を事例にして~ |
| 木下 宗近 | 「自己責任」論をめぐる考察 |
| 佐倉 慧美 | 藤原兼子の研究 |
| 経広 佑介 | 小学校社会科歴史学習における有田和正氏の「ネタ」の性格と開発 |
| 中村 文香 | 淡路国国衙領都志郷における支配と在地動向 |
| 名越 郁乃 | 聖獣神話と人びととの関わり -神話に関する社会学的考察- |
| 藤井 優策 | 近世初期村落社会の一考察 |
| 増田 康児 | 織田政権の播磨支配 |
| 万壽本 寛之 | 地域史学習の授業開発 ~姫路市勘兵衛新田を事例として~ |
| 水田 翠 | 小学校社会科 平和学習の授業開発 |
| 村上 悠史 | 北埔事件について |
| 村木 琢磨 | 坂本龍馬暗殺事件に関する一考察 |
| 盛 佑輔 | 新選組と会津藩の正当性に関する一考察 |
| 赤田 暁俊 | 徳川慶喜と渋沢栄一 |
|---|---|
| 上山 岩根 | 「本当の自分」をめぐる言説分析 |
| 杉原 光平 | 『台湾日日新報』に見える日本・台湾の玩具について |
| 蘇楽吉瑪 | 日本の自動車産業の中国進出 |
| 武内 恵 | 東京裁判に関する一考察 |
| 平野 智子 | スポーツイベントの経済波及効果 -のじぎく兵庫国体の場合- |
| 平野 未来 | 小学校社会科における地域学習の授業設計 -合理的意志決定能力の育成をめざして- |
| 嶺山 雅代 | ベトナム人の生活と国民性 -ホーチミンの事例からの社会学的考察- |
| 宮﨑 喜子 | オランダの自然と農業の発展 |
| 湯谷 奈世 | 坂本龍馬と薩長同盟の成立 |
| 四方 佑季 | 靖国問題に関する基礎的考察 |
| 伊藤 香奈子 | 小学校社会科の教材開発―6学年「平安時代の貴族と庶民」― |
|---|---|
| 伊藤 佑輔 | 韓国併合に関する一考察 ~伊藤博文暗殺を中心として~ |
| 伊藤 友佑 | 都市内自動車交通の特性と課題 -大阪の路上駐車を中心に- |
| 丑田 麻友 | 大学の体育会系クラブ活動組織の研究 -リーダーシップの社会学的分析から- |
| 太田 美紀 | 4世紀におけるコンスタンティノープルの発展 |
| 大塚 翔 | 兵庫県におけるゴルフ場の分布と立地の研究 |
| 鴛田 麻美 | 地域からせまる小学校社会科の国際理解学習―6学年の国際単元を手がかりに― |
| 佐々木 翔一 | 大谷吉継の研究 |
| 重松 和宏 | 新撰組隊士沖田総司の伝説と逸話 |
| 高橋 進一 | 近世「被差別民」の研究 -畿内・近国を中心として- |
| 竹之熊 晶代 | 「3世紀の危機」とローマ帝国 |
| 中谷 幸弘 | 「加東郡3町の合併における成果」についての研究 |
| 元 美香子 | 神戸市内の小学校の立地と児童数の変動に関する考察 |
| 林 達雄 | 大政奉還に関する研究 |
| 春名 祥吾 | 憲法に書かれてない人権 |
| 藤田 博嗣 | 日本の安全保障 -対中関係を中心として- |
| 山本 朋 | 細川ガラシャについて |
| 岡本 明子 | 山崎断層と周辺断層について |
|---|---|
| 小谷 友紀 | 沖縄県の観光業について |
| 櫻井 与晃 | 日米交渉の研究 ~松岡洋右を中心として~ |
| 佐々木 弘二 | 満州事変と板垣征四郎 |
| 佐藤 亘 | 坂本龍馬に関する一考察 |
| 谷川 歩 | エルニーニョ現象とその影響 |
| 谷口 知子 | 日中国交正常化における歴史的考察 |
| 辻 容子 | 阿里山ツオウ族の伝統社会 |
| 坪井 亜衣 | プトレマイオス朝エジプトにおけるセラピス信仰 |
| 土井 優子 | 自我形成について |
| 松浪 軌道 | 1863-1868 土方歳三の研究 |
| 森田 紀史 | 鳥取県米子市淀江町の地形と遺跡 |
| 籔田 侑亮 | 日本の高速道路網の発達 |
| 山本 修平 | フランス革命におけるシンボルの変化について |
| 岡田 恵 | 京都の観光資源と巡回モデルコースの立案 |
|---|---|
| 木元 可南 | 加古川市中野村における坪刈の研究 |
| 栗川 由佳里 | 子どものしつけと自我の形成についての一考察 |
| 史 静 | 安楽死をめぐって「生」と「死」についての研究 |
| 杉元 真希 | 塾に対する意識に関する一考察 |
| 土屋 真平 | 関東軍特別大演習に関する研究 |
| 池 桂花 | 「満州国」における朝鮮人の生活と教育 |
| 津田 嘉秀 | 学校現場における「国旗・国歌法」のあり方 |
| 西久保 蓉子 | 世界史教育における「パレスチナ問題」の考察 |
| 法山 知恵 | イラクへの自衛隊派遣における有事関連法案 |
| 原田 夕紀 | 永倉新八『浪士文久報国記事』の研究 |
| 福井 奈菜 | 播磨地域における広域公園と近隣公園の立地と利用動向 |
| 松本 碧 | グローバル化とナショナル・アイデンティティーにおける一考察 |
| 山脇 章裕 | ファシズムに関する一考察 |
| 池田 起子 | 歴史の中の差別を考える社会科授業 |
|---|---|
| 甲斐 啓介 | 巡察使バリニャーノと天正遣欧使節 |
| 慶田元 広信 | ネタ教材に基づく社会科授業開発 |
| 末久 淳史 | 日米開戦と南方資源 |
| 千賀 由里子 | 十字軍の研究 |
| 高尾 美賀子 | 香川県中央部綾上町におけるうどん産業の展開 |
| 畑 敦子 | 若者の宗教意識に関する一考察 |
| 平川 徳知 | 神楽の成立と変容にみる石見地方の特質 |
| 福岡 武史 | 兵庫県におけるゴルフ場の分布と立地の研究縄文時代の遺跡分布とその背景 |
| 藤井 幹子 | 青少年の価値観と不登校に関する一考察 |
| 藤原 裕司 | 粒度分析からみる播磨平野の古環境 |
| 前田 正弘 | 現代における老子の受容について |
| 向井 俊則 | 学校における「ジェンダーフリー」の取り組み |
| 矢田 浩太郎 | 社町の地形環境 |
| 山口 由貴 | 室町・戦国期法隆寺領播磨国鵤荘における村落と公文 |
| 青木 伸也 | 非日常における自己確認 「スーパーサバイバルキャンプ」を事例として |
|---|---|
| 赤木 一成 | 高速バスによる都市間連結ネットワークの形成と変化 |
| 浅川 葉木 | 祭りを通してみる社町の地域性 |
| 五十嵐 康顕 | 南北朝・室町期における樺山氏の政治的動向 |
| 池尾 尚子 | 吉田茂・政権担当能力の研究 |
| 出水澤 春菜 | 革命前夜のフランス社会に関する研究 |
| 岩下 真一郎 | 地域学習の教材開発と授業実践 -地域見学活動の視聴覚教材活用を視点にして- |
| 内田 雄太郎 | 明治初年における木村益二郎の戦略 |
| 尾﨑 由季 | 伊藤博文の対朝鮮政策に関する一考察 |
| 小幡 美佳 | 沖縄における戦跡観光に関する地理学的研究 |
| 酒井 頼子 | 都市近郊地域における憩い空間の創造 -神戸市北部のレクリエーション公園- |
| 坂本 勝志 | 笠岡湾干拓に関する地誌学的考察 |
| 重内 俊介 | 千種高原スキー場の立地と展開 -西播北西部の観光開発と地域振興- |
| 高見 篤士 | 村上春樹の初期の小説について -『風の歌を聴け』,『1973年のピンボール』の「僕」- |
| 竹森 伸二 | 鹿児島県離島と現状と課題 -地域の自律と学校教育の持続性を探る- |
| 田邊 仁美 | 鎌倉~室町期における竹原小早川氏の発展 |
| 戸田 弘恵 | 古代・中世説話集にみる女性と家族 |
| 内藤 聡 | ナチスの台頭 |
| 中島 由美子 | 多元的解釈を促す歴史学習 ~南京事件を手がかりに~ |
| 松岡 利恵 | 守護細川氏の丹波国支配の展開 |
| 宮阪 征史朗 | 第二次大戦中における和平派の行動について -米内光政を中心として- |
| 山田 真衣 | マイヤーリンク事件に関する研究 |
| 秋定 辰昌 | 総合スポーツ施設の整備計画と立地機能 ― 長野県菅平と神戸市しあわせの村 ― |
|---|---|
| 伊藤 正江 | 奇兵隊の研究 ~ 高杉晋作を中心として ~ |
| 稲津 寛子 | 最終氷期における氷上盆地の古環境 |
| 辛川 智大 | 不登校と体験学習に関する社会学的実証研究 ― 適応指導教室におけるフィールドワークを中心に ― |
| 菅原 弘貴 | 社町台地の地形発達史 |
| 杉山 修平 | 地図検索システムの開発と利用環境の整備 |
| 髙田 佳予子 | 高校世界史の教材研究 ~ ユダヤ人問題を例として ~ |
| 髙吉 京子 | 有村次左衛門兼清の研究 ~ 桜田門外の変を中心として ~ |
| 田中 慎一郎 | 少年法制の形態に関する研究 ~ ティーンコートを中心として ~ |
| 戸部 美紀 | 赤穂平野の地形と開発過程 |
| 永岡 功太郎 | 日本企業の海外進出 |
| 中島 正登 | 播磨在田氏の研究 |
| 長棟 健太 | 民俗芸能伝承に関する社会学的研究 ― 塩屋荒神社の獅子舞を事例として ― |
| 南部 智大 | 町人郷土坂本龍馬に関する一考察 |
| 外薗 祐樹 | 地方都市の国際交流に関する社会学的研究 ― 神戸市の姉妹都市事業を中心として ― |
| 前田 健佑 | 兵庫開港に関する一考察 |
| 松尾 美和 | グリム兄弟とその時代 ―『童話集』を中心にして ― |
| 松原 秀樹 | ナポレオン=ボナパルトに関する研究 ― ナポレオンの支配とその影響を中心として ― |
| 松本 由紀 | 千種川中流域の地形 |
| 宮崎 智至 | 摂津有馬氏の研究 |
| 山田 孝夫 | ホメロス研究 |
| 山田 雅彦 | ゴルフ場開発と地域変容に関する一考察 ― 宮崎県門川町を事例に ― |
| 赤松 稔 | 情報化社会における青少年の人間関係に関する一考察 |
|---|---|
| 池田 宏美 | 物語作品の想像空間と地理空間の再構成 |
| 石田 美香 | 青少年の価値観とボランティア活動 |
| 恵後原 宏彰 | 円高と日本経済の動向 |
| 小田 浩平 | 曹魏政権の人事機構についての考察 |
| 河合 聡子 | 毛沢東の抗日戦争思想と方針について |
| 栗原 由利子 | 年齢別人口分布からみた兵庫県の地域特性 |
| 久留米 正名 | ジャンヌ=ダルク研究-処刑裁判を中心として- |
| 黒瀬 広充 | 政教分離と信教の自由に関する一考察 |
| 小越 周平 | 「西脇の自然環境」寺内 仁 自由主義の可能性と限界 |
| 中村 由美 | 丹波波多野氏の発展と領国支配 |
| 藤原 正徳 | モータースポーツの安全性における1考察 |
| 堀 慎一郎 | 姫路平野南部の地形発達 |
| 本玉 章二 | 真田昌幸の大名化について |
| 松井 由味 | 昭和20年・終戦処理に関する一考察 |
| 三好 優香理 | 昭和18年・学徒出陣に関する一考察 |
| 渡邉 亜希子 | 西アジアの気候変動と文明 |