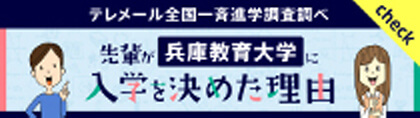古典に学ぶ「臨床教育学」〜現代の教育を「臨床教育学」する〜 《津田 直子さん》
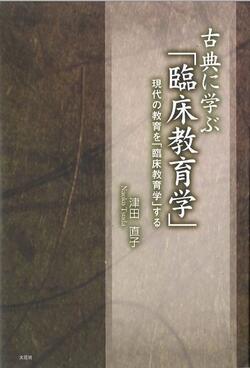 |
著者 |
津田 直子学校教育専攻 生徒指導コース平成10年3月修了(第17期) |
| 発行 | 文芸社 | |
| 発行年月 | 2015年5月15日発行 |
著書の紹介
書名が示す通り、『風姿花伝』『論語』などの古典から多くの示唆を受けて鋭く、また美しく論を展開している。
ユニークで教えられるところの多い現代教育論として、広く読まれることを期待する。
目次
<目 次>
第一章 はじめに
1 『徒然草』に倣って
2 筆者の来し方とこの本への思いれ
第二章 学校教育とは−ウチとソトとの認識の違い−
1 学校と勉強−学校だけが勉強の場か−
2 教育指導(生徒指導)とは−学校教育が成立するかどうかの瀬戸際−
3 学校の「危機管理」とは−その意味と実際−
4 「人間関係」と「危機管理」−学校における最大の危機の発生源−
5 学校教育以外の「教育」−大きく広がるその範囲−
第三章 現代社会と教育
1 教育の移り変わり−時代の変遷と教育−
2 IT社会の功罪−大学入試での携帯電話不正使用事件を通して−
第四章 「伝承」-教育における教え伝えることとは−
1 弟子に受け継がれた「技」−金メダルへの十二年の道のり−
2 伝統を守り伝える儀式−変わらずに変わる老舗の味−
3 精神を受け継いで一人前−ある寿司職人の親方と弟子−
4 筆者のささやかな経験−筆者の背中を見ていた教え子たち−
第五章 人を育てる−「教育」における「育てる」とは−
1 筆者が「育てた」二人の子ども−対照的な関わりの効果−
2 「教師」と「育師」−学校教育における「育てる」とは−
第六章 教育と人間関係−何より大切なもの−
1 学校教育と「人間関係」−その複雑なあり様−
2 「人間関係」スキルとしての「交流分析」−その活用法の提案−
第七章 教育における有機栽培の可能性
1 りんごの有機栽培への挑戦−実現までの苦難−
2 究極の有機栽培−そこに見る深い哲学−
3 りんごの木と子ども−そこから見えてくる現代の教育問題−
第八章 学校教育の「枠」のウチとソト−「個性」の難しさ−
1 「制服」と「個性」−その関係とは−
2 「個性」の二律背反−その取り扱いの大変さ−
第九章 テレビ番組や映画の臨床心理学的分析−斜めから楽しむ試み−
1 善人が引き起こす迷惑−二人の医師の対照的な生き様−
2 禁止令の恐ろしさ−裏のメッセージがもたらす悲劇−
3 スーパーバイズとは−『羊たちの沈黙』に見るそのあり方−
第十章 教育の表と裏−「教えること」と「教えられること」の関係とは−
1 『ハスラー2』に見る「教えること」と「教えられること」−その表と裏−
2 教員の「教えること」と「教えられること」とは−体験や見聞からの考察−
第十一章 理論と実践の関係とは−「臨床教育学」の意味と意義−
1 あるシェフの試み−そこに見出せる「臨床」の意味−
2 理論と実践の折り合い−「臨床教育学」のあり方とは−
3 現状をどうする−「臨床教育学」の可能性−
第十二章 「意欲」の大切さ−学ぶことの原動力としての働き−
1 「意欲」の格差の問題−その理論的基盤の「教育臨床社会学」−
2 「意欲」溢れる人たち−意欲的に学ぶ二人の高齢者−
第十三章 古典と教育 一−『論語』に見る教育の本質−
1 古典に見出す教育論−古今東西の教育論−
2 『論語』に見る「教育」の本質−「教育」における不易−
3 『論語』の中身−現代にも通じるその内容−
第十四章 古典と教育 二−『風姿花伝』に見る日本の教育の原点−
1 『風姿花伝』との出会い−筆者と『風姿花伝』との縁−
2 『風姿花伝』とは−驚嘆すべきその内容−
3 教育論としての『風姿花伝』−「修行」と「教育」との共通点−
4 『風姿花伝』と臨床心理−演劇の臨床心理学的理解とは
5 「芸」の技と心理面接−演劇と心理面接との共通点とは−
6 「型」と技、そして技から「芸」へ−目指すべき理想の境地−
7 教育論としての『風姿花伝』−「修行」と「教育」との共通点−
4 『風姿花伝』の凄さ−現代に生かすべきその内容−
第十五章 ここで「打ち止め」