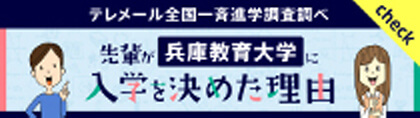京都府立第一高女と鴨沂高校 《拝師 暢彦さん》
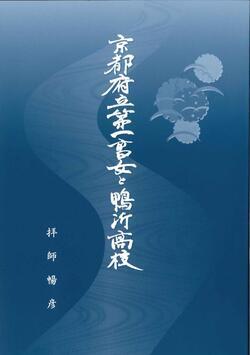 |
著者 |
拝師 暢彦教科・領域教育専攻 自然系コース昭和58年3月修了(第2期) |
| 発行 | 拝師 暢彦(自費出版) お問い合わせ:①筆者・E-mail nobuhiko.haishi@gmail.com ②京都新聞出版センター・TEL 075-241-6192 |
|
| サイズ | A5判・194頁 | |
| 発行年月 | 2017年2月15日発行 |
書名(校名)について
京都府立第一高(等)女(学校)は、我が国女子教育の嚆矢「新英学校及び女紅場」を前身とし、また、鴨沂高(等学)校は、昭和23年の学制改革で新制高(等学)校となり、校名を鴨沂(おうき)と名付けられました。
NHK大河ドラマ『八重の桜』の山本八重、ミス日本第1号の山本富士子、森光子、田宮二郎、沢田研二さんらが通った学校と言えば、「そうか」と分かっていただけるかもしれません。
この鴨沂高校に、筆者は平成13年4月から同16年3月までの間、3カ年間、校長として勤務しました。
本著は、その間に体験したこと、疑問に思ったこと等について書き綴ったものです。
本の概要
記述したテーマは次に記す4項目です。
第一話 京都府立第一高等女学校長・河原一郎の『特別引継事項』
第二話 新制京都府立鴨沂高等学校
第三話 学校所蔵名画の謎
第四話 こぼれ話...鴨谷庵独言 以上
各話の要旨
【第一話】
着任して間もなく、校長机の収納庫を整理していると、明治23年から大正6年までの約27年間、校長を務められた河原一郎氏の文書『特別引継事項』が出てきました。
文書に記されていたことがらは、①旧校舎より移築した建造物、②記念樹、③大禮記念事業、④日露戦争記念事業、⑤特別事業〈明治神宮献木他〉、⑥特別寄贈品〈ピアノ他〉、及び⑦将来施設の件〈運動場拡張他〉と、現在校(鴨沂高校)のコンセプトに繋がる内容でした。
第一話では、上記項目①〜⑦のそれぞれについて、解説を加え説明しています。
河原校長が記された『特別引継事項』文書は、鴨沂高校関係者は言うまでもなく、学校教育研究者にとっても、明治・大正期における女子教育を理解していくうえで、見逃せないものであると考えています。
【第二話】
昭和20年8月、我が国はポツダム宣言を受諾、昭和23年に「教育基本法」が制定されるとともに、「教育勅語」は失効・廃止されました。このことにより、多くの旧制中学(女学校)は新制高(等学)校となります。
地域制(高校3原則)となりましたので、校名は通常、設置された地域の地名が付けられることになりました。例えば、府立第一中学は洛北、府立第二高女は朱雀という如くです。いわゆる数字の付いた校名(ナンバースクール)は無くなりました。府立第一高女の場合、地名にない鴨沂(おうき)と名付けられました。
なぜ地名にない校名が名付けられたのでしょう? そもそも鴨沂とはどういう意味なのでしょう?
由来・経緯を調べていく過程で、当時の校長(片岡仁志氏)が腐心されていたことが分かりました。
その他、本章においては、今まで不明確であった新制高校発足当初の状況について考究しています。
【第三話】 京都府立鴨沂高校は140有余年の歴史を有する学校です。旧制女学校時代は皇室とも係わりがあり、九条家所縁の校門をはじめ寄贈された名画(上村松園作『夕暮』)等を数多く所蔵しています。
なぜ、鴨沂高校にはたくさんの美術品があるのでしょう? 学校の『所蔵美術図録』(平成5年3月復刻版)に掲載された美術品26点を中心に、その由来・来歴等について調べました。
作品一つひとつについて、寄贈の経緯等を明らかにしていくと、謎が解けてきました。......
その他、昭和の学制改革のとき、近隣の学校から所蔵する書画、備品等が持ち込まれたことが分かりました。このことについては、現在、京都文化博物館等により調査がなされています。
【第四話】 鴨沂高校の校内に足を一歩踏み入れると、ユニークな施設設備(九条家の薬医門、段差の小さい木製階段、地下トンネル他)が目に飛び込んできます。更に勤務校となると、学校専用の言葉(用語)に悩まされました。例えば、ウィーンの森、スクールソング、鴨沂の自由、などなどです。
なぜこのように呼ばれるようになったのでしょう? 言葉の意味・由来を永年勤務している職員に尋ねても、納得できる答えが返ってきません。そこで、校内に残された文書、資料等を調べると、......。
第四話においては、新制高校になってからの出来事を中心に、逸話を交えて紹介しています。
【附録(略年表)】
本文を補完する目的で、明治初年から今日(2016年)に至るまでの出来事を、本校に関係する事項とその他、国・府等に関係する事項との二つに区分し、それぞれ21頁(×42頁)に亘り記載しました。
明治〜大正〜昭和〜平成と我が国における学校教育の移り変わりを俯瞰することが出来ます。