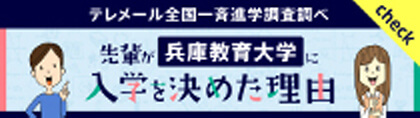| 題目22 | これからの時代における手書きの意義-認知機能の生涯発達の観点から― | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 現代においては、急速なデジタル化により手書きの機会が減少している。デジタル化が読み書き能力に及ぼした影響や、漢字の手書き習熟が高度な言語能力に及ぼす効果に関する講師自身の研究成果、および、それに関連する国内外の研究知見について紹介し、認知機能の生涯発達における読み書き習熟の意義について検討する。 | |
| 教員 | オオツカ サダオ | |
| 大塚 貞男 | ||
| 分野・教科名 | 生涯学習 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 備考 | sotsuka(あっと)hyogo-u.ac.jp ※(あっと)は@に置き換えてください。 |
|
| 題目15 | 虐待を受けた子どもへの対応と支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 虐待対応をする際の留意点や子どもへの心理的サポートについて,また支援の際に陥りやすい教師の心理的疲労やセルフケアについて取り上げる。 | |
| 教員 | ウンノ チホコ | |
| 海野 千畝子 | ||
| 電話 | (0795)44-2182 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目16 | 教師を対象とした青少年の自殺予防プログラム | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 自殺(自死)は,本邦の青少年の死因第1位である。教師が知っておくべき青少年の自殺予防の基礎知識,自殺の危機が迫っている青少年への対応の原則,多くの自殺の背景と推測されているうつ病の実態と治療について学んでいく。 | |
| 教員 | エンドウ ヒロノ | |
| 遠藤 裕乃 | ||
| 電話 | (0795)44-2168 | |
| 分野・教科名 | 教育臨床心理学 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ||
| 市民一般 | ||
| 分類 |
|
|
| 題目17 | 発達障害の理解と対応 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 発達障害の特性を理解し,本人や家族へのかかわり方について一緒に考えていきます。 | |
| 教員 | サダヒサ マキ | |
| 佐田久 真貴 | ||
| 電話 | (0795)44-2283 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ 小学校高学年以上 | |
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目1901 | 対人支援スキルアップ ~児童生徒の成長を支える関わり方~ | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 相手の話を傾聴し,共感的に受け止めることは,対人支援において不可欠なスキルです。ただし,実際のところ,そのような関わりだけでは問題解決に向かわないケースが数多く存在します。本講座では,このような状況に直面した際に,次の一手が打てるようになるために,実証的根拠に基づいた認知行動療法の考え方や関わり方について,演習やワークを加えながら解説したいと思います。 | |
| 教員 | イトウ ダイスケ | |
| 伊藤 大輔 | ||
| 電話 | 080-9459-8142 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ||
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目1902 | 今日からできる感情のセルフマネジメント | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 私たちにとって,自分自身の感情とうまく付き合っていくことは,円滑な生活を営む上で極めて重要です。本講座では,まず,抑うつ,不安,怒りなどの感情の役割について解説します。そして,自分ですぐに実践できる感情のコントロールの方法について,演習やワークを加えながら紹介したいと思います。 | |
| 教員 | イトウ ダイスケ | |
| 伊藤 大輔 | ||
| 電話 | 080-9459-8142 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ | |
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目23 | 現代の青少年に対する理解と支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 現代の家族や社会の変化に中で,心の育ちにも変化が生じています。その中で,不登校・ひきこもり,発達障害に加え,見えづらい不適応の問題が目立つようになりました。こうした変化をどのように理解し,彼らの心を育み,鍛え,豊かに出来るのか,親や教師,周囲の大人も変わっていけるかについて,一緒に考えていきます。 | |
| 教員 | ナガヤマ トモユキ | |
| 永山 智之 | ||
| 電話 | 080-7252-9648 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ | |
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目21 | 児童期・思春期の心理的困難について | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 不登校,いじめ,虐待,養育・指導困難,発達障害,学習の困難,自傷・自殺など,教育現場において生起するさまざまな問題を心理学的に理解し,その具体的な対応法を考察していくことを専門としています。 | |
| 教員 | ウエダ カツヒサ | |
| 上田 勝久 | ||
| 電話 | (0795)44-2266 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ | |
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|
| 題目18 | 精神障害・発達障害のある方へのキャリア教育及び就職支援 | |
|---|---|---|
| 題目概要 | 高等教育から社会(産業)へと移行していく支援については,現在制度の谷間と言われており,支援サービスや技術などの専門性が高まっていない現状にあります。そういった課題改善に向けて,福祉サービスなどの地域資源との連携や認知行動療法を用いた支援について扱います。 | |
| 教員 | イケダ ヒロユキ | |
| 池田 浩之 | ||
| 電話 | 080-9459-8130 | |
| 分野・教科名 | キャリア教育・就労支援 | |
| 対象 | 教員 |
|
| 児童・生徒 | ○ | |
| 保護者 | ○ | |
| 市民一般 | ○ | |
| 分類 |
|
|