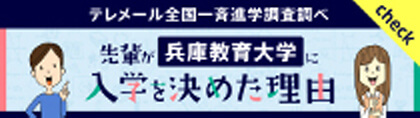本表彰は平成22年から実施しています。兵庫教育大学大学院学校教育研究科の修了生本人または構成員とする団体の教育実践研究活動等における顕著な成果や功績に対して、学長と同窓会長の連名で表彰を行うものです。
令和7年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和7年度は、役員推薦3名(嬉野賞2名・奨励賞1名)が受賞されました。
なお、本年度は教育実践研究論文による表彰(奨励賞)は該当者がありませんでした。
表彰式は、令和7年7月26日(土)開催の「令和7年度大学院同窓会総会・第44回全国研究大会【高知大会】」で執り行なわれました。
(順不同・敬称略)
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 長﨑 政浩 |
平成4(1992)年3月 |
教科・領域教育専攻 言語系コース(英語) |
高知県立高等学校英語教諭を皮切りに、高知県教育センター研修指導部指導主事(1997~2001)や、高知県教育委員会事務局高等学校課学校教育班長(2006 ~2007)、同事務局高等学校課チーフ(2007~2008)を歴任後、高知工科大学に異動。 |
| 傳法谷 肇 |
平成27(2015)年3月 令和7(2025)年3月 |
教育実践高度化専攻 教育実践高度化専攻 |
兵庫教育大学大学院「学校経営コース」と「教育政策リーダーコース」の両コースを修了された。 大学院修了後に、北海道教育委員会主任指導主事、帯広市教育員会統括指導主事を歴任。一貫して教育指導や教育計画策定に関わり、教育現場で活躍している。その中で、兵庫教育大学大学院での学びと研究成果を活かし、教育行政職として勤務の傍ら、教育政策や学校改善などに関して、多様な研究を重ねている。 研究成果として、「持続可能なコミュニティスクールの取組として、学力向上、新教科の設立による児童生徒の向上を目指すプランの構築」や「地域社会のつながりを醸成するカリュキュラムの編成」、「学校やメタバースを活用したコミュニティの創出」、「幸せの実感と児童生徒の資質・能力の向上を図るプランの策定」がある。 また、社会に開かれた教育課程を実現するために、ふるさと納税を活用するなど、多くの成果を収めた。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 高田 哲史 |
平成3(1991)年3月 |
教科・領域教育専攻 生活・健康系コース(保体) |
大学院修了後、岡山県立高等学校保健体育科教員として、また日本体育・スポーツ・健康学会体育哲学専門領域の研究者として多くの研究を行った。 |
令和6年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和6年度は、役員推薦2名、教育実践研究論文3件4名が受賞されました。
表彰式は、令和6年8月3日(土)開催の「令和6年度大学院同窓会総会・第43回全国研究大会【盛岡大会】」で執り行なわれました。
(順不同・敬称略)
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 大谷 哲弘 |
平成21(2009)年3月 |
学校教育学専攻 臨床心理学コース |
・2010年より6年間、岩手県立総合教育センター支援指導部教育支援相談担当の研修指導主事として、児童生徒への支援、教育相談やカウンセリング等で若手教員の指導に当たった。また、『いわて「いじめ問題」防止・対応マニュアル』の作成に尽力した。 |
| 川村 庸子 |
昭和60(1985)年3月 平成31(2019)年3月 |
学校教育学専攻 教育実践高度化専攻 |
・岩手を代表する女性教育者で、釜石市の中学校を皮切りに県内の中学校で教育に当たり校長職を務めた。現在もなお、社会に開かれた教育課程を目指した活動や若手教員の指導にあたっている。 ・本学大学院第8代同窓会長として2期4年にわたり、同窓会の発展に寄与された。前回岩手大会では、発表者として登壇。今回盛岡大会では顧問として大会運営に関わった。また、共に学ぶ同志とともに「コミュニティスクール構想」を岩手県全域に推進している。 ・「生涯にわたって学ぶ。」を自ら実践し、本学大学院で昼間コース、夜間コースと二度にわたって学び、今も学び続けている。 ・教育に対する崇高な理想と、瞬時の判断力を有し、教育者として、管理職として、そして同窓会長として、場に応じた判断や適応力を発揮され、同窓会を牽引してきた。 |
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 甲斐 順 | 平成14(2002)年3月 (20期) |
教科・領域教育専攻 言語系コース(英語) |
ペアによる音読指導を重視した英語授業実践 |
| 宮川 雄基 | 令和4(2022)年3月 (31期) |
教育実践高度化専攻 授業実践リーダーコース |
自閉症・情緒障害特別支援学級における、人間関係調整力・自己調整力の向上を目指して取り組んだ特別活動及び自立活動の実践 |
|
日光 恵利 川口めぐみ |
令和2(2020)年3月 令和2(2020)年3月 |
人間発達教育専攻 人間発達教育専攻 |
保育学生の伝統的な遊びの実施状況と認識に関する研究 |
令和5年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和5年度は、次の5名(嬉野賞2名、奨励賞3名)が受賞されました。
表彰式は、令和5年8月5日(土)開催の「令和5年度大学院同窓会総会・第42回全国研究大会【大阪・奈良・和歌山大会】」で執り行なわれました。
(順不同・敬称略)
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 酒井 喜八郎 |
平成6(1994)年3月 |
教科領域教育専攻 社会系コース |
南九州大学人間発達学部子ども教育学科 准教授 |
| 樋口 洋三 | 昭和62(1987)年3月 (6期) |
教科領域教育専攻 生活・健康系(保体)コース |
・2002年4月より3年間、文部科学省より中国・天津日本人学校校長として派遣され、学校移転や日本人学校としては例をみないという部活動の創設等にも尽力した。 ・帰国後、日本人学校校長経験者として、文部科学省主催の各種研修会や講習会の講師を永年務めている。 ・これまで大阪市教育センター教育指導員として、新任や若手教員の指導にあたる。また、現在は、大阪市教育支援センター指導員として、悩みや困難を抱える多くの児童生徒に寄り添い課題解決への支援を行っている。 ・今夏開催される「第42回全国大会」における大会実行委員長に人望厚く推挙され、大会の成功に向けてリーダーシップを発揮している。 |
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 西井 孝明 | 平成14(2002)年3月 (21期) |
障害児教育専攻 | 知的障害特別支援学校における各作業種に対応した作業班別「安全点検確認シート」の開発 |
| 柳瀬 賢佑 | 令和4(2022)年3月 (41期) |
人間発達教育専攻・教育コミュニケーションコース | 多忙な中学校現場における教師のリフレクションを促す持続可能な教育実践(研修)の提案 ─教師の「対話」に焦点を当てて─ |
| 伊藤 良介 | 令和2(2020)年3月 (39期) |
教育実践高度化専攻 授業実践開発コース |
小学校総合的な学習の時間におけるICEモデルを活用した自己有用感を高めるキャリア教育の授業改善 |
令和4年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和4年度は、次の7名(嬉野賞1名、奨励賞6名)が受賞されました。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 米谷 光弘 | 昭和58(1983)年3月 (2期) |
学校教育専攻 幼児教育コース |
西南学院大学人間科学部教授 一般財団法人国際グローバル交流発展協会代表理事 幼児健康学・幼児体育学の実践及び研究に加えて、保育学・乳幼児教育学の本質について研究、提言をされ、国際的・学際的・学術的な立場から国内外の保育者及び教員養成の大学教鞭を西南学院大学で執られ、保育の一元化に寄与された。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 寺田 道夫 | 昭和57(1982)年3月 (1期) |
学校教育専攻 教育基礎コース |
東海学院大学人間関係学部心理学科客員教授 岐阜県の公立小・中学校で教諭・教頭・校長を歴任され、その後は、東海学院大学心理学科で准教授・教授・客員教授として学部・院生の指導に尽力された。長年不登校問題に関り、臨床実践および学術研究に取り組み、著書「不登校の子どもの理解と支援」を出版された。 |
| 小林 由美子 | 平成3(1991)年3月 (10期) |
学校教育専攻 生徒指導コース |
名古屋学院大学スポーツ健康学部准教授 名古屋市のスクールカウンセラーの育成に努め、文部科学省いじめ等不登校支援事業審査委員として全国の教育実践の推進に寄与するとともに、教育研究学会の発表や教育専門誌の執筆で最新の教育情報や自らの研究成果を伝えた。 また、本学大学院同窓会理事として同窓会活動の推進に尽力された。 |
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 井上 敏孝 | 平成21(2009)年3月 (28期) |
教科・領域教育学専攻 社会系コース |
非対面型授業における授業構想力の育成 -教員養成課程における「社会科教育法」を通してー |
| 馬場 裕子 | 平成21(2009)年3月 (27期) |
教科・領域教育学専攻 言語系コース(国語) |
異言語環境における「感覚共有」についての一考察 ー海外書道実践とサッカーチームの事例からー |
| 西小路 勝子 | 平成22(2010)年3月 (28期) |
学校教育専攻 幼年教育コース |
明治後期の保育実践内容と保育意図についての考察 ー大阪市立愛珠幼稚園の「保育要目草案」に着目してー |
| 浦郷 淳 | 平成22(2010)年3月 (29期) |
教育実践高度化専攻 教育実践リーダーコース |
ICT活用が生み出す生活科授業での「時間」についての一考察 -1年生「学校紹介」に焦点をあてて- |
令和3年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和3年度は、次の5名(奨励賞5名)が受賞されました。
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 富坂 耕次 (静岡県) |
平成2(1990)年3月 (9期生) |
教科・領域教育専攻 |
中学生の幾何学的思考水準の進展を促す授業 -van Hiele の学習水準理論に着目して- |
| 井上 万紀 (兵庫県) |
平成27(2015)年3月 (33期生) |
教育実践高度化専攻 生徒指導実践開発コース |
音楽紙芝居の実践と効果 -子育て支援ルームと特別支援学校での教材開発- |
|
仲井 勝巳 |
平成27(2015)年3月 (33期生) |
人間発達教育専攻 教育コミュニケーションコース |
小学2年生における特別の教科「道徳」の授業法に関する研究 -主体的・対話的で深い学びを目指した1年間の実践から- |
| 白川 正樹 (東京都) |
平成28(2016)年3月 (35期生) |
教育実践高度化専攻 学校経営コース |
学校を主体とした第三者評価の全国的普及の推進に係る課題と展望 -日本・イギリス・アメリカ・ニュージーランドの第三者評価の比較- |
| 出村 雅実 (茨城県) |
平成22(2010)年3月 (29期生) |
教科・領域教育専攻 自然系(理科)コース |
総合的な学びが深まるハイフレックス型授業の実践について -大学1年生への実践記録から- |
令和2年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和2年度は、次の4名(嬉野賞1名、奨励賞3名)が受賞されました。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 山谷 敬三郎 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
学校教育専攻 教育基礎コース |
学校法人北翔大学理事 学長 北海道教育委員会教育相談スーパーバイザー、日本学校心理士会 会長を歴任し、社会貢献活動も積極的に行っている。 「教授・学習過程における教育方法・技術とコーチングモデルの統 合に関する研究」で博士号を取得するとともに、その普及と実践 に尽力している。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 橋本 美彦 | 昭和63(1988)年3月 (7期生) |
学校教育専攻 教育経営コース |
中部大学現代教育学部現代教育学科 准教授 中部教育実践研究会を主宰し、若い現職教員と教員志望学生の 指導に携わっている。 豊富な現場経験と研究者精神に基づく指導は、現職教員の力量 向上と大学での教育養成の推進力となっている。 理科授業について多数の論文を発表し、教職教育に関する著書 も執筆している。 |
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 大島 浩 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
自然系コース | 1.生徒実験としてのアボガドロ数算出の評価 2.寺田物理学の位相 |
| 井上 万紀 | 平成27(2015)年3月 (33期生) |
教育実践高度化専攻 生徒指導実践開発コース |
特別支援教育におけるわかって出来る音楽の授業 |
令和元年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
令和元年度は、次の5名(特別賞1名、嬉野賞2名、奨励賞2名)が受賞されました。
| 特別賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 大橋 博 | 平成13(2001)年3月 (20期生) |
学校教育専攻 教育経営コース |
日本を代表する教育社・教育実業家 第5代大学院同窓会会長 《主な功績および役職》 学校法人創志学園理事長 兵庫教育大学学長選考委員 創造学園、環太平洋大学、クラーク記念国際高校、創志学園等を 創設し、日本の教育に大きな影響を与えている。 |
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 大槻 雅俊 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
教科・領域教育専攻 社会系コース |
教育研究活動や社会貢献を通して後進を指導 元大学院同窓会副会長 《主な功績および役職》 大阪成蹊短期大学教授 大阪市立小学校長、国際理解教育部長、兵庫教育大学E.D.Seminar 代表等を歴任し、社会科教育等の分野において、教育実践を通した 理論研究を推進した。 |
| 川﨑 聡大 | 平成8(1996)年3月 (15期) |
障害児教育専攻 | 本大学出身の新進気鋭の研究者 《主な功績および役職》 東北大学准教授(大学院教育学研究科教育心理学講座) 障害児教育を中心に幅広い分野での研究をしている。全国各地で講 演会・講習会の講師をつとめている。日本の障害児教育や心理学に 偉大な功績を残している。 |
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 丹後 政俊 | 平成3(1991)年3月 (10期生) |
教科・領域教育専攻 社会系コース |
学校教育における冒険教育の効果とその課題 ~ささやま冒険教育の実践を中心として~ |
| 河合 信之 | 平成27(2015)年3月 (34期生) |
教育内容・方法開発専攻 認識形成系教育コース |
概念変換を促すワークシートの考案と効果の実証的研究 ~力と運動における素朴概念を事例として~ |
(敬称略)
平成30年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成30年度は、次の8名(嬉野賞1名、奨励賞7名)が受賞されました。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 伊井 直明 | 昭和61(1986)年3月 (4期生) |
学校教育専攻 教育基礎コース |
教育現場や教育行政、在外教育施設での豊富な経験を踏まえ、 海外子女教育、帰国・外国人児童生徒教育、人権教育を中心に 研究論文や提言等を多数執筆し、顕著な実績を上げている。 また、同窓会活動の発展にも尽力している。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 津田 直子 | 平成10(1998)年3月 (17期生) |
学校教育専攻 生徒指導コース |
教育現場での実戦経験を踏まえ、大学院修了後更に研究を深め 博士(臨床教育学)の学位を取得された。臨床教育学を専門領 域に単著二編を執筆し、また心理カウンセラーとして教育相談 活動に携わるなど教育への貢献は大きい。 |
| 三谷 祐児 | 平成8(1996)年3月 (15期生) |
教科・領域教育専攻 言語系コース(国語) |
長年にわたり国語科(作文教育)について研究を深め「百マス 作文」を考案し実践に取り組む。また、学校管理職として午前 授業5時間制の導入を行うなど、特色ある学校づくりや教育の 充実、教職員の働き方改革に成果を上げている。 |
| 奨励賞(論文賞) | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 論文のテーマ |
| 小川 雄太 | 平成29(2017)年3月 (36期生) |
教育実践高度化専攻 授業実践開発コース |
公民科「現代社会」において社会認識の深化を目指したNIEの実践 公民科「現代社会」において社会認識の深化を企図したNIEワーク シートを作成し、その効果について実践的な研究を深め、教育実践 研究活動の向上に貢献した。 |
| 河合 信之 | 平成27(2015)年3月 (34期生) |
教育内容・方法開発専攻 認識形成系教育コース |
科学的概念への変換を促す質問紙による教授・学習法 -「光の進み方」を事例として- 光の進み方の認識に焦点を当て、科学的概念の理解・定着・活用を 図るための質問紙を考案し、教授・学習法の研究を実践的に深め、 教育実践研究活動の向上に貢献した。 |
| 松田 雅代 | 平成29(2017)年3月 (35期生) |
教育実践高度化専攻 授業実践開発コース |
小学校教師の理科授業の力量形成に関する一考察 -概念変容理解を通した調査事例から- 理科を専門としない教職経験10年以下の小学校教師を対象とした 教師の力量形成に関し、概念変容を促す授業の実践的研究を深め、 教育実践研究活動の向上に貢献した。 |
| 中 佳久 | 平成12(2000)年3月 (19期生) |
障害児教育専攻 | 乳幼児期の子どもの教育相談の取り組みに関する研究 -見え方を中心に- 乳幼児期の子どもの見え方についての教育相談事例を統計的に分析 し、具体的な事例を含めその対応について考査を深め、教育実践研 究活動の向上に貢献した。 |
| 小川 圭子 |
平成11(1999)年3月 |
幼児教育専攻 | |
(五十音順、敬称略)
平成29年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成29年度に受賞されたのは、次の8名(嬉野賞3名、奨励賞5名)の方々です。
| 嬉野賞 | |||
|---|---|---|---|
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース 名 | 受 賞 理 由 |
| 荒井 豊 |
昭和58(1983)年3月 |
教科・領域教育専攻 |
教育現場での豊富な経験を踏まえ、理科教育指導法に関する実践的研究を深め、平成21年には兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科に博士論文を提出し、博士号が授与された。また、同窓会活動の発展に尽力している。 |
| 中園 大三郎 | 昭和59(1984)年3月 (3期) |
学校教育専攻 生徒指導コース |
特別活動を専門領域に、キャリア教育の視点から係活動について実践的研究を深められた。特別活動に関する、単著・共著・論文等を多数執筆するとともに講演活動にも熱心に取り組む。現在も大学と同窓会の発展に尽力している。 |
| 拝師 暢彦 | 昭和58(1983)年3月 (2期) |
教科・領域教育専攻 自然系コース |
教育現場での地道な実践とともに、同窓会活動に尽力し組織づくりに果たした功績は大きい。退職後も、学び続ける教員として在職した学校の沿革史を自費出版するなど社会貢献活動にも熱心に取り組んでいる。 |
| 奨励賞 | |||
|---|---|---|---|
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース 名 | 受 賞 理 由 |
| 大島 浩 | 昭和59(1984)年3月 (3期) |
教科・領域教育専攻 |
教育実践研究論文「課題探求型モデル学習の構成」 |
| 澁谷 義人 |
平成19(2007)年3月 |
学校教育専攻 |
教育実践研究論文「より深く地域と連携した高校教育の実践」 |
| 古屋 光晴 | 平成27(2015)年3月 (34期) |
教育実践高度化専攻 |
教育実践研究論文「特別支援学校における大学等への進路指導に関する一考察」 |
| 宮内 征人 | 平成21(2009)年3月 (28期) |
教科・領域教育専攻 言語系コース |
教育実践研究論文「中学校国語科における年間を見通した書くことのカリキュラム構想と実践の研究」 |
| 宮垣 覚 | 平成13(2001)年3月 (20期) |
教科・領域教育専攻 自然系コース |
教育実践研究論文「兵庫県の理数教育推進事業について」 |
(五十音順、敬称略)
平成28年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成28年度に受賞されたのは、次の4名(嬉野賞3名、奨励賞1名)の方々です。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 大前 泰彦 | 平成7(1995)年3月 (14期生) |
学校教育専攻 生徒指導コース |
教育現場での豊富な実践経験を踏まえ、また、臨床心理学の研究者としても 専門性を生かし、論文や訳書・共著等を多数執筆する。社会活動を広く展開し、 青少年の健全育成や後進の指導・育成にも尽力している。 |
| 小西 豊文 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
学校教育専攻 教育方法コース |
算数教育の指導者として実績があり、算数の指導法についての実践的研究を 深め、単著・共著等を多数執筆する。同窓会の研究部長としても手腕を発揮し、 基盤構築に貢献した。現在、教員養成系大学で後進の育成に努めている。 |
| 藤井 一亮 | 昭和63(1998)年3月 (7期生) |
教科・領域教育専攻 社会系コース |
終了後も、学び続ける教員としてギリシャ哲学の研究を深め、研究成果を活 かした授業実践に取り組んでいる。教育研究者として公民教育についての単 著・共著・論文等を多数発表し、送信の指導や育成に顕著な実績を上げている。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 小橋 拓司 | 平成17(2005)年3月 (24期生) |
教科・領域教育専攻 社会系コース |
県立高校教諭。専門の地歴科地理分野において実践的研究を深め多角的視点 から論文・調査報告等を多数執筆する。在籍する学校では、地域教材として生 徒とともに防災教育に取り組み、研究成果を発表するなど成果を上げている。 |
(五十音順、敬称略)
平成27年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成27年度に受賞されたのは、次の5名(嬉野賞3名、奨励賞2名)の方々です。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 坂口 豊 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
教科・領域教育専攻 言語系コース |
国語教育の指導者として豊富な実績があり、特に作文指導に関する共著や研究 論文等を多数執筆する。社会活動も広く展開し、後進の育成にも貢献している。 同窓会活動に尽力し組織の基盤づくりに果たした功績は大きい。 |
| 花井 正樹 | 昭和60(1985)年3月) (4期生) |
学校教育専攻 生徒指導コース |
教育研究者として不登校問題や教育相談を始め、教師への教育的支援について も研究を深め、論文や単著・共著等を多数執筆する。教育現場での豊富な経験 を生かし、愛知県でのスクールカウンセラー制度の普及・浸透に努めた。 |
| 平松 清志 | 昭和61(1986)年3月 (5期生) |
教科・領域教育専攻 生徒指導コース |
教育現場での実践経験を踏まえた、教育相談・臨床心理学の研究者として、論 文や単著・共著等を多数執筆する。実践研究活動における後進の指導や育成に も努めている。平成11年連合大学院後期博士課程修了(学校教育学博士)。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 酒井 達哉 | 平成23(2011)年3月 (30期生) |
教科・領域教育専攻 言語系コース |
総合的な学習の時間を中心に、他教科との関連を図りながら地域教材を生かし た授業の研究や教材開発に努めている。読売教育賞最優秀賞を始めとし教育実 践を踏まえた表彰を多く得ている。後進の育成にも尽力している。 |
| 真鍋 博 | 昭和58(1983)年3月 (2期生) |
学校教育学専攻 教育基礎コース |
大学院在学当時から、東井義雄先生の教育倫理と実践について研究を深め、学 校現場ではその実践に情熱を傾けた。退職後は、故郷の愛媛県で社会貢献活動 を広く展開し、地域づくりとその活性化に |
(五十音順、敬称略)
平成26年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成26年度に受賞されたのは、次の4名(嬉野賞2名、奨励賞2名)の方々です。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 佐倉 義信 | 昭和60(1985)年3月 (4期生) |
教科・領域教育専攻 言語系コース |
児童詩教育の指導者として豊富な実績があり、国語教育に関する編著執筆や |
| 福山 逸雄 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
学校教育専攻 生徒指導コース |
教育研究者として不登校問題や教育相談、教職研究の分野・領域において研 究に努め、論文や共著等を多数執筆する。実践研究活動における後進の指導 や日本学校教育相談学会の設立及び運営に尽力し、社会的貢献も大きい。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 成澤 真介 | 平成10(1998)年3月 (17期生) |
学校教育専攻 障害児教育コース |
特別支援学校教諭。発達障害に関する支援方法について研鑽を重ね、日本 支援教育実践学会研究奨励賞を受賞。地域における特別支援教育活動の功 績により、文部科学大臣優秀教員表彰を受賞する。特別支援教育に関する 著作も多い。 |
| 藤本 浩行 | 平成10(1998)年3月 (17期生) |
学校教育専攻 教育方法コース |
小学校教諭。社会科の地域教材を生かした教育実践に尽力し、文部科学大 臣優秀教員表彰等を受賞する。学級経営や学習指導等に関する共著・単著 も多数。地域の教育サークルを主催するなど後進の育成にも貢献している。 |
(五十音順、敬称略)
平成25年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成25年度に受賞されたのは、次の6名(特別賞2名、嬉野賞3名、奨励賞1名)の方々です。
| 特別賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 酒巻 成欣 | 昭和58(1983)年3月 (2期生) |
学校教育専攻 教育方法コース |
終了後は市行政に携わり地方教育の充実と発展に相応の成果を上げた。 国語教育への造詣は特に深く、市学習教材編集の代表として携わるほか 全小国語研究会の運営にもその手腕を発揮した。第3代同窓会長。 |
| 塩瀬 昌雄 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
学校教育専攻 教育経営コース |
第4代同窓会長。氏の会長就任は本会設立から10年を経る頃であるが、 本会及び都道府県支部の更なる活性化を課題に全国大会の地方持ち回り を積極的に推進するなど、現在の活動の基を整えた功績は大きい。 |
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 中田 正浩 |
昭和63(1988)年3月 平成18(2006)年3月 |
教科・領域教育専攻 学校教育専攻 |
中学校~地方教委~小・中学校長での公教育における実践を本学大学院で の理論研究と融合させた教育経営・教師教育関連の著作多数。現在、教員 養成系大学で、教職を目指す後進の育成と人材開発に努めている。 |
| 森 泰三 | 平成6(1994)年3月 (13期生) |
教科・領域教育専攻 社会系コース |
県立高校教諭。地理学及び地理教育学領域の研究で論文・レポート執筆や 学会発表多数。地理情報システム学会賞(2010.9)、日本国際地図学会賞 (2011.2)を受賞する。岡山大学大学院博士後期課程修了(環境理工学博士)。 |
| 山下 恭 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
教科・領域教育専攻 社会系コース |
県立高校教諭。終了後も塩業史の研究を継続し、神戸大学大学院博士課程 修了(経済学博士)。その研究論著は国内外100を超える大学図書館に所 蔵され、日本塩業史の第一人者と認められている。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 森本 雄一 | 平成21(2009)年3月 (28期生) |
教科・領域教育学専攻 自然系コース |
県立高校教諭。自宅に理科実験研修施設を開設して若い教員や学生に実験 ・観察指導を行うほか、教員研修の指導等に招聘されることが頻繁。大学 と連携してCSTの育成にも尽力し、理科教育の振興に果たす功績大である。 |
(五十音順、敬称略)
平成24年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成24年度に受賞されたのは、次の4名(特別賞2名、嬉野賞1名、奨励賞1名)の方々です。
| 特別賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 吉田 廣 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
学校教育学専攻 教育方法コース |
市教育委員長及び市教育長の経歴がある。本学大学院修了後、県教育 行政に携わった経験を生かして市教育の充実と発展に尽力し、相応の 成果を上げた。 同窓会会長(第5代)を7期14年にわたり努める。 |
| 山下 裕 | 昭和61(1986)年3月 (5期生) |
教科・領域教育学専攻 芸術系コース |
県教委指導職また学校長として精力的に組織を牽引し、教育現場の正 常化並びに教員の育成に多大な成果を上げた。 同窓会会長(第6代)を1期2年努めるが、都道府県連携推進本部設置 に関わり、その後の大学と同窓会の連携の礎を創った。 |
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 難波 治彦 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
教科・領域教育学専攻 自然系コース |
理科教材の自主開発並びに教育実践に長年携わり、理論と実験を融 合させた数々の理科指導法を確立した。これらの成果に対し、科学 振興に係る公的各機関から数多くの表彰を得ている。 |
| 池田 恩四郎 | 昭和59(1984)年3月 (3期生) |
教科・領域教育学専攻 自然系コース |
頻繁に開かれる市自然観察教室で児童生徒への現地指導を重ね、ま た、教員には教材開発や指導方法改善のための研修指導など、非常 に豊富な指導実績があると共に、教員育成にも貢献し続けている。 |
(五十音順、敬称略)
平成23年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成23年度に受賞されたのは、次の6名(嬉野賞2名、奨励賞4名)の方々です。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 臼井 英治 | 昭和58(1983)年3月 (2期生) |
教科・領域教育学専攻 社会系コース |
文化史専門領域の単著・編著を執筆、また論文を多数発表する。 岡山市文化奨励賞を受賞する。 |
| 河村 龍弌 | 昭和58(1983)年3月 (2期生) |
学校教育学専攻 教育経営コース |
教育研究者として、単著・共著・論文等を多数発表し、後進の指 導に顕著な実績を上げている。社会活動も広く展開し、青少年の 健全育成にも尽力する。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 浦辻 洋一 | 平成4(1992)年3月 (11期生) |
教科・領域教育学専攻 自然系コース |
自然観察研修、へき地教育実践の指導者として多種豊富な実績が あり、教員育成にも貢献する。関連叢書の分担執筆が頻繁である。 |
| 西住 徹 |
平成2(1990)年3月 |
教科・領域教育学専攻 社会系コース |
政治学博士。専門の日本現代政治学において、また教育学の研究 者として、単著・共著・論文等多数。 北村徳太郎研究の第一人者と評価されている。 |
| 林 保 | 昭和61(1986)年3月 (5期生) |
教科・領域教育学専攻 生活・健康系コース |
県中校長会長や全中校長会の要職を歴任する。教育実践研究レポ ートや編著書の執筆、また教育講演の実績が多数ある。 現在、熊野町教育長。 |
| 前田 紘二 | 平成2(1990)年3月 (9期生) |
教科・領域教育学専攻 芸術系コース |
合唱教育の普及に貢献した。主宰する音楽教育研修会が教師塾へ と発展し、人材育成にも大きな成果を上げる。 |
(五十音順、敬称略)
平成22年度 教育実践研究活動等に係る被表彰者
平成22年度の受章者は、次の8名(嬉野賞5名、奨励賞3名)の方々です。
| 嬉野賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 池田 芳和 |
昭和61(1986)年3月 |
教科・領域教育学専攻 社会系コース |
平成19年度全国連合小学校長会長を務め、マネジメント機能を最重 視した学校経営改革を全国規模で啓発推進した。 |
| 下山田 隆 | 平成8(1996)年3月 (15期生) |
教科・領域教育学専攻 自然系コース |
植物図鑑の共著執筆をはじめ、科学分野の教育研究また開発教材を 多く発表してきた。県内外の教育関係機関から研修指導の委嘱等を 受け、科学教育の普及活動に努めている。 |
| 武 泰稔 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
学校教育学専攻 教育経営コース |
岡山県小田郡矢掛町教育長。岡山県町村教育長会長、全国町村教育 長会副会長を務めるなど広く教育行政の推進に寄与している。 |
| 辰田 芳雄 | 昭和63(1988)年3月 (7期生) |
教科・領域教育学専攻 社会系コース |
日本中世史に関する研究は高く評価されている。高校教諭として教 材開発や教育実践が顕著であるとともに、発表する多くの論文で社 会科教育の充実に大きく貢献している。 |
| 壷内 明 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
学校教育学専攻 教育方法コース |
平成20年度全日本中学校長会長を務める。学習指導要領改訂移行期 の教育課程編成をはじめ学校経営の工夫について研究推進し、啓発 に尽力した。 |
| 奨励賞 | |||
| 氏 名 | 修了年月(期) | 専攻・コース名 | 受賞理由 |
| 梶谷 光弘 | 昭和63(1988)年3月 (7期生) |
学校教育学専攻 教育基礎コース |
華岡清州に師事した郷土の先人を研究することに発し、華岡流医 術の解明に至る研究業績によって、郷土史研究の発展に尽くした。 |
| 谷井 紀夫 | 平成元(1989)年3月 (8期生) |
教科・領域教育学専攻 言語系コース |
大学院在学当時から、短詩型表現力を育成する教育を追求してき た。指導法の工夫・開発と教育実践を重ね、短詩の普及と指導者 育成に果たした功績は大きい。 |
| 平松 義樹 | 昭和57(1982)年3月 (1期生) |
教科・領域教育学専攻 社会系コース |
教職研修の指導者として教員育成や学校支援に長年尽力し、教育 実践研究における第一人者と認められている。 |
(五十音順、敬称略)
※詳しくは,「兵庫教育大学大学院修了生等の教育実践研究活動等に係る表彰実施要項」をご覧ください。